【資料紹介94】通字(とおりじ) 大名友政から友禄まで

「江戸初期の切井村百姓への定書」
苗木の大名遠山家は初代友政から最後の12代友禄まで名に「友」を用いるのはなぜかと聞かれました。
江戸時代は幼名の後、通称と諱(本名)がありました。例えば、初代 久兵衞尉―友政、7代 左兵衞―友央、11代 刑部少輔―友寿、12代 美濃守―友禄です。読み方も通称は音読みで、諱は訓読み(和名)が多くなっています。
へりくだる意味で武士同士は一般に通称を用い、下位の者(百姓など)には諱を用いたようで、江戸初期の切井村百姓への定書には友政と諱が見られます。(写真)
諱は高位の人が配下の者に名の一字を譲る例があり、通字といいます。鎌倉時代の創始者源頼朝は重臣加藤景廉(かげかど)に遠山荘の地頭を命じましたが、その子景朝が恵那へ移り、地名の遠山を姓として遠山景朝と名乗りました。「朝」は頼朝から譲られ、父の景廉の景と併せ、景朝としたのでしょう。
しかし、北条氏は三代実朝を殺し、頼朝の系を絶ち北条政権を維持したので、景朝で始まる遠山家は「景」は用いたが「朝」の字は避けて「友」で代用しました。
明知では戦国時代に景友・友春・友治、岩村では友通(景任。苗木直廉の兄、共に1572年病死)が見られます。(「美濃国諸家系譜」)
恵那各地の遠山家は初代が景朝だったから「景」か「朝(とも)」を用いる例が多かったようです。飯場では、岩村第7代遠山景秀の弟景義が飯場城主の養子になりましたが、その子に実子なく友勝を養子としました。友勝は京都の三淵大和守の子でした。三淵・細川は名門で甥に細川藤孝(幽斎=孫の忠利が熊本城主)がおり、現在の細川家に至ります。なぜ飯場城主となり友勝を名乗ったかは不明ですが、信長に近く、苗木城主に命じられ、友勝の没後に子友忠はやはり信長の命で苗木城を後継しました。近代の「友」を諱とする苗木遠山家は友勝が祖(1572年~)であり、大名は友政から始まります。
大正時代、14代友郷(幼名:英彦)の急死で15代となった若き弟の健彦は友を通り字にするのをやめました。
中津川市博物館だより 恵那山 2025Vol.26.No.1掲載分
中津川市苗木遠山史料館
- 〒508-0101 岐阜県中津川市苗木2897-2
- 電話番号0573-66-8181
- ファックス0573-66-9290
- メールによるお問い合わせ






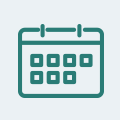
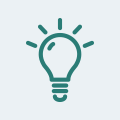







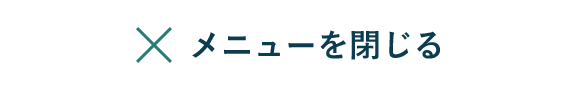
更新日:2025年04月01日