【資料紹介93】「高森書庫」と「遠山書庫」
「高森書庫」と「遠山書庫」
遠山史料館には旧藩主遠山家の蔵書が多数あり、「匏斉(ほうさい)」(11代遠山友寿)や「混々斉(こんこんさい)」(12代遠山友禄)の蔵書印が捺されているものもありますが、それと別に「高森書庫」・「遠山書庫」と朱色の角印(蔵書印)が捺されているものがあります。
「高森書庫」
高森書庫と捺された本は歴史の概説書が多い。出版の早いものは「日本王代」(1652年 全7巻)とか「将軍譜」(1658年7冊)、また「日本書紀」(1669年 7冊)等、江戸時代前期が見られるが、多くは江戸時代後半の出版です。 一般には耳慣れない「逸史」(1779年13冊)とか「百練抄(ひゃくれんしょう)」(1803年14冊)もあるが、「校刻日本外史」(22冊)や「皇朝史略」(1826年10冊)、「国史纂論」(1846年10冊)等、歴史の概説書と思われるものが多いです。
遠山文書の蔵書の多くは藩主の真摯な歴史研究を補助する版本でした。 漢詩に関心が深かった友禄らしい一部の書物にも「高森書庫」蔵書印が見られます。
「遠山書庫」
「高森書庫」と比較すると、蔵書印「遠山書庫」はさほど多くはありません。「日本政記」(1861年16冊)、「南木誌」(1864年 5冊)、「近世史略」(1872年3冊)「続国史略」(1873年5冊)、「続国史略 後編」(1874年 5冊)、「国史攬要」(1874年 16冊)でやはり歴史の概説書といえますが、出版が幕末から維新の物が多くなっています。
幕末・維新の苗木遠山友禄は藩政改革に多忙で、概論書の蒐集に掛かるゆとりはありませんでした。明治2(1869)年の版籍奉還、4年の廃藩置県で、大名から知事、そして放免となり、華族として東京で余生を過ごす事になりました。明治4年以降は、東京で個人として蔵書印「遠山書庫」を使用したのではないでしょうか。
恵那山 2024Vol.25No.4掲載

高森文庫

遠山文庫
中津川市苗木遠山史料館
- 〒508-0101 岐阜県中津川市苗木2897-2
- 電話番号0573-66-8181
- ファックス0573-66-9290
- メールによるお問い合わせ






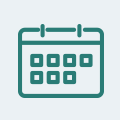
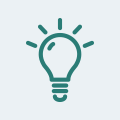







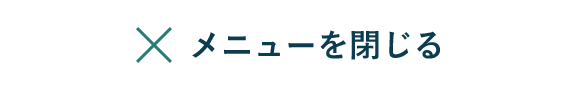
更新日:2025年01月30日