中津川市の指定文化財

中津川市内の文化財、史跡、名勝、天然記念物などを紹介します。
中津川市指定文化財が2件新規指定されました!
令和5年8月16日付で、以下の2件が市指定文化財に指定されました。
- 市指定有形文化財(美術工芸品) 「太刀 銘 政秀 附 太刀拵」(付知)
- 市指定史跡 「坂下の磨崖仏」 (坂下)
文化財一覧
| 有形文化財 |
| 無形文化財 |
| 有形民俗文化財 |
| 無形民俗文化財 |
| 史跡 |
| 名勝 |
| 天然記念物 |
有形文化財
国指定(3件)
| 名称 | データ | 解説 |
|---|---|---|
|
(たち めい びぜんのくにおさふねじゅうちかかげ)
|
員数:1 長さ72.5センチメートル 反り1.8センチメートル 時代:鎌倉 指定年月日:昭和3年4月4日 所在地:中津川市苗木2897-2(苗木遠山史料館) マップ:googleマップ 所有者、保持者等:神明神社 |
この太刀は、備前国長船の名工長光門下の刀匠の1人であった近景の銘が入っており、安永3年(1706)、苗木領主第9代遠山友清が神明神社に寄進したものです。 |
|
(たち めい よしのり)
|
員数:1 長さ75,6センチメートル 反り2,6センチメートル 時代:室町 指定年月日:昭和3年4月4日 所在地:中津川市苗木2897-2(苗木遠山史料館) マップ:googleマップ 所有者、保持者等:榊山神社 |
鎌倉後期から南北朝時代にかけての刀匠、山城国三条の住人「吉則」の作刀です。三条派吉則の製作で現存するのはきわめて少なく、国の重要文化財の指定を受けているのは、この太刀一口のみです。磨き上げがあり、茎尻に刻銘があります。 |
|
(もくぞうやくしにょらいざぞう)
|
員数:1 像高0.51メートル 時代:平安 指定年月日:大正14年4月24日 所在地:中津川市東宮町 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:東円寺 |
この像は、曹洞宗寿福山東円寺の本尊で、右手をあげ、左手が掌を上に膝の上にのせ、薬壺を持っています。制作当時金漆塗りでありましたが、現在は金色はほとんど見当たりません。この薬師如来を安置したお堂の前を馬に乗って通行すると必ず落馬するので、その向きを変えたため、「後ろ向き薬師」と言われています。 |
県指定(6件)
| 名称 | データ | 解説 |
|---|---|---|
|
(じゅうろくらかん)
|
員数:16 絹本 仏画寸法:長さ約1メートル 幅約43センチメートル 時代:室町 指定年月日:昭和33年7月16日 所在地:中津川市付知町7096 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:寶心寺(ほうしんじ) |
十六羅漢画像(16幅)は室町時代初期の画僧・明兆作です。明兆は宋・元の画風を研究し、肥痩のある墨線とやや暗い色調による力強い画風を確立し、多くの仏画や頂相(ちんぞう:禅宗高僧の肖像)を描きました。題材は釈迦の亡き後を託された十六人の弟子を描いたものです。かつては、大阪府岸和田市の真言宗久米田寺にありましたが、所有者が転々とした末に寶心寺の寺宝となりました。 |
|
太刀 銘貞綱(中津) (たち めい さだつな)
|
員数:1 長さ76.2センチメートル 反り3.6センチメートル 時代:平安 指定年月日:昭和44年8月5日 所在地:中津川市苗木2897-2(苗木遠山史料館) マップ:googleマップ 所有者、保持者等:恵那神社 |
太刀の力匠の貞綱は寛弘頃の人と伝えられ、「恵那神社誌」によると源義仲が奉納したものと記されています。 |
|
(もくぞうえんのぎょうじゃざぞう)
|
員数:1 像高100センチメートル 時代:室町 指定年月日:昭和40年9月7日 所在地:中津川市坂下大門1124-2 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:蔵田寺 |
蔵田寺の役行者は特異な風貌で、怪異で凄味があり、役行者の烈しい風格を表しています。 |
|
(もくぞうしゃかにょらいざぞう)
|
員数:1 像高46.5センチメートル 台座高54.0センチメートル 光背高79.5センチメートル 時代:室町後期 指定年月日:昭和40年9月7日 所在地:中津川市坂下大門1124-2 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:蔵田寺 |
本像は元々、坂下の萬蔵山長昌寺の本尊として尊崇されていましたが、明治初年に出された廃仏令のため福岡下野地区の良雲山法界寺に移されました。その後、復旧された蔵田寺に安置されています。 螺髪は通例の様式と異なり、簡略された彫り方をしており、釈迦如来像として異例です。 |
|
木造馬頭観世音菩薩像(阿木) (もくぞうばとうかんぜおんぼさつぞう)
|
員数:1 像高30センチメートル 時代:室町 指定年月日:昭和44年1月22日 所在地:中津川市阿木101-1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:萬嶽寺 |
この像は、市内手賀野の天台宗龍泉寺の本尊であったが、天正2年(1574)武田勝頼が同地の阿寺城を攻略した際、辛うじて消失の難をまぬがれ、現在の萬嶽寺に安置されるに至ったと伝えられています。月馬を頭に頂き、念怒の相をし、三面八臂の坐像であります。 |
|
(もくぞうやくしにょらいざぞう)
|
員数:1 像高0.34メートル 時代:南北朝~室町 指定年月日:昭和40年9月7日 所在地:中津川市上野本郷433 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:磯前神社 |
旧薬王山東光寺の本尊とされる。桧の寄木造で縦横一尺一寸の仏所造と言われています。彫刻時期は南北朝時代末~室町時代とされる。かつては脇に月光・日光菩薩を持っていたと考えられるが、現在は独尊となっている。木像は上部漆と金箔が重ねられていたが、腐食がすすみ、近年解体修理された折、台座に北朝年号があったと言われるが、詳細は不明。 |
市指定(107件)
| 名称 | データ | 解説 |
|---|---|---|
|
(おりべとうろう)
|
員数:1 時代:慶長期~元和期 指定年月日:昭和57年4月8日 所在地:中津川市新町7-39(間家大正の蔵敷地内) マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
織部燈籠は、織部流茶道の祖古田織部正重然が考案したものといわれ、別名キリシタン燈籠ともいわれています。この燈籠がキリシタン遺物であったか否か確証はありません。 |
|
(そうとういっしんどうそじん)
|
員数:1 時代:文化13年(1816) 指定年月日:昭和57年4月8日 所在地:中津川市駒場397-2 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
この道祖神は、通称「こでの木」といわれる、中山道から脇街道の苗木道への分岐点に、文化13(1816)年3月、藤四郎、長蔵両名により建立されたものです。男女別々の頭部をもち、肩から足元にかけて一体となっています。 |
|
(きゅうはざまけそうこ)
|
員数:1棟 時代:大正6年頃 指定年月日:平成7年2月16日 所在地:中津川市中津川1940-4 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
鉄筋コンクリート地上3階建て、延べ床面積208.52平方メートル。この倉庫は、東濃随一の豪商といわれた中津川宿の間家のもので、現在は「間家大正の蔵」として一般に公開されています。 |
|
(そがけじゅうたく)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:平成17年1月26日 所在地:中津川市本町2-6-44 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
江戸時代には肥田家が庄屋を勤めながら旅籠屋「田丸屋」を営んでいました。 明治中期以降に曽我家が入り医院を開業され、部屋の一部が診察室として使用されていました。 通りの向かいに本陣があり、東隣に脇本陣がある宿場の中心地に位置しています。 |
|
(かんぜおんぼさつざぞう)
|
員数:1 像高15センチメートル 時代:鎌倉 指定年月日:昭和31年4月1日 所在地:中津川市えびす町 所有者、保持者等:個人 |
この像は、左手に蓮華を持ち(現在は紛失)、右手は印を結ぶ遊戯坐像で、念持仏であるため小像であります。裳に当時のものと思われる金箔の文様が残っています。 |
|
(もくぞううすしまみょうおうりゅうぞう)
|
員数:1 像高56センチメートル 時代:江戸 指定年月日:昭和46年10月28日 所在地:中津川市手賀野603 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:松源寺 |
この像は、6臂の忿怒形で火炎光背を背に蓮台に立っています。6臂にはそれぞれ持物をもち(一部欠失)、本体は種々の顔料で彩色されています。もとは苗木領内にあったといわれ、明治初期の廃仏毀釈の折に松源寺に移されました。 |
|
(どうぞうたんじょうぶつ)
|
員数:1 像高84センチメートル 重量26.5キログラム 時代:江戸 指定年月日:昭和46年10月28日 所在地:中津川市東宮町8-12 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:東円寺 |
上半身裸体、下半身に裳をまとい右手をあげ天を指さし、左手を垂下し地を指して立った非常に大きな銅造の誕生仏です。 |
|
(ほけきょうはちのまき)
|
員数:8 時代:江戸 指定年月日:昭和57年7月22日 所在地:中津川市中津川841-4-1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:長久寺(ちょうきゅうじ) |
この経文「八の巻」は苗木にあった正中山佛好寺(日蓮宗)の所有であったが、廃仏毀釈により灰になるところを、信者によって難をのがれ、妙見山長久寺に移され、伝来したものです。文字数69,384文字といわれています。 |
|
|
員数:2 時代:江戸中期 指定年月日:昭和59年4月18日 所在地:中津川市苗木2897-2(苗木遠山史料館) マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
朱札色々糸縅二枚胴具足、勝糸縅横矧五枚胴具足の2領で、苗木遠山家に代々伝わり、丸に二引きの紋が所々にちりばめられています。 |
|
(なえぎはんしやすだたざえもんいしょ・せんめん)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和54年4月24日 所在地:中津川市苗木2897-2(苗木遠山史料館) マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
苗木領主第5代遠山友由の忠勤を励んだ側近で、領主の死を悼み、その後を迫って、享保7年(1722)5月11日殉死した安田太左衛門の遺書と辞世の句が書かれた扇面です。 |
|
(なえぎりょうしゅれきだいしょうぞうが)
|
員数:11 時代:江戸 指定年月日:昭和59年4月18日 所在地:中津川市苗木2897-2(苗木遠山史料館) マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
苗木領主遠山家の初代友政から11代友寿までの肖像画です。同一年代に製作されたと思われるものもありますが、歴代領主の肖像画が揃っている例は極めて希です。 |
|
(あらしさぬきのくようひ)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:平成14年4月24日 所在地:中津川市千旦林42-1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
嵐讃岐は木曽家の有力武将の一人で、千旦林に居をかまえ、千旦林八幡宮(八幡神社)の再建につくした人と伝えられています。 この供養碑は、寛永3年(1626)に嵐讃岐を供養するために建てられたもので、中世から近世にかけての墓石様式の変遷をあらわすものとして貴重であり、岐阜県内でもめずらしい様式です。 |
|
(もくぞうこまいぬいっつい)
|
員数:2 像高55センチメートル 時代:鎌倉 指定年月日:昭和42年3月24日 所在地:中津川市千旦林642-1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:八幡神社 |
横向きの狛犬で、彩色はおちています。銘がない為、作者・年代は不明ですが、桧の寄木細工であることから、鎌倉末期の作と推定されます。 |
|
(もくぞうごしんたいぞう)
|
員数:13 像高20~33センチメートル 時代:室町 指定年月日:昭和42年3月24日 所在地:中津川市千旦林642-1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:八幡神社 |
神像11体、僧像2体の内、笏持ち神像6体、衣冠服装10体、顎髭御顔9体。すべて木彫(一本彫り)桧材を用いた彫刻で、腰高な形が多いです。像の底部に「観応三年」(1352)の年季の記入のあるものが6体ほどあります。 |
|
(わきざし めい やまとのかみよしみち)
|
員数:1 刃長39.2センチメートル 反り0.6センチメートル 元幅3.04センチメートル 元重0.8センチメートル 時代:江戸 指定年月日:平成14年4月24日 所在地:中津川市落合 所有者、保持者等:個人 |
明治時代初期、旧湯舟沢村の庄屋であった島田家が、信州伊那地方から入手したものです。刃文に桜花の姿が見え、芸術史上重要な刀剣です。 |
|
(もくぞうじゅういちめんかんのんりゅうぞう)
|
員数:1 像高100センチメートル 時代:江戸 指定年月日:昭和39年2月20日 所在地:中津川市阿木5865 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:長楽寺 |
この像は、長楽寺の本尊で、戦国争乱の時代、武田氏の軍勢がこの地を侵攻した時に、川へ投げ捨てられたが、拾い上げられ十二坊のひとつ梅本坊に安置されたといわれています。扉を開くと災害が起きるといわれ、秘仏として一般公開されていません。 |
|
(しょうかんぜおんぼさつざぞう)
|
員数:1 像高80センチメートル 時代:江戸中期 指定年月日:昭和59年5月23日 所在地:中津川市阿木101-1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:萬嶽寺 |
この仏像の作風は、定朝様式を写していますが、造像の細部にわたって見ると、江戸中期の特徴が多くみられます。仏像の裏面には「宝永元年正月八日」の銘記があります。 |
|
(おおびょうもいせきしゅつどじょうもんどき)
|
員数:1 器高50センチメートル 時代:縄文中期 指定年月日:昭和44年3月24日 所在地:中津川市飯沼505-1-2 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:禅林寺(ぜんりんじ) |
昭和42年に阿木飯沼大日向(おおびょうも)遺跡から出土したものです。出土状況からみて幼児を埋葬したものではないかと推定されます。 |
|
(ちょうらくじのはじき)
|
員数:1 器高29.5cm 時代:奈良前期 指定年月日:昭和39年3月24日 所在地:中津川市阿木5865 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:長楽寺 |
長楽寺裏東南の小高い山の上の経塚から出土したもので、経文を納めて埋めた奈良時代前期のものとされています。 |
|
(じりょうのかいゆうすいびょう)
|
員数:1 器高21.8センチメートル 時代:平安 指定年月日:平成元年3月7日 所在地:中津川市阿木33 阿木コミュニティセンター マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
昭和46年中津川市阿木公民館の建設工事中に発見されたもので、良く原形を保っています。素地は鉄分の多い、やや粗い土で、黒褐色を呈します。 |
|
|
員数:7 時代:鎌倉後期~室町後期頃 指定年月日:昭和63年10月18日 所在地:中津川市馬籠 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
この付近は発掘調査により鎌倉後期~室町後期にかけての寺院跡であったことが確認されています。この五輪塔も同時期の形態を整え、近在に現存する他の五輪塔に比較して形も大きく梵字も刷毛書で秀逸です。 |
|
(えいしょうじのしょうめんこんごうこうしんとう)
|
員数:1 碑の高さ68センチメートル 幅35センチメートル 時代: 指定年月日:平成5年6月3日 所在地:中津川市馬籠5358 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:永昌寺 |
舟形光背に高彫りで庚申信仰の主尊である青面金剛王の合掌像が刻まれています。像は六臂で二臂は合掌、他に宝棒などを持っています。 |
|
(もくぞうあみだにょらいざぞう)
|
員数:1 像高58センチメートル 膝張47.5センチメートル 時代:平安 指定年月日:昭和63年10月18日 所在地:中津川市馬籠5358 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:永昌寺 |
檜材の1本作りで、平安時代末期(12世紀末)の作品で、漆箔を施した痕が頬や膝前に残っています。 |
|
(もくぞうしょうかんのんりつぞう)
|
員数:1 像高53センチメートル 時代:江戸前期 指定年月日:昭和63年10月18日 所在地:中津川市馬籠5358 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:永昌寺 |
円空上人(1632~95)の作った仏像で、横顔の美しいすんなりした立像です。微笑を含んだ顔は優美だが、全体からは円空独特の行動的な作風が感じられる仏像です。 |
|
(しほんぼくしょだいはんにゃきょう)
|
員数:2 指定年月日:昭和63年10月18日 所在地:中津川市馬籠5358 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:永昌寺 |
大般若経を写経したもので、全600巻の内、巻第410と巻450の2巻が現存しています。表紙は漆の刷毛塗りで、室町初期またはそれ以前に写経されたことが推定できます。 |
|
(こやすかんのんぞう)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和55年4月30日 所在地:中津川市坂下高部(高部観音堂) マップ:googleマップ 所有者、保持者等:高部自治会 |
本尊は、苗木藩の最後藩主遠山友禄の室が、九州島津家の分家である佐土原三万石から嫁いできた際に、念珠仏として苗木に持ち込まれた。明治初年廃仏毀釈で折焼き払われる運命であったが、藩公の乳人から暗黙の約束の中に、本尊を高部の同志とともに苗木から迎えた。江戸時代初期に、九州若しくはさらに南方の地域の材を用いて造仏されている。高部観音堂に安置され、安産の霊験あらたかと評判も高い。 |
|
(ほんぞんじゅういちめんかんぜおんぼさつとさんじゅうさんかんのんぞう)
|
員数:1と53 時代:江戸 指定年月日:平成5年3月25日 所在地:中津川市坂下握 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:握自治会 |
かつて東向山光宗寺の観音堂にいずれも安置されていた。光宗寺は中世後期に創立された寺で、西芳寺が天正10年焼失した後、これをよく補佐して興したと伝承されている。本尊十一面観世音菩薩は享保16年下組庄屋吉村八郎右衛門朝貞の発願に田立禅東院の住職により開眼された巨像であることが記録に見える(一本彫)三十三観音は下組庄屋吉村八郎右衛門多吉秋信と田口?兵衛が先導者となり、寛保3年から造仏。明治初期にかけて補修、解体、修理されていたことが文献に残る観音講、月待講などによって保存、安置されている。 |
|
|
員数:1 高さ2.91メートル 花崗岩 時代:正徳3年 指定年月日:昭和53年2月27日 所在地:中津川市川上 所有者、保持者等:個人 |
十三仏塔とは、死者の追善の法事を修めるとき、その年忌に配当された13の仏菩薩を信仰するものです。 正徳3年(1713)原嘉兵衛政勝の発願により、村中48人が寄進協力して造立されました。 13の仏像は浮彫りで坐像です。造立当時は露天に安置されていましたが、後に堂宇に納められました。 |
|
(あみだにょらいぞう)
|
員数:3 時代:元禄12年 指定年月日:昭和53年2月27日 所在地:中津川市川上362番地 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:田之尻地区 |
|
|
|
員数:1 時代:正保4年(1647) 指定年月日:昭和60年2月20日 所在地:中津川市川上 所有者、保持者等:個人 |
正保4年(1647)の造立で、川上地区では最古の石造物です。 龕部(がんぶ)の1面に1体ずつ6体が浮彫りされていますが、稚児の姿で簡略化された彫刻になっていて、6仏がみな微笑みをたたえています。 |
|
(かんぜおんぼさつ) |
員数:33 時代:宝永5年 指定年月日:昭和53年2月27日 所在地:中津川市川上 所有者、保持者等:個人 |
|
|
(きんせいこもんじょ) |
員数:458 時代:江戸時代 指定年月日:昭和60年2月20日 所在地:中津川市川上 所有者、保持者等:個人 |
|
|
(おおすぎじぞうそんのしょうろう)
|
員数:1 時代:明治 指定年月日:昭和55年1月17日 所在地:中津川市加子母小郷 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:大杉地蔵尊世話人会 |
一重の入母屋造りで間口6.3メートル、奥行き5.9メートル、高さが7.8メートルあり、明治35年(1902)に加子母村法禅寺の小川覚道住職が建立しました。 |
|
(かしもむらきょうどかん(きゅうやくば))
|
員数:1 時代:明治27年(1894) 指定年月日:昭和58年4月22日 所在地:中津川市加子母上桑原 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
明治27年(1894)に村役場として建築されたものを、昭和60年(1985)に改装して郷土館にしたものです。木造瓦葺二階建ての洋風建築で明治時代の代表的な役場建築を伝える貴重な建物です。 |
|
(しゃかのねはんず)
|
員数:1 指定年月日:平成9年3月5日 所在地:中津川市加子母小郷 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:大杉地蔵尊世話人会 |
加子母村小郷区の大杉地蔵尊が所蔵する作品で作者は不明です。 |
|
|
員数:1 時代:江戸時代 指定年月日:平成9年3月5日 所在地:中津川市加子母小郷 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:大杉地蔵尊世話人会 |
小説家で参議院議員でもあった今東光(こんとんこう)が来村し、大杉地蔵尊を参詣した際に、渓斎英泉(けいさいえいせん)の作品であるから大切に保管するように言った作品です。 英泉は江戸後期に活躍した浮世絵師で、歌川広重と「木曽海道六十九次」を製作しました。 |
|
|
員数:3 指定年月日:平成9年3月5日 所在地:中津川市加子母小郷 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:大杉地蔵尊世話人会 |
|
|
(しゃかにょらいぞう(えんくうぶつ))
|
員数:2 時代:江戸 指定年月日:昭和51年7月20日 所在地:中津川市加子母小郷 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:大杉地蔵尊世話人会 |
貞享3年(1686)の円空の作と言われています。 戦後この大杉地蔵尊は地域の子ども達の遊び場所であり数体あった円空仏を子ども達が遊び道具として使い、だんだん数が減り現在は2体しか残っていません。 |
|
(じぞうぼさつぞう)
|
員数:1 時代: 指定年月日:昭和51年7月20日 所在地:中津川市加子母小郷 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:大杉地蔵尊世話人会 |
|
|
(しょうぎたいのず)
|
員数:1 130×111センチメートル 牧野伊三郎、油彩 時代:明治25年 指定年月日:昭和53年10月13日 所在地:中津川市付知町4956-43 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
旧恵那郡付知町出身の洋画家牧野伊三郎の作品です。江戸上野の寛永寺で討幕軍と戦う彰義隊をモチーフにしたこの絵は、日本における油絵作品としてはもっとも古いもののひとつで、明治26年(1893)春の明治美術会展に出品され評判になりました。 これにより伊三郎は、同会の通常会員に推挙されました。 |
|
(ひゃくしょくにんのず)
|
員数:1 三尾暁峰 61×137センチメートル 指定年月日:平成2年9月14日 所在地:中津川市付知町 所有者、保持者等:個人 |
幕末の職人の働く姿を軽妙な動きのある筆づかいで描き、百人の表情ある職人が画面に配置されています。幕末の生活や風俗をうかがうことができる貴重な作品です。 |
|
(しょくのさんどうのず)
|
員数:1 三尾暁峰 紙本水墨淡彩・軸装 128×76センチメートル 時代:江戸 指定年月日:平成2年9月14日 所在地:中津川市付知町 所有者、保持者等:個人 |
弘化4年(1847)暁峰45歳の作です。山深く険しい蜀の仙境を、繊細な筆使いと力強い構図で表しています。暁峰の充実期の作品です。 |
|
(じゅうろくらかんず)
|
員数:1 三尾暁峰 紙本水墨淡彩・軸装 97×162センチメートル 指定年月日:平成2年9月14日 所在地:中津川市付知町 所有者、保持者等:個人 |
さまざまな向きの羅漢を画面全体に配置し、一人ひとりの羅漢の心情をうまく顔に表現した作品です。暁峯が得意とした独特の虎も画面に配置されています。 |
|
(ひゃくろうじんのず)
|
員数:1 三尾暁峰 紙本水墨淡彩・軸装 135×98センチメートル 指定年月日:平成2年9月14日 所在地:中津川市付知町 所有者、保持者等:個人 |
表情豊かな百人の老人を、習熟した動きのあるタッチで描写し、遠近感も良く表現された作品です。 |
|
(じゅうにしとろうじんのず)
|
員数:6曲1双 屏風 三尾暁峰 紙本水墨淡彩 46×121センチメートル 時代:江戸 指定年月日:平成2年9月14日 所在地:中津川市付知町 所有者、保持者等:個人 |
十二支と花鳥及び寿老人をそれぞれの画面に配置し、色の冴えた格調の高い色調でまとめられた作品です。熟練した暁峰の画技がうかがわれる優品です。 |
|
(くじゃくとつるのず)
|
員数:6曲1双 屏風 三尾暁峰 紙本水墨彩色 60×169センチメートル 指定年月日:平成2年9月14日 所在地:中津川市付知町 所有者、保持者等:個人 |
孔雀と鶴の動きを右隻、左隻に表わし、写実的描写に優れた作品です。対角線に対象物を取り入れ、余白の処理にも工夫が見られた品格のある作です。 |
|
(うんりゅうのず)
|
員数:8 襖 三尾暁峰 紙本水墨淡彩 110×78センチメートル 指定年月日:平成2年9月14日 所在地:中津川市付知町3184 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:宗敦寺(そうとんじ) |
「阿」「呍」の龍を配置し、大胆な構図で動きのある龍を描き、力強く迫力のある絵です。「暁峰龍」の代表作です。 |
|
(かちょうのず)
|
員数:4 三尾暁峰 紙本水墨淡彩・襖 110センチメートル×178センチメートル 時代: 指定年月日:平成2年9月14日 所在地:中津川市付知町3184 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:宗敦寺(そうとんじ) |
雲龍図と同じ宗敦寺方丈の襖絵です。緻密な写生に基づく、品格のある落ち着いた作です。 |
|
|
員数:1 21.5cm×32cm 時代:大正2年 指定年月日:平成14年3年4月 所在地:中津川市付知町4956-43 所有者、保持者等:中津川市 |
付知町出身の熊谷守一画伯からの寄贈された作品です。 守一が明治43年(1910)から大正4年(1915)までの付知の実家に戻ってる時に描かれたもので、大正4年(1915)の第2回二科展覧会に出品されました。 |
|
(もくぞうあみださんぞんとずし)
|
員数:4 時代:寛永2年以前 指定年月日:昭和49年12月3日 所在地:中津川市付知町3133 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:阿弥陀堂 |
三尊像とは、阿弥陀如来とその両脇に脇侍する観音と勢至の両菩薩のことであり、総ケヤキ造りの厨子に安置されています。 寛永2年(1625)の庄屋家文書にもこの阿弥陀如来のことが記録されており、付知地区では古い仏像の一つです。 |
|
(もくぞうせんたいやくしりゅうぞうならびにきょうじぞうとひぼかんのん)
|
員数:969 サワラ材 時代:寛政年間 指定年月日:昭和49年12月3日 所在地:中津川市付知町寺山 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:寺山薬師堂 |
下付知の医者・田口廣林が約6年かかって自力で彫りあげたものです。 薬師如来は医薬をつかさどる仏で、この千躰仏造りは信仰心が厚く慈悲深い廣林の人柄をよくあらわしています。 |
|
(もくぞうしょうめんこんごうそんりつぞう)
|
員数:1 時代:元和4年(1618) 指定年月日:昭和49年12月3日 所在地:中津川市付知町鳥屋脇 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:鳥屋脇庚申堂 |
青面金剛(庚申)とは、帝釈天の使者で顔色が青い金剛童子のことです。 |
|
(もくぞうじゅうおうそんざぞう)
|
員数:10 時代:江戸中期 指定年月日:昭和51年1月20日 所在地:中津川市付知町御堂後 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:辻堂観音堂 |
いずれも桧寄木造りで着色がしてあり、ガラス目玉が入っています。作者も製作年代も不明ですが、第八王の背面に「天保14年(1843)再彩色」と記されていますから江戸時代中期の作と考えられます。 |
|
(もくぞうしょうかんぜおんざぞう)
|
員数:1 像高50.5cm 時代:14世紀末 指定年月日:平成11年1月19日 所在地:中津川市付知町3184 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:宗敦寺(そうとんじ) |
宗敦寺の聖観世音坐像は、中世に多く見られる作例とは異なり、一本の丸太から製材した(共木)を用いて製作しています。 |
|
(とうせいこまいぬ)
|
員数:1対 雄44センチメートル 雌43センチメートル 時代:宝永4年 指定年月日:昭和49年3月26日 所在地:中津川市付知町字富田3875 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:水無神社 |
水無神社が所有する一対の陶製の狛犬です。作者や生産地について詳しいことは不明ですが、雄の背中部分に「奉寄進 付知村一之宮 願主三尾善六郎 宝永四年(1707)亥五月吉日」 とあります。 残念ながら、雌雄とも耳が欠損してしまっています。 |
|
(とうけん(かねもと))
|
員数:1 銘、兼元 刃長63.7センチメートル 反り1.6cm 時代:室町中期 指定年月日:平成2年9月14日 所在地:中津川市付知町 所有者、保持者等:個人 |
美濃鍛冶と呼ばれる刀工で、古くは南北朝時代に始まり、室町時代から幕末までの約700年にわたり、現在の関市方面で活躍した刀工集団による作品です。 |
|
(とうけん(のさだ))
|
員数:1 銘 兼之(之の上にウ冠) 刃長65.4センチメートル 時代:室町中期 指定年月日:平成2年9月14日 所在地:中津川市付知町 所有者、保持者等:個人 |
刀銘「濃州関住 兼之(之の上にウ冠)作」。兼之が「和泉守」を受領する前の明応(1492~1501)か文亀(1501~1504)年間の作と推測される。 |
|
(とうけん(けんのさだ))
|
員数:1 銘 濃州関住 兼之(ウ冠に之) 刃長22.6cm 時代:室町中期 指定年月日:平成5年9月8日 所在地:中津川市付知町 所有者、保持者等:個人 |
美濃国関の刀工「和泉守兼定」の作です。兼定は孫六・兼元と並んで室町時代の美濃鍛冶の双璧でした。刀の銘に「定」の字のウ冠の下を「之」と切るので、通称「之定(のさだ)」といいます。 |
|
(けっしょだいじょうみょうてん)
|
員数:8 時代:寛政3年 指定年月日:昭和51年1月20日 所在地:中津川市付知町3184 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:宗敦寺(そうとんじ) |
大乗妙典は、大乗仏教の経典のうち聖(妙)典と称されている法華経をさすといわれています。 この大乗妙典は、寛政3年(1791)、宗敦寺第6世住職・偃渓玄松和尚が、村人の幸福と平和を願って自分の血液を混ぜた朱墨で写経したものです。そのため現在でも、経典の文字は薄茶がかった朱色です。 |
|
(しほんじゅうさんにんぼくせき)
|
員数:1 掛軸 内法40.5cm、丈110.5cm 時代:室町・文明6年(1474) 指定年月日:昭和51年1月20日 所在地:中津川市付知町3184 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:宗敦寺(そうとんじ) |
室町時代の15世紀末頃、五山文学の文学僧13人が寄せ書きした詩文です。五山文学は京都五山(南禅寺、建仁寺、東福寺、建長寺、円覚寺)の禅僧が禅宗の教えの真理を漢文にまとめたものです。 箱に「六世、偃渓補修」とあることから、彼が在任した安政末期~文政初期に補修されています。 |
|
(しほんぼくせきはくいんぜんじしょ)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和51年1月20日 所在地:中津川市付知町3184 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:宗敦寺 |
和紙「達磨絵と讃」129cm×59cm内寸で「直指人心、見性正佛(成仏)」と読む |
|
(しほんぜんとくざんそうとんじじゅっきょうのじゅっとく)
|
員数:1 時代:寛文10年 指定年月日:昭和51年1月20日 所在地:中津川市付知町3184 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:宗敦寺(そうとんじ) |
宗敦寺開山・魏海宗活和尚が、本堂完成と開山を慶賀し、その本堂から眺めた付知村の四季の景を踏まえて、自分の仏教観を述べた自作詩です。 |
|
(きがく・はくいんぜんじしょ)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和55年2月9日 所在地:中津川市付知町3184 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:宗敦寺(そうとんじ) |
白隠禅師が、宝暦8年(1758)に宗敦寺へやってきたとき筆をふるったのが「達磨絵と讃」および「寺門額」の文字で、その内の一点です。 |
|
(かんぽう、らんぽういがくのかんぽん、しゃほん)
|
員数:304 時代:天正5年 指定年月日:昭和56年4月18日 所在地:中津川市付知町 所有者、保持者等:個人 |
三尾家(大黒屋)は、3代、約150年間にわたり付知村で医者として活躍しました。この当時に学んだ医学・医術関係の本や写本です。 |
|
(しょじごはっとしなじなむらじゅうれんばんちょう) |
員数:130 時代:明和6年~明治7年 指定年月日:昭和51年1月20日 所在地:中津川市付知町 所有者、保持者等:個人 |
所有者の先祖が、明治5年に、一時的に付知村が3カ村に分かれた時、東付知村庄屋になり、元の1カ村に戻ったときは副村長になった関係もあり、川東地域に関する文書が多いことが特徴である。 |
|
(つけちむらひゃくしょうこうじょうしょ)
|
員数:1 時代:宝永7年 指定年月日:昭和51年1月20日 所在地:中津川市付知町 所有者、保持者等:個人 |
尾張藩領であった付知村は、加子母村・川上村と合わせて「裏木曽三ヶ村」と呼ばれ、藩の厳しい林政管理下にありました。 田畑の少ない付知村は、年貢を米麦で納める代わりに木で納める(板子年貢)が認められていました。 しかし、天和2(1682)年に加子母村が米納に切りかえられる事態が起きました。付知村も米納になることを危惧した百姓は、宝永7(1710)年に嘆願の口上書を作り提出しました。 |
|
(ごけんやくおふれがき)
|
員数:131 時代:文政5年~明治5年 指定年月日:昭和51年1月20日 所在地:中津川市付知町 所有者、保持者等:個人 |
文政5年(1822)から明治5年(1976)に至る公家御法度、村掟、宗教、祭礼、人別増減など、付知村および村民生活の実際を示す証文です。 |
|
(きんせいしょうやかんけいもんじょ)
|
員数:1410 時代:慶長16年~慶応 指定年月日:昭和53年10月13日 所在地:中津川市付知町 所有者、保持者等:個人 |
明治以降代々の当主の努力により、膨大な資料の整理が今日に至るも、なおすすめられている。とりあえず1,410点が昭和53年に町指定されたものである。 |
|
(きんせいようすいかんけいもんじょ)
|
員数:215 時代:寛政~慶応 指定年月日:昭和53年10月13日 所在地:中津川市付知町 所有者、保持者等:個人 |
215点が昭和53年に町指定となった。 江戸時代後半、付知村で「5大用水=鱒渕、西股、宮沢、北、荏薙用水」がつくられた。その頃の付知村は日本一といわれるヒノキなどの産地であること東美濃と飛騨、信州を結ぶ重要通過地点であったが、村人口が増加するのに、それを支える農業生産力が劣っていた。目の前に水量豊富な付知川が流れているにもかかわらず、40~50メートル下を流れるため、平坦地があるが、かんがい水が少なく田畑つくりが進まなかったためである。何度もの工事の失敗、資金が足りない状況で20年余りかけ、ついに完成させた。 |
|
(きんせいむらかたもんじょ)
|
員数:212 時代:安永9年 指定年月日:昭和56年4月18日 所在地:中津川市付知町 マップ: 所有者、保持者等:個人 |
天保の飢饉などで、困っている村人の救済や庄屋田口慶郷の用水開削に大きな協力を行ったので、尾張藩から宗門自分一札、一代切帯刀御免を許された。江戸中期が多く、証文類など当時の生活ぶりがうかがえる貴重な文書である。 |
|
(しほんそうとんじえんかくりゃっき)
|
員数:1 時代:明治元年 指定年月日:昭和61年9月12日 所在地:中津川市付知町 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:宗敦寺 |
廃仏毀釈騒動で宗敦寺も当時の檀家の7割が、改宗の届を連名で県に提出し、寺存続の危機を迎えた。子供のころ宗敦寺の小僧として育った静岡の清見寺の僧である坂上宗詮(真浄)は、この危機を救おうと寺子屋時代の仲間とともに届を出した檀家を1件1件説得に回った。この護持運動のおかげで、改宗の願いは取り下げられ、宗敦寺は元の姿に戻りました。この護持運動を顕彰して記したものである。 |
|
(きんせいもんじょおよびきんだいもんじょ)
|
員数:83 時代:寛文7年~明治元年 指定年月日:昭和63年8月10日 所在地:中津川市付知町 所有者、保持者等:個人 |
寛文年間から文政年間の付知村の年貢についての書付(文書)です。 |
|
(たにばたのじょうもんどき)
|
員数:2 時代:縄文中期 指定年月日:昭和49年3月26日 所在地:中津川市付知町 所有者、保持者等:個人 |
大型半円錐形深鉢土器 高さ36cm、口径27.5~26.5cmでやや円型を欠く。 釣手式土器 高さ22cm×直径22cm×奥行16.5cm、口径10.5cm 籐づる等で吊して照明具を入れ使用したもの。 |
|
(かんえいだいききんのきんせきひぶん)
|
員数:1 石英安山岩 36cm×25cm×7cm 時代:江戸嘉永2年(1849) 指定年月日:昭和53年10月13日 所在地:中津川市付知町 所有者、保持者等:個人 |
寛永18年(1641)から翌年にかけ「寛永の大飢饉」と呼ばれる飢饉が発生しました。時の庄屋、田口慶傅は悲惨な事実を後世に伝える文書を牛頭天王社(倉屋神社)に奉納しました。後に、嘉永2年(1849)に慶傅の子孫である庄屋田口慶郷がこれを金石碑にして保存しました。金石碑からは付知村の人口およそ700人の内90人もの人が餓死したことが書かれ、当時の惨状を伝えています。 |
|
(えなぐんつけちむらさいけんえずめん)
|
員数:1 横426cm、縦86cm 時代:嘉永3年 指定年月日:昭和49年12月3日 所在地:中津川市付知町4956-43 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
嘉永7年(1854)に作成された付知村全図です。筆者は三尾暁峰らしい。 |
|
(ねはんのず)
|
員数:1 三尾暁峰 紙本水墨 134×55 指定年月日:平成2年9月14日 所在地:中津川市付知町 所有者、保持者等:個人 |
画面全体を同じ太さの墨の線で、細部にわたるまで徹底的に精密描写された涅槃(ねはん)図です。作者暁峰の習熟した技術が伺われます。 |
|
(とくがわばくふにしのまるざいばしゅつのず)
|
員数:1 三尾暁峰 指定年月日:平成2年9月14日 所在地:中津川市付知町 所有者、保持者等:個人 |
山深い森林の中から桧を伐り出し、運材する様子をきめ細かく説明的に表した絵巻物です。徳川時代の運材の様子を知るうえで歴史資料としても極めて貴重なものです。 |
|
(にしまた・ますぶちにようすいのず)
|
員数:2 三尾暁峰 指定年月日:平成2年9月14日 所在地:中津川市付知町 所有者、保持者等:個人 |
墨の濃淡をうまく利用し、山水画の技法を取り入れ、けわしい谷間を縫って流れる用水の姿をきめ細かく表しています。色調も落ち着き優れた作品です。 |
|
太刀 銘 政秀 附 太刀拵 (たち めい まさひで つけたり たちごしらえ)
|
員数:3 指定年月日:令和5年8月16日 所在地:中津川市付知町 所有者、保持者等:護山神社 |
これらの太刀は、尾張領主徳川齋莊(なりたか)(斉荘)が幕命により護山神社を天保14年(1843)に創祀した際、祭具一式とともに奉納されました。3口の太刀には全てに「政秀」の銘が刻まれ、尾国住政秀として知られる刀工が尾張領内向けに製作した太刀の可能性があります。 |
|
(なんぐうじんじゃ ほんでん)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市田瀬1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:南宮神社 |
祭神は鉱山を司る神である金山昆古命(かなやまひこのみこと)です。田瀬神社とも南宮神社とも称するのは、古くは南宮神社と称していたものを、明治4年(1871)神社の位置を定めた折、村社田瀬神社としたためられたためです。 |
|
(なんぐうじんじゃ とりい)
|
員数:1 時代:元文元年(1736)または元文3年(1738) 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市田瀬1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:南宮神社 |
田瀬神社に遺る文書によると、泉州(現在の和歌山県)の石工である森兵衛が建立したとされています。 |
|
(なんぐうじんじゃ しゃひょう(にわかいかくひっせき))
|
員数:1 時代:明治 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市田瀬1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:南宮神社 |
丹羽海鶴が揮毫した社標です。海鶴は文久3年(1863)、田瀬村庄屋丹羽五兵衛の四男として出生、名を正長といいました。明治22年(1889)日下部鳴鶴の門下生となり、その後鳴鶴の推薦で学習院書道教師、日本書道作振興会審査委員等をつとめ、日本書道界の指導者として名声を博した人です。 |
|
(はくさんじんじゃ ほんでん)
|
員数:1 時代:江戸時代 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:岐阜県中津川市下野1154 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:白山神社 |
下野地区に白山神社が勧進されたのは明らかではありませんが、本郷を中心とした集落発生の時期と考えて室町時代と思われます。 神社に残された最も古い棟札は、明暦3(1657)年の社殿を改築したときのものです。 |
|
(こうしんどう)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:平成元年4月1日 所在地:中津川市大字下野 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
鎌倉時代源頼朝の勧奨により、文覚上人がひろく佛跡の再興を図るため、諸国行脚の際にこの地へ尊像を携えてきて安置されたのが始まりと言われています。本堂は安永7年(1778)に建てられたものです。 |
|
(さかきやまじんじゃ ほんでん)
|
員数:1 時代:明治初期 指定年月日:平成元年4月1日 所在地:中津川市福岡500 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:榊山神社 |
総社である祇園牛頭天王は、元正天皇の御宇養老2午戌年の創立であると言われる。福岡植苗木の住人荒田栄久の勧請と伝えられ、彼の庭に杉苗七本天降り、家人寄集まって評議する時、家の童子によるおつげにより、杉を植えて森とし、社殿を創立して飛天王と称し、この氏神を尊崇し荘内はこれを宗敬した。慶応4年政府の「神仏分離令」布告によって、「八重垣神社」とも称えたが、榊が群生しているところから、明治3年榊山神社と社名を改称されて現在に及び、さらに昭和39年神社本庁の金幣社指定を受けて今日に至る。 |
|
(さかきやまじんじゃ はいでん)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:平成元年4月1日 所在地:中津川市福岡500 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:榊山神社 |
(注)榊山神社・本殿を参照 |
|
(さかきやまじんじゃ いしとうろう)
|
員数:2 時代:元文3年(1738) 指定年月日:平成元年4月1日 所在地:中津川市福岡500 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:榊山神社 |
本殿右脇社前にあるこの石燈籠一対は、高さ210cm、笠巾55cm、左右の側面に 「元文三年戌年十月吉日」「西尾孫六郎勝房」とそれぞれ刻銘されています。 |
|
(さかきやまじんじゃ のぎまれすけひっせき)
|
員数:1 時代:明治43年頃 指定年月日:平成元年4月1日 所在地:中津川市福岡500 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:榊山神社 |
碑の表面に刻まれた「日清日露戦没記念碑」の文字は第三軍司令官であった乃木希典大将の揮毫によるもので、裏面には日清戦争13名、日露戦争125名の従軍者の氏名が記録されています。 |
|
|
員数:1 時代:明治24年(1891) 指定年月日:昭和58年2月26日 所在地:中津川市高山1026-1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
楽屋の落書から明治24年( 1891)5月6日の舞台開きを知ることができます。入母屋、妻入りの形式で間口17.1メートル、奥行き26.9メートルと立派なもので、農村の娯楽の殿堂 として賑わった当時を偲ぶことができます。戦時中一時軍需工場に利用されたりしましたが、その後何度も改修され、平成4年(1992)には屋根の 葺き替え工事と共に回り舞台も復元されました。 地区の歌舞伎保存会によって、毎年素人歌舞伎や子ども歌舞伎が上演され、賑わいを見せています。 |
|
(かんのんどうえてんじょう)
|
員数:1 時代:明治 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市田瀬 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:上田瀬町内会 |
観音堂が建築された折、田瀬村の長谷川好静によって描かれた絵天井です。脱色落剥が激しく、平成3年(1991)の改築の折、原茂、古田雅博両氏によって全面的に修復がなされました。 |
|
(もくぞうやくしるりこうにょらいざぞう)
|
員数:1 時代:安永2年(1773) 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市田瀬 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:宮脇町内会 |
木彫り彩色の立派な姿です。台座の連弁と本体が分離でき、胎内に位牌が収蔵されています。安永2年(1773)「木蓮社眼誉呑屋上大和尚 春日御作也」の造像銘があります。 |
|
(もくぞうじゅういちめんかんぜおんりゅうぞう)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市田瀬 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:上田瀬町内会 |
鎌倉長谷寺から来た行脚僧が、この地で倒れ、その僧が所持していた木造の十一面観世音菩薩を元禄7年(1694)8月11日田瀬村中で祀ったと伝えられています。中央には十一面観世音菩薩、脇侍は、右に不動明王、左に四天王を配し漆塗の厨子に安置されています。 |
|
(もくちょうやくしるりこうにょらいざぞう)
|
員数:1 像高60cm 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市福岡 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:長根奉賛会 |
寄木造り、彩色、金箔が施され、左手に薬壺を持ち右手は与願印を結び、顔容は円満温和の相を示しています。貞享5年(1688)志津野喜右衛門は、苗木遠山家士として活躍したのちの下野、志津家の祖先にあたる人物です。 |
|
(もくちょうこうぼうだいしざぞう)
|
員数:1 高さ30センチメートル 巾33センチメートル 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市高山 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:下組町内会 |
木造彩色丸彫でなで肩の優しい面相に造られ、温雅にして慈悲に富む彫造です。 左手に数珠、右手には五鈷杵をもつ典型的な大師像に彫造されていますが、付知川の水害のときに数珠、五鈷杵が失われました。 |
|
(にわかいかくひっせき)
|
員数:1 時代:大正 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市田瀬14 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:田瀬小学校 |
「文行忠信 大正乙卯 春日為 田瀬小学校 海鶴正長書」 丹羽海鶴は文久3年(1863)田瀬村庄屋の家に生まれ、幼名を金吾、後に正長と改名しています。 明治書道界の重鎮である日下部鳴鶴に書才を認められ、学習院や東京高等師範学校の書道教師を歴任し、書道教育界に大きく貢献しました。 |
|
(なえぎはんむらかたもんじょ) |
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市福岡1-22郷土資料館内 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:高山財産区 |
高山村庄屋八代後藤吉右衛門宅矩が庄屋役在任中に「見聞日記」4冊(表紙とも351枚)書き綴っています。 |
|
(はくさんじんじゃしゃでん)
|
員数:1 時代:天保12年(1841) 指定年月日:昭和60年5月17日 所在地:中津川市蛭川588-2 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:白山神社 |
明治維新の改号により、今村神社とされたものの、現在では独立した白山神社となり今日に至っています。 |
|
(たはらじんじゃのこまいぬ(とうき))
|
員数:2 時代:江戸 指定年月日:昭和60年5月17日 所在地:中津川市蛭川5068-1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:田原神社 |
狛犬の背中に「寛保3年(1743)9月5日」ときざまれています。御深井(おふけ)焼という陶器づくりです。 |
|
(ほうりんじしょだいしょううんごうきのじくほか2てん(しゃくじょう、ほらがい))
|
員数:3 時代:江戸 指定年月日:昭和49年2月6日 所在地:中津川市蛭川 マップ: 所有者、保持者等:個人 |
蛭川の金剛山宝林寺の佐藤宝林は、苗木の雲林寺三世一秀より松雲の号記を授かりました。 宝林寺は以前山伏寺であったといわれ、この法螺貝と錫杖は、当時のものとして宝林寺に伝わったものです。 |
|
(げんしじだいいせきしゅつど せっき・どきひょうほん)
|
員数:559 時代:縄文・弥生 指定年月日:昭和49年2月6日 所在地:中津川市蛭川2240-5 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
蛭川地域で出土した縄文時代・弥生時代の石器や土器です。 |
|
(かさぎじんじゃしゃでんせっけいずおよびうけおいけいやくしょうしょ)
|
員数:2 時代:江戸 指定年月日:昭和31年7月12日 所在地:中津川市蛭川 マップ: 所有者、保持者等:個人 |
寛永7年(1854)に笠置神社は山火事のため全焼しましたが、近隣の村々からの寄付をうけその年の内に再建しました。再建には中野方村重兵衛が棟梁をつとめ、笠置村の大工職であった安江良八郎が脇棟梁として工事にあたりました。本物件は、再建時にかわされた請負書と設計図です。 |
|
(しゅずごうけつき)
|
員数:10 時代:江戸 指定年月日:昭和42年3月12日 所在地:中津川市蛭川 マップ: 所有者、保持者等:個人 |
この書籍は筆者発行所及び出所も不明です。江戸時代全国の城の図面と城主名等を記しています。 |
|
(かしはらゆいしょときゅうどうめんきょまきもの)
|
員数:9 時代:江戸 指定年月日:昭和49年2月6日 所在地:中津川市蛭川 所有者、保持者等:個人 |
西尾家に伝わる系図と弓術の免許巻物です。 系図によると、西尾家の祖は苗木遠山家の遠祖加藤景廉の息女景勝院尼公とあり、鳥居峠の戦いで武勇を馳せた西尾征四郎や、大阪の陣で活躍した西尾勲八郎らの名が記されています。 |
|
(ほうりんじかこちょう)
|
員数:6 時代:室町 指定年月日:昭和49年2月6日 所在地:中津川市蛭川2240-5 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:神国教 |
宝林寺初代住職の松雲和尚の時代から書き続けられた過去帳です。 |
|
(やまぐちすわじんじゃほんでん)
|
員数:1 指定年月日:平成5年6月3日 所在地:中津川市山口732 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:諏訪神社 |
文化4年(1807年)、宮の越の宮大工中村傳左衛門によって建てられました。総ケヤキ作りの本殿には鷲、鶴、龍、鯉、仙人、高砂の姥などの精巧華麗な彫刻が施されています。 |
|
(こうさいじのじゅういちめんかんのんこうしんとう)
|
員数:1 高さ75cm、幅38cm 時代:貞享 指定年月日:平成5年6月3日 所在地:中津川市山口西寺大門 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:光西寺 |
舟形光背の十一面観音の立像浮き彫りです。光西寺の庚申塔は数少ない十一面観音像で、下部に両端に鶏を配しており、台座石には見ざる・言わざる・着かざるの三猿を彫ってあることから、庚申像として建立されとものであることが解ります。 |
|
(ろくじぞうせきどう)
|
員数:1 高さ8cm、笠の幅18cm 時代:宝暦3年(1753) 指定年月日:平成5年6月3日 所在地:中津川市山口 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
石幢は寺の堂内にかかげられた幢と呼ばれる6角または8角形に組み合わされた幡を原型としたものです。この石幢には宝暦3葵酉10月吉日建立の時期ならびに施主宮下仁左衛門の名前が刻んであります。 |
無形文化財
市指定(1件)
| 名称 | データ | 解説 |
|---|---|---|
|
(とうけんつばのせいさくぎほう)
|
員数:1 指定年月日:昭和56年7月16日 所在地:中津川市中津川 所有者、保持者等:成木 一彦 |
自身で焼いた炭で砂鉄を吹き、鉄を鍛錬して地金を作るタタラ製鉄によった鍔製作技法。昭和38年以来、独学による刀剣鍔研究の中で大成したが、令和3年3月、保持者死去により滅失。 |
有形民俗文化財
県指定(2件)
| 名称 | データ | 解説 |
|---|---|---|
|
(えなぶんらくにんぎょうがしら)
|
員数:23 時代:江戸 指定年月日:昭和33年12月14日 所在地:中津川市中津川3651-2 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:恵那文楽保存会 |
現在、保存会に残る頭は47体があり、うち優秀品23体が指定されています。その作者はすべて不明ですが、大体において製作年代が古く、製作技巧の発達する以前の作と思われます。これらは大阪系の素朴な味をもち、人形頭の古典的逸品として、その発展研究史の上でも貴重な資料です。 |
|
(かしもののうそんぶたい(めいじざ))
|
員数:1 時代:明治27年 指定年月日:昭和47年7月12日 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
加子母村の有志たちによって建てられた芝居小屋は、廻り舞台やスッポン、両花道を備えた劇場形式の農村舞台です。樹齢約400年長さ8間以上もある巨木を梁に、しっかりと組み上げられています。 |
市指定(15件)
| 名称 | データ | 解説 |
|---|---|---|
|
(ふたわたりせきぶつぐん)
|
員数:1 指定年月日:昭和55年12月8日 所在地:中津川市加子母二渡 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:二渡区 |
明和4年(1767)に信徒有志が祖先菩提のために建立した観音堂に本尊観世菩薩のほかに多くの仏像があります。境内には、十三仏、三十三観音、千手観音、地蔵尊などの石仏や二十三夜塔・金比羅大権現碑六字名号碑(南無阿弥陀仏)が二基・大乗妙典供養等などの石仏、石仏群があります。 |
|
(しもくのみちしるべ)
|
員数:1 高さ130センチメートル、幅50センチメートル、厚さ45センチメートル 時代: 指定年月日:昭和52年12月8日 所在地:中津川市加子母下桑原 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:下桑原区 |
明治座へ行く道すがらに立つ自然石を使った石の道しるべで、天明4年(1784)に建てられました。 かつての飛騨街道と白川街道の分岐点にあり、往時の名残を留めています。 |
|
(まんがのつじのみちしるべ)
|
員数:1 高さ15センチメートル、幅70センチメートル 自然石 時代:明治42年(1909) 指定年月日:昭和55年1月17日 所在地:中津川市加子母万賀区 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:万賀区 |
村の在郷軍人団によって南北街道(飛騨街道)から分かれて白川街道への分岐点、万賀の辻に建てられたものです。 |
|
|
員数:2 指定年月日:平成9年3月5日 所在地:中津川市加子母中切3420 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:水無神社総代 |
村の総社で水無神社祭神は、高照光姫と大年祭。元和7年に建立され、その52年後の延宝2年に始まったと推定される。上山車、下山車があって、木造二階建て高さ5.60m、幅2.81m、奥行き3.29mの大きさ。この山車は別々に鳥居から神前までの約70mを笛や大太鼓、小太鼓、鼓の祭囃子にのって、長さ約20m、太さ約12cmの縄で曳きあげる。 |
|
(かみやまのねぎとみこ)
|
員数:2 指定年月日:平成9年3月5日 所在地:中津川市加子母中切 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:水無神社総代 |
元和7年に始まったといわれる祭りは、2台の山車が曳きだされ、上山車と下山車に分かれ、氏子が受け持ち行われている。上山車の禰宜と巫女はともに身長130cmくらいの木製で素朴なものである。山車上部前面でからくりの禰宜と巫女を操って「湯取り神事」という厄払いの神事を神前に奉納する。 |
|
(しもやまのねぎとしし)
|
員数:2 指定年月日:平成9年3月5日 所在地:中津川市加子母中切 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:水無神社総代 |
下山車の禰宜は1体山車の前人形であり、ひものからくりで両腕が動く仕掛けになっている。踊ると災害を呼ぶと伝えられているため、繰り踊らせることは全くない。からくりの獅子は、2つあり、胴体は老朽化により損傷し手作りで鉄に改造されているが、獅子頭やその他の物は当初からのものと推定される。祭礼は9月23日の秋分の日に行われる。 |
|
(しもやまのねぎほかんばこ)
|
員数:1 長さ110センチメートル 幅60センチメートル 高さ65センチメートル 時代:江戸 指定年月日:平成9年3月5日 所在地:中津川市加子母中切 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
祭の山車で使うからくりの人形の箱です。箱に下山車が延宝2年(1674)に製作されたと書かれています。 箱の蓋の内側には宝暦2年(1752)、文化3年(1805)、安政ほか明治3年(1870)に大太鼓、小太鼓を張り替え、昭和8年(1933)には、箱を修理したなどが書かれています。 |
|
(こうじんさまとこまいぬ)
|
員数:2 指定年月日:平成9年3月5日 所在地:中津川市加子母上桑原区 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:上桑原区 |
高さ50cm、幅25cmの三面六びの石像で、ご神体には「天正四子ノ年三月」(1577年)「加子母村下半郷」と、また狛犬の台座には「安政2年井山太助」と刻んである。 |
|
(めいじざのひきまく)
|
員数:1 指定年月日:平成9年3月5日 所在地:中津川市加子母下桑原 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
明治座を建設した時に出資した家の名前が書かれています。屋号と、その家の娘の名前が書かれており、「娘引幕」とも呼ばれています。 色も艶やかで柄も全部違ったものを配置してある奇抜な発想です。100年過ぎた今でも出来たときの色鮮やかさを保っています。 |
|
(つじどうのいしじぞう )
|
員数:1 高さ99.5センチメートル、281.3kg 時代:天保10年(1839) 指定年月日:昭和49年12月3日 所在地:中津川市付知町御堂後 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:辻堂観音堂 |
領主であった尾張徳川家が建立した地蔵です。 |
|
(あみだどうのむねふだ、りんがいぼくせき)
|
員数:15 時代:寛文~嘉永 指定年月日:昭和51年1月20日 所在地:中津川市付知町3133 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:阿弥陀堂 |
棟札は、わずか2~3行の文字しか記されていないが、いろいろな情報がわかります。 |
|
(おんたけさんどういちりづかどうひょう)
|
員数:6 時代:明治13年 指定年月日:昭和51年1月20日 所在地:中津川市付知町辻堂より字峠まで 所有者、保持者等:中津川市、個人 |
明治時代初期にできた御嶽道には、付知(辻堂)から御嶽頂上まで十丁ごとに建てられた道標です。 |
|
(もくぞうびんづるそんじゃざぞう )
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和51年1月20日 所在地:中津川市付知町寺尾 所有者、保持者等:寺山薬師堂 |
享和元年(1801)、田口廣林が彫りあげました。廣林は田口(さかや)家の4代目で漢方医でした。他にも寺山薬師堂に安置される木造千躰仏を6年がかりで彫りあげるなど、信仰心のあつい人でした。「賓頭慮尊者」とは「十六羅漢」のひとり「ビンドゥーラ」のことです。 |
|
(いしづくりみたらし )
|
員数:1 時代:寛延3年 指定年月日:昭和51年1月20日 所在地:中津川市付知町倉屋1940 所有者、保持者等:倉屋神社 |
倉屋神社境内にある石造りの御手洗。今は使われず水ははられてないが、約400年にわたり、子供たちが小石で御手洗のふちを叩いて遊んだために、大小合わせて31余の穴があき、いかにも古いものに見える。 |
|
|
員数:1棟 時代:昭和24年 指定年月日:平成18年7月28日 所在地:中津川市蛭川2198番地1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
蛭川地区の娯楽の殿堂として、特に村芝居を楽しむために造られた、木造地上2階地階建ての大規模木造軸組で造られた劇場型公民館である。 建物正面は旧御園座の建物に似せたモルタル塗りで、シンメトリーを意識したモダンな外観となっている。 |
無形民俗文化財
県指定(5件)
| 名称 | データ | 解説 |
|---|---|---|
|
|
員数:1 時代:元禄年間~ 指定年月日:平成元年7月7日 所在地:中津川市中津川3651-2 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:恵那文楽保存会 |
この文楽は、元禄年間に淡路国のくぐつ師(人形遣い)が、美濃国に巡行し、人形浄瑠璃を演じ、川上(かおれ)地区の人々に伝授したのが始まりとされています。江戸時代末期に隆盛となり、明治から昭和初期にかけて一時衰退する時期があったものの、地元有志によって今日まで伝えられています。恵那神社祭礼奉納は、毎年9月29日、前宮境内 直会殿前にある文楽演舞場にて上演されます。 |
|
|
員数:1 指定年月日:昭和50年7月17日 所在地:中津川市付知町 マップ:googleマップ 所有者・保持者等:付知町木曳保存会 |
徳川家康が慶長15年(1610)に全国の諸大名に命じ名古屋城を築いたとき、加藤清正がこの築城に加わり難工事をなしとげました。この工事のとき石曳きに唄われた音頭が付知村に伝わり、伊勢神宮の御神木を送り出すときに唄われるようになり、今日に引き継がれてきました。 |
|
(おきなまい つけたりにんぎょうかしらとめん )
|
員数:1 指定年月日:昭和50年7月17日 所在地:中津川市付知町 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:付知町翁舞保存会 |
付知の翁舞(通称 三番叟〔さんばそう〕)の発祥は天和2年(1682)であり、三百有余年歴史を保ち全国的にみても大変古くから続けられてきた伝統芸能(神事)です。 |
|
(ひるかわのきねふりおどり)
|
員数:1 指定年月日:昭和31年7月12日 所在地:中津川市蛭川字中切 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:杵振花馬保存会 |
杵振り踊りは杵振り祭りとも云われ、獅子舞に付随した踊りとして伝わっています。安弘見(あびろみ)神社例大祭に奉納されます。行列の構成は、稚子、鬼、天狗、おかめ、ひょっとこ、杵振り、お囃子、蠅追い。 |
|
(さかしたのはなうま)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:平成20年9月24日 所在地:中津川市坂下820番地1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:坂下花馬保存会 |
毎年10月の第2日曜日に、諸願の成就を感謝して坂下神社で行われます。 祭りの起源は、一説には木曽義仲が平家追討の祈願を行ったことによるとも伝えられています。しかし、古文書研究から実際は18世紀中頃の発祥と想定されます。祭り当日と前日の2日間馬を花で飾り立て行列する形態は、他所で見られなくなった形態で民俗学的にも貴重です。 |
史跡
国指定(2件)
| 名称 | データ | 解説 |
|---|---|---|
|
|
員数:1 156,774平方メートル 時代:江戸 指定年月日:昭和56年4月22日 所在地:中津川市苗木2799-2-1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市他 |
木曽川北岸の小高い山に築城された戦国及び近世の城郭跡です。川面から天守までの比高差は約170mあります。土岐氏と並んで東美濃一帯を根拠として覇を称えた遠山氏の居城で、「赤壁城」や「霞ヶ城」ともよばれています。 |
|
(なかせんどう(おちあいのいしだたみ)) |
約840m 道幅平均約4m 時代:江戸 指定年月日:平成22年2月22日 所在地:中津川市落合1447 所有者、保持者等:中津川市 |
市内の旧中山道約20キロメートルのうち、信州・美濃の境から落合字新茶屋、山中地区の約840m間は中山道の面影がよく残っている。特に、3ヶ所(計70.8m)の石畳が当時のまま現存しており、その周辺についても昭和63~平成7年度「歴史の道整備事業」にて石畳の修復がなされ、中山道の風情を偲ぶことができる。 |
|
(なかせんどう(おちあいじゅくほんじん))
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:平成22年2月22日 所在地:中津川市落合840-1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
落合宿本陣は、江戸期から代々井口家が本陣、庄屋、問屋を務めた。 文化元年(1804)と文化12年(1815)の二度にわたってこの地域を大火が見舞い、本陣も罹災・焼失したが、伝承によるとその3年後の文化15年(1818)に復興され、その際に当家を常宿としていた加賀前田家から門が寄進されたと井口家では伝えている。 その後、文久元年(1861)には皇女和宮親子内親王が徳川家へ降嫁される際に御小休され、明治13年(1880)には明治天皇が巡幸の際に御小休された。なお、御小休がされた部屋である「上段の間」も、往時を偲ぶ形で保存されている。 翌明治14年(1881)の改築の際に、現在のような土蔵造(一部2階建)、桟瓦葺屋根となった。 |
県指定(3件)
| 名称 | データ | 解説 |
|---|---|---|
|
(なかあらいきただいいちごうかまあと)
|
員数:1 1,229平方メートル(指定面積) 時代:室町初期 指定年月日:昭和33年7月16日 所在地:中津川市千旦林1414-5 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
この窯跡は、地山をくりぬいて営造された瀬戸系の大窯の形式に属するもので、室町時代初期の築造と推定される古窯跡がほぼ原形のまま発掘されました。しかし、冬の凍害等により、現形を保存することが難しくなり、埋め戻しを行ったため、今日では地下に眠る史跡となっています。 |
|
|
員数:1 25.9平方メートル 時代:縄文 指定年月日:昭和31年3月28日 所在地:中津川市福岡字野尻1219-1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
付知川と松島川が合流した段丘上、標高約340メートルに位置しています。昭和31年の調査で一辺約4メートルの方形の住居跡とそれに伴う石囲炉が発見されました。 この遺跡からは西日本、東日本のそれぞれの様式の土器が出土していることから、東西交流が盛んであったと考えられています。 |
|
(しまざきとうそんたく(まごめじゅくほんじん)あと)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:平成17年9月6日 所在地:中津川市馬籠4256番地の1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:財団法人 藤村記念郷 |
この史跡は、中山道馬籠宿の本陣であり、近代日本を代表する文豪の一人である島崎藤村(本名春樹)の生家でもあります。 本陣時代の建物は隠居所の他は明治28年の大火で焼失しましたが、残された屋敷の礎石や石垣等は、かつての建物群の所在をしめしています。 |
市指定(73件)
| 名称 | データ | 解説 |
|---|---|---|
|
(よこたもとつなのはか)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和31年4月17日 所在地:中津川市中津川2117-20 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:実戸町内会 |
横田元綱は、平多門国学に学び、元治元年(1864)年水戸浪士らの謹皇倒幕参加し、18歳の若さで自害しました。幕府のきびしい詮議の目をのがれ、実戸の地に埋葬され、大正5年墓碑が建立されました。現在の墓碑は昭和50年国道19号中津川バイパス建設のため、移転復元されたものです。 |
|
(なえぎとおやまけびょうしょ)
|
員数:1 間口29.3メートル 奥行20メートル 面積58平方メートル 時代:江戸~明治 指定年月日:昭和54年4月24日 所在地:中津川市苗木2875 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
苗木遠山家初代遠山友政から15代、またその家族など、大小合わせて28の墓碑が、中央広場を囲んで向かい合って立ち並び、その間に7基の石燈篭が点在しています。 |
|
(なえぎはんしやすだたざえもんじゅんしのあと)
|
員数:1 時代:享保7年(1772) 指定年月日:昭和54年4月24日 所在地:中津川市苗木2876-2 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
苗木領第5代遠山友由の側近として仕えた太左衛門は、29歳の若さで死去した友由の墓前の地である巨岩の盤上で殉死しました。殉死は幕命によって禁じられていましたが、太左衛門の忠誠心と責任感の強さによるものとして問題になりませんでした。 |
|
(なえぎはんしなんやくながおかよいちざえもんかげあきのはか)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和54年4月24日 所在地:中津川市苗木2390-1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
長岡與一左衛門景明は、長州長府の人で、苗木遠山家に招かれて以来、友明、友清の二君の武術を講じ、家臣を指南しました。馬術及び槍術に優れ、剣道の長岡流は苗木領御家流として廃藩に至るまで続きました。 |
|
|
員数:1 時代:明治 指定年月日:昭和54年4月24日 所在地:中津川市苗木609 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:八幡神社 |
自然石を蓋にした堂で、内部は洞穴の形態をしています。広さ約10平方メートルの堂内には、廃仏毀釈の後当時の仏教信者たちによって、一時地中に埋められた石仏等が集められていたと伝えられています。 |
|
(りゅうけいじあと)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和54年4月24日 所在地:中津川市苗木1192 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
現在は、五輪と、巨岩に刻まれた「南無阿弥陀仏」の名号が残っています。明治維新の廃仏毀釈によって廃寺となりました。 |
|
(なえぎはんこうにっしんかんあと)
|
員数:1 時代:明治 指定年月日:昭和54年4月24日 所在地:城山病院 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:城山病院 |
幕末、苗木藩に藩校設置が計画され、明治2年日新館が建設されました。我国唯一の平田国学を主体とした藩校でありました。 |
|
(なえぎはんまとばあと)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和54年4月24日 所在地:中津川市苗木4588-20 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
この一帯は古くから苗木領の総合軍事調練場として使用されてきました。現在は耕地となっている南北250メートル、東西100メートルのところに、当時は3基の的場があり、その内中央の土塁が残っています。 |
|
坂下の磨崖仏(さかしたのまがいぶつ)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:令和5年8月16日 所在地:中津川市坂下 所有者、保持者等:個人 |
この磨崖仏は西方寺集落の入口付近にあり、高さ約3.0m、幅約5.0mの自然石の花崗岩に、大きく船形光背を彫り込み、その内側に半肉彫りで彫られた阿弥陀如来坐像で、座高は約150センチメートルに及びます。
また、像右には「施主庄六良謹造立」とあり、当時西方寺一帯の有力者であった可知氏の可知庄六良の造立とされます。 |
|
(あぎじょうあと)
|
員数:1 時代:安土・桃山 指定年月日:平成14年4月24日 所在地:中津川市阿木1406 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
阿木城は通称城ヶ峰と呼ばれる標高541メートル、比高差約60メートルの山上一帯に築かれています。城の広さは東西約180メートル、南北約150メートルで、近隣の中世城郭の中では大規模な城です。遺構の保存状態も良く、当時の城の形態がよく分かります。 城がいつ頃に築かれていたのかは定かではありませんが、文献や遺構などから戦国時代末期には築城されていたと考えられています。 戦国時代の東濃地方は、織田氏・武田氏の激しい勢力争いが繰り広げられており、その中で阿木城も何らかの役割を果たしていたと思われます。 |
|
(ぶたいとうげれきしのみち)
|
員数:36 時代: 指定年月日:昭和52年12月8日 所在地:中津川市加子母小郷 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:小郷区 |
加子母村を縦断して北へ向かうと、下呂市との境に舞台峠がある。鎌倉幕府時代執権職であった北条時頼は出家し全国を旅して民情を視察した。途中威徳寺に詣で峠に舞台を作り能狂言を催して人々に鑑賞させたことから舞台峠と呼ぶようになった。峠下の石仏群は、峠を往来する人の安全を祈り立てたといい、頂上には石地蔵が建てられ干ばつのときは白山に向かって雨乞いをしたといわれている。 |
|
(さいのかみとうげれきしのみち)
|
員数:1 指定年月日:昭和55年1月17日 所在地:中津川市加子母万賀 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:万賀区 |
加子母村の東南端、付知町との境の峠である。その境に賽の神が祀ってあるので名付けたものです。賽の神とは道祖神のことで、疫霊を防ぐ神として祀られていたが、この峠は谷や沢を曲がりくねった難路のため、通行人の安全を祈り建てられたものである。 |
|
(ふたわたりばんしょあと)
|
よみ: 員数:1 指定年月日:昭和58年4月22日 所在地:中津川市加子母二渡 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:二渡区 |
江戸時代加子母二渡区の加子母川西側、お宮峠の登り口に通行人を監視する番所がありました。これは、峠が白川町佐見を経て飛騨街道の金山宿に通じる交通の要所にあったためです。 |
|
(おごばんしょあと)
|
員数:1 指定年月日:昭和58年4月22日 所在地:中津川市加子母小郷 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:小郷区 |
加子母小郷地区に役屋という家があり、亨保11年(1726)に荷抜番所として設けられました。 飛騨との交流物資の通関として運上金を徴収したり、禁制物資の取締りを代官所から委託されており、巡回役員の宿も兼ねていました。 |
|
(たもんぼうあと)
|
員数:1 指定年月日:昭和58年4月22日 所在地:中津川市加子母小郷 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:小郷区 |
多聞坊は、加子母小郷地区の国道257号線の舞台峠を下りたところにあります。記録によると威徳寺(いとくじ)の東坊にあたり、文覚上人もここで入寂されたと伝わっています。 |
|
(よはねす・で・れーけのさぼうあと)
|
員数:1 時代:明治 指定年月日:平成9年3月5日 所在地:中津川市加子母下桑原 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:下桑原 |
明治時代にオランダの水利技術者ヨハネス・デ・レーケの技術指導で完成した巨石堰堤です。 明治政府は外国の治水技術をとりいれるため、外国人技術者を雇いました。デ・レーケはその内の1人で明治6年(1873)に来日し、同36年(1903)に帰国するまでの間、主に木曽川水系の改修計画を担当しました。 デ・レーケは明治13年(1880)8月7日に加子母に入り、嫌谷(やんたに)・須母田谷・木曽谷・穴洞で工法について指導しました。現在残っているのは嫌谷のものだけです。 |
|
(にしまたようすいろずいどう)
|
員数:1 時代:嘉永3年(1850) 指定年月日:昭和49年12月3日 所在地:中津川市付知町字宮島 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
西股用水は、猪の谷を水源として天保元年(1830)から翌年にかけてつくられた「猪の谷用水」が、水源の水不足や漏水などで効率が悪いためこれに代わるものとしてつくられました。 |
|
(もみのきばしとひ)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和49年12月3日 所在地:中津川市付知 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
江戸時代、通行に難儀をする人々の窮地を見かねた輪外胡佳和尚(宗敦寺4世住職)が橋を作ろうと賛同する村人とともに尾張藩の材木の払下げを陳情するなど、資金集めに様々な苦労と努力の末、天明6年に橋が完成した。碑は、寛永3年大橋が出来る前の一本橋のころに増水した川へ落ち、溺死した人々の悲劇を悼んでいる。 |
|
(はいぶつきしゃくのざんせき・くようとうぐん )
|
員数:1 時代:寛政 指定年月日:昭和56年4月18日 所在地:中津川市付知町寺山墓地 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:寺山墓地 |
廃仏毀釈の騒動により、旧苗木藩では全国でも一番過激な廃仏毀釈がすすめられ、付知村は尾張藩領で、苗木藩領のような行動はなかったものの、平田学派に心酔した一部の村内有力者の神道に改宗したあげく仏像仏塔を傷つけたり墓石を土中に埋めたりした。 |
|
(ひだかいどうのどうひょう(ひだみち))
|
員数:1 指定年月日:昭和59年3月26日 所在地:中津川市付知町2区 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
高さ80センチメートルの自然石に指の絵と「ひだみち」、裏側に「田口養圭建」と書いてある。 |
|
(ひだかいどうのどうひょう(しろかわ・くろせみち))
|
員数:1 64cm 指定年月日:昭和59年3月26日 所在地:中津川市付知町7区 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
市道1号線と県道付知-越原線の分岐点にある自然石を利用した道標です。 |
|
(ひだかいどうのぶつぞう・ばとうかんのん )
|
員数:3 時代:安政・慶応 指定年月日:昭和59年3月26日 所在地:中津川市付知町8区 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
頭上に馬の頭の宝冠をのせた観音様で忿怒(ふんぬ)相をあらわします。一面二臂の像が多く見られますが、なかには三面二臂、三面八臂像も見られます。馬頭の宝冠をつけているこから、馬の保護神として江戸時代に広く信仰されました。 |
|
(ひだかいどうのぶつぞう・そうたいどうそじん)
|
員数:1 時代:江戸・文化8年(1811) 指定年月日:昭和59年3月26日 所在地:中津川市付知町2区 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
付知-加子母の村境にまつられた道祖神です。男女二躰の神がきちんと正座し正面を向いている珍しい形態です。 |
|
(おやまたいらほうきょういんとう)
|
員数:1 時代:慶長年間 指定年月日:平成14年2月19日 所在地:中津川市付知町3区大山 所有者、保持者等:個人 |
宗敦寺裏の急な大山谷を登ると峠へ出る。この辺りは平地が数ヘクタールも続く。西へ下ると加子母角領である。西側のピークに大山神社の奥社があり延宝2年の棟札がある。奥社の東下に由緒不明の宝篋印塔が一基。この東100mの三角の石塔はここで療養中に亡くなった加子母法禅寺の僧の墓と判明した。 |
|
(てらはたほうきょういんとう)
|
員数:1 時代:慶長年間 指定年月日:平成14年2月19日 所在地:中津川市付知町寺畑 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
元は「宝篋印塔陀羅尼」というお経を納めるための木製の塔だったが、鎌倉時代から石造りになり、江戸時代には墓標として用いられるようになった。塔身の四面に四方仏を梵字で刻んである。 |
|
(わかみやずいどう )
|
員数:1 時代:文化6年 指定年月日:平成14年2月19日 所在地:中津川市付知町8区袖屋~若宮神社裏 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:付知町用水組合 |
写真は若宮隧道の出口。右手前は開通時に祀った水神様。このトンネルを利用して、恵北浄化センターへ上水を送っている。200年前から流れ出ている水と現代の付知川の水がトンネル内で交差している。 |
|
(おうたきしんどうつけたりおうたきしんどうきねんひ)
|
員数:2(道1ヶ所、記念碑1基) 時代:明治 指定年月日:平成28年3月24日 所在地:中津川市付知町字樋口(道) 中津川市付知町字平作垣戸(記念碑) マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
王滝新道は、明治9年(1876年)に開通した道で、同時期に開通した丈右衛門新道(黒瀬湊~旧付知村)とともに、名古屋方面から王滝方面への最短経路として利用された。開通から中央鉄道(現在のJR中央本線)全通に至るまでの期間、林業経営や物流、交通の基幹路として活用されたほか、御嶽山に至るための信仰の道としても利用された。王滝新道記念碑の正式名称は「自付知至王滝新道剏(創)見記念之碑」と言い、王滝新道を拓いた三尾甚平を顕彰するために、明治40年(1907年)、王滝新道沿いに建立されたもの。濃飛流紋岩製で、寸法は、高さ177cm、幅109cm、奥行き37cm。記念碑には王滝新道の由来とその開通に伴う付知地域の発展について記されている。 |
|
(なむあみだぶつのひ(やだいら))
|
員数:1 時代:文政2年 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市田瀬矢平 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:矢平地区 |
旧福岡町の最北端の地区矢平の入口の三叉路に立つ名号等。傷跡は廃仏の際のもので、南無阿弥陀仏の揮毫は、名だたる僧の手によるものであることのみ現在に語りつがれています。 |
|
(なむあみだぶつのひ(しもたせ) )
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市田瀬下田瀬 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:下田瀬地区 |
この名号等は自然石を用い、上部に一円相を刻み「南無阿弥陀仏」、左右に「宝暦一年辛羊十二月吉日、寒念佛同行中」と刻銘があります。 |
|
(みぞじりかんのんせきぶつ)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市田瀬 マップ:googleマップ 所有者、保持者等: 芝ヶ瀬地区 |
昔から交通難所といわれ、何人もの人が転落しましたが、無傷であったことから、交通安全の守り神として広く親しまれている。形像は三面六びの浮彫立像、中央の手は合掌して頭上に馬面を置く典型的な馬頭観音で「宝暦十庚辰年十月」と刻銘があります。 |
|
(じゅうろくらかんせきぶつ)
|
員数:16 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市田瀬 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:上田瀬地区 |
この地は、江戸時代前期の曹源寺という寺院跡と伝えられています。廃仏毀釈による首のない六地蔵が安置されており、付知川の丸石が代用されています。 |
|
(あきばとうろう )
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市田瀬 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:上田瀬地区 |
文化年間、井織屋の先祖が造り酒屋をしていたときに火災が発生し、酒に火がつき大火になりました。そのため火難除けを祈願し家の近くに常夜灯を建立させたと伝えられています。灯篭には「秋葉大権現常夜灯文化二木の乙丑九月吉日 永代」と刻銘され、花岡岩を用いた、立の高い形の神前型灯篭です。 |
|
(さんじゅさんかんのんせきぶつ)
|
員数:33 時代:寛政17年(1799) 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市田瀬 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:向田瀬地区 |
向田瀬から大槙に行く道の脇に、三十三観音が安置されています。明治初年の廃仏毀釈の際には、破壊することなくそのまま池や畑の脇石として隠し置いていたものを、その後になって掘り起こし、ここに祀ったものです。 |
|
(どうひょう(たせざか))
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市田瀬田瀬坂 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:田瀬坂地区 |
旧飛騨街道の田瀬坂地内に、左は上野、坂下を経て木曽路へ、右は小野沢から下野、福岡を経て苗木に通ずる旧道の分岐点にある小さな自然石の道標。「右なへきみち 左きそみち」裏面には「此村たせ」と教えています。 |
|
|
員数:1 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市下野 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:本郷町内会 |
平安前期の代表的な歌人で絶世の美人とうたわれた小野小町が、吾妻路に向かう途中、この清水井戸で白粉をとかし旅の化粧崩れを直し、旅立って行ったという伝説がその名の由来です。 |
|
(しんべいしんろうやしきあと)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市下野 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:本郷地区 |
下野村庄屋田口新兵衛は、隣村との山論の調停に条理を尽くし努力したが一向に好転せず、苗木藩に提訴したが下野村方敗訴という重罪の断が下された。新兵衛とその子新四郎は憤恨やるかたなく、元禄二年七月庄屋屋敷を炎上させ、万策尽き 自害する。無念のあまり庭の椿に向かい、「椿よ性あれば永遠に実を結ぶことなかれ」と辞世の句を残した。 |
|
(しんべいしんろうのはか)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市下野 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:本郷地区 |
無念にも父子は差し違え自害しましたが、村方百姓らは新兵衛父子の義烈に追慕の情をよせ、数多の椿を屋敷跡に植え菩提を弔ったと伝えられています。現在も7月6日を忌日として供養霊祭が行われています。 |
|
(なむあみだぶつのひ(たしろ) )
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市下野田代 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:田代地区 |
下野田代より上野へ抜けるかつての木曽古道の荒廃した道筋の傍らに南無阿弥陀仏名号塔と月待塔の2基が立っています。名号塔は方形の基礎に花崗岩の分厚い塔身が置かれ、輪郭を近世好みの木瓜形に造りだし「南無阿弥陀仏」と箱彫しております。 |
|
(じょうえもんしんどういせき )
|
員数:1 時代:明治 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市福岡 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
明治10年、まだ国道や鉄道が出来る前に、付知から名古屋方面に向けての便利な近道を、付知村の大地主牧野丈右衛門によって造られました。丈右衛門新道として語り伝えられ8区黒川谷付近から稲荷平、福岡の新田、蛭川、中野方を経て八百津に至る40キロメートル近い道程で、中央線が開通するまでは地域の発展に大きく貢献しました。 |
|
(どうひょう(はちぶせ))
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市福岡 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:八布施地区 |
旧付知道と柏原道の分岐点にあります。 |
|
(なむあみだぶつのひ(たかのす) )
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市福岡高之巣 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:高之巣地区 |
地域の人たちに「庚申さま」と呼ばれ親しまれているこの堂宇の中の本尊は青面金剛で、かつては苗木藩八十八か所一二番札所の奥の院でありました。この堂宇の傍らに立つ南無阿弥陀仏の名号塔は身部の輪郭を木瓜形に彫造し、頭部に一円相を線刻しました。裏面には「安永二癸巳十月日 元八伏高巣 細萱迠」 |
|
(にじゅうさんやのひ(たかのす))
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市福岡 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:高之巣地区 |
巣山から高之巣へ抜ける旧道の山の入口左側にあります。 |
|
(こおりもちのいけ)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市福岡字二ツ森 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:福岡財産区 |
享保8年(1723)、苗木藩六代領主遠山友将は、「氷餅」の製造場所を苗木高峰山から福岡二ツ森山頂に移転を命じました。山道作り、小屋かけ、井戸掘りと近郷の百姓204人が二日間で完成したと伝えられています。 氷餅とは、寒冷期に池水を利用して餅を凍らせ、乾燥して粉状にしたもので兵糧備蓄等に使われた保存食です。 |
|
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市福岡 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:植苗木地区 |
むかしは道中での不慮の災難が多かったため、その安全を祈る「祭祀遺跡」と思われます。小石を塚に捧げて旅路の恙がなきことを祈ったところから「小石塚」と呼ばれるようになったのでしょう。 |
|
(こえじじょうあととしゅうへんいったい)
|
員数:1 時代:中世 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市福岡 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
南北朝の動乱期元弘建武(1331~1334)の頃に遠山一雲入道景利と、その男加藤左衛門景長が居城したと『高森根元記』に記されています。 北は飛騨口、南は岩村との連絡路、西は木曽西古道を押える要害の地にありました。 現在城の存在と思わせるものは、堀切と古井戸のみです。 |
|
(へんこうじあと)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市福岡 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
慶安3年(1650)ときの苗木藩主遠山友貞公の母堂、 寿昌院殿の供養のため建立されました。苗木藩領内には、藩公の菩提寺である苗木雲林寺の末寺が15を数え、片岡寺はその首位でした。開山は周岳玄豊和尚で、以後第十一世大領和尚まで仏門の繁栄を見ましたが、廃物毀釈で廃寺となりました。 |
|
(しょうにんつか)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市福岡 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:植苗木地区 |
盛り土で塚をつくり(高さ2メートル)頂上部に方形の基盤を置いて、卵形の塔身を据えた単制の無縫塔があります。裏面に刻銘が見られますが風化により判読できません。近くに片岡寺があったことから、僧侶の霊を供養した塚と推考されます。 |
|
(なむあみだぶつのひ(なつやけ))
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市福岡夏焼 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:夏焼地区 |
高山から杉渡瀬の西古道筋を北に向かうと、山の斜面が付知川の川岸に迫っているところの対岸が下村です。かつてここには阿弥陀堂が立っていたと推察され、境内に「南無阿弥陀仏」の大きな名号塔が立ち、裏面に安永三甲午三月吉日」と刻銘されています。 |
|
(あかばねどうひょう )
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市福岡字赤羽根 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中組地区 |
赤羽根から檜坂に上る三叉路を追分けとよんでいました。小さな石の道標が二基立っていて、 一基は正面に「道祖神」左右の側面に「左ひた道」「右きそ道」と刻み、他の一基にも「つけち道」「さヶ下道」と道の名前が刻まれており、これらの道は、各地に通じる重要な生活道路でした。地図が少ない昔の旅人にとって、大切な道案内でした。 |
|
(ずいりゅうじあと)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市高山 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
保存されていた棟札から天保6年に随龍寺という十一面観音堂のあったことを知ることができる。 |
|
(こうしぶんぎんのひ)
|
員数:2 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市高山 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
江戸時代高山村に「ぶん」・「ぎん」の姉妹がおり、貧しいの生活の中で、自らの幸せを求めず、父親に孝養をつくし、家業に精励したことが領主の賞するところとなり、二度に亘って米穀を下賜された。(江戸時代の君臣父子の儒学思想が民衆の中に位置付いていたことを表す貴重な資料です。)大正4年、高山地区青年団がその美徳を讃え、高山小学校西に記念碑を建立した。 |
|
(じゅうさんづか)
|
員数:1 時代: 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市高山 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中上地区 |
南北朝の動乱期、後醍醐天皇の皇子宗良(むねよし)親王の御子尹良(ただよし)親王は南朝方の将士とともに北朝方から逃れ木曽路へ落ちのびようとしていました。しかし、福岡高山の関屋で敵の追撃にあい、関屋の戦いとなりました。この合戦で、討死した将士らの塚が、周辺に十三建てられましたが、明治期の開墾で塚は現在の場所に合祀され供養碑が建立されました。 |
|
(がんしょうじあと)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市高山 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
17世紀後期から藩政終了時まで高山村一円を檀徒として開創された臨済宗妙心寺派天龍山雲林寺の8等地の末寺で、住持職は首座禅師(最下位の住持職)でした。岩松寺は雲林寺再興開祖一秀玄廣に業を受けた大休祖圓により開山されましたが、神仏判然令により明治3年9月に9世の士彦(還俗後加納彦左衛門房継)の時に廃寺となりました。常磐神社から300mほど北に「高嶽山岩松禅寺」の大きな石碑や岩松屋(岩松寺の方丈の四方一間を取り壊し民家と同じ大きさにし住居とした)の屋敷内にある歴代烈祖住持職の墓がその名残りをとどめています。 |
|
(きゅうたかやまがっこうあと)
|
員数:1 時代:明治初期 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市高山 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
明治16年5月竣工、6月落成式をあげ、常磐神社の調進所を仮校舎として開風義校を開き授業を始めましたが、日を追って「おひのくよう」の地を選び高山学校の校地としました。 |
|
(おひのくようひ)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市高山 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
地元の人が「おひのくよう」と呼ぶ三基の石塔は、岩松寺の和尚がこの場所で「日の供養」をしたことの由来すると伝えられています。内、一基は、文化年間高山村の寺子屋師匠で能書家でも知られる越石郷左衛門の供養塔と考えられます。 |
|
(きそにしこどういせき)
|
員数:1 時代:中世 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市高山 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
天正11年(1583)森長可と遠山友忠・友政の間で戦われた法泉寺坂の戦いでは、遠山方の遊撃隊が間道として利用し、森方を包囲し、これを打ち破りました。 江戸時代になって苗木城下町と尾州領細目村をつなぐ黒瀬街道のバイパスの役目を果たしました。 |
|
|
員数:1 時代:南北朝 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市高山 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
南朝親王伝説による尹良親王の首級を埋めたところと伝えられています。 |
|
|
員数:1 時代:室町 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市高山字西洞 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
全階式宝篋印塔と呼ばれる形式で、塔身約2メートルの立派なものです。後醍醐天皇の孫にあたる尹良(ただよし)親王の妃を祀る塚と伝えられていますが、形式から検討すると、年代に相違があり伝説を裏付けることは困難です。いずれにしても、高貴な人の墓塔と推察することができます。 |
|
(ちはらばしくようとう)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市高山字向知原 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:下組地区 |
苗木城下と蛭川・中野方・八百津を結ぶ街道が黒瀬街道です。当時付知川には橋がなく、街道を行き交う人々は大変困っていました。そこで、文化2年(1805)高山村の後藤東吾が中心となって付知川に橋を架けました。それが知原橋です。同年、村人はその喜びと共に水の犠牲者の供養と災厄排除の願いを込めて、岩松寺住職の揮毫による供養塔を造立して記念碑としました。 |
|
(ちはらこせんじょう)
|
員数:1 時代:中世 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市高山 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:付知川河川敷 |
「苗木伝記」等の史料によると、『天正十一年法泉寺坂の戦で破れた森長可は、苗木城攻略の挙に出、東山道から大井宿を経て中津川宿に宿営。叔父森可政らは、笠置山麓を通過し、蛭川より高山知原川(今の付知川)河畔に着陣。知原川を渡って苗木に突入。苗木城城主遠山友政自ら陣頭に立ち奮戦したが、落城し夜陰にまぎれ徳川家康に保護を求めた。以上の史料から野尻、関戸付近から郡上島あたりまで相当広い範囲にわたっていたと推測されます。 |
|
(いっぽんぎたいらいせき)
|
員数:1 時代:縄文 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市高山 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
石器出土地 |
|
(くろぜみちじぞう)
|
員数:1 高さ224センチメートル 時代:天明6年(1786) 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市高山 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:下組地区 |
黒瀬街道は八百津の黒瀬湊と苗木を結ぶ交通路で、苗木の並松で飛騨街道と接していました。この地蔵は、その分岐点、現県道中野方から苗木線沿いに立っています。天明の大飢饉の最中、地蔵尊の功徳を求めた村人たちの厚い信仰心が伝わってきます。 首のところで割られた跡があるのは、明治初期の廃仏毀釈の際のもので、一旦村人たちによって山中深くに隠されていましたが、後に現在の場所に設置されました。 |
|
(したじまいせき)
|
員数:1 時代:縄文 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市高山 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
県道苗木中野方線の付知川知原橋から100メートルほど下流左岸の傾斜地に位置し、古くからその存在が知られていました。昭和45年(1970)に発掘調査が行われ、縄文中期後半から晩期初頭の土器片および、石剣、御物石器、独銛石などが出土しました。 |
|
(ほうせんじこせんじょう)
|
員数:1 時代:中世 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市高山 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
本能寺の変の後、秀吉は苗木城主 遠山友忠・友政を森長可に属させようとしたが、従わなかったために戦となり、苗木藩は飛騨の金森氏の援軍を得て、一隊は法泉寺の弓手の洞に、別隊は遠の巣(今の木積沢)の山中に待伏させ、敗走すると見せかける策略で、敵軍を総崩れにさせました。 戦場となった山中に五輪塔が点在し、往古この付近に法泉寺があったと伝えられています。 |
|
(てっぽういけこせんじょう )
|
員数:1 時代:中世 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市高山 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:木積沢地区 |
天正年間に苗木の遠山氏と兼山の森氏との間に激しい合戦が行われた場所です。言い伝えによるとこの合戦で討ち死にした武士の死骸や鉄砲などの武器を投げ入れ埋めたとされ、その後、この池に赤と黒との奇妙な形をした魚が棲むようになり、この魚を見た人は目が悪くなってしまうということで、ここを通る村人達は、目をそらせて通ったと言われています。 |
|
(にじゅうさんやとう)
|
員数:1 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市高山木積沢 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:木積沢地区 |
月待の本尊は月天子であり、月天子をと祀って延命長寿、無事息災を祈願するのが本旨と伝えられます。木積沢墓地の入り口に自然石の前面を加工し「二十三夜塔」と彫刻した月待塔が六字名号塔二基と並んで立っています。 |
|
(わだまさとものひ)
|
員数:1 時代:昭和 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市高山 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:若山地区 |
昭和3年(1928)、建長寺の今井福山師が建長寺資料の中から南朝方の武将和田政朝がこの地で没していることを発見しました。同年発掘調査の結果、地下1メートル余の所から兜、鉄釜、人骨の入った大甕や、鉄製武器や装身具なども発見されたので、福山師らによって和田政朝の墳墓であると推定されました。 和田政朝は新田義貞と共に活躍した人で、護良親王の臣でしたが、戦を逃れこの地に隠棲し、貞和3年(1347)病没したと伝えらています。 |
|
(さんじゅうさんかんのん)
|
員数:29 時代:江戸 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市高山 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:高山財産区 |
三十三観音は、三十三体の異形の観音で、法華経の中にあらわれる三十三化身であると言われています。高山村庄屋後藤吉右衛門が宝暦2年(1752)高遠長蔵と和泉国の四郎兵衛という2人の石工を招き作らせたことが日記からわかります。 明治3年(1870)の苗木藩の廃仏令の強行で破損したものも見られますが、二十九体は完全な形で残っています。大正末期、真言宗の行者青山漂舟によって、姫塚の西側から現在地(大円坊) に移されました。 |
|
(さんじゅうさんかんのん)
|
員数:33 時代:江戸 指定年月日:平成元年4月1日 所在地:中津川市福岡 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:植苗木地区 |
この地は、江戸後期の天保から弘化のころ地蔵堂があり、当時の村人の信仰を集めた場所であったといわれています。33体すべてに割られた跡があり、苗木藩の廃仏毀釈の厳しさを物語っています。 33体の石仏の他に「宝暦甲戌十月」と刻まれた南無阿弥陀仏の六名号塔と弘法大師像が安置されています。 |
|
(ほうきょういんとう)
|
員数:1 時代:鎌倉、室町 指定年月日:昭和60年5月17日 所在地:中津川市蛭川4063-2 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:奈良井区 |
二子山神社のそばにある古いお墓です。鎌倉時代か室町時代に建立されたものと思われます。 |
|
(こんごうさんほうりんじじひょう)
|
員数:1 時代:不明 指定年月日:昭和55年8月27日 所在地:中津川市蛭川 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
廃仏毀釈のため壊され、川に放り出されていましたが、寺の跡にあらためて建てられたものです。 |
|
(しんのうづか)
|
員数:1 時代:南北朝 指定年月日:昭和50年8月9日 所在地:中津川市蛭川 所有者、保持者等:個人 |
南北朝時代の南朝方の後醍醐天皇につながる親王の墓所といわれ石櫃は近くのものを移したものです。 |
|
(やまのかみこふん)
|
員数:1 時代:7世紀初頭~中期 指定年月日:平成12年12月25日 所在地:中津川市山口 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
山の神古墳(2号墳)は、直径約15メートル高さ約3メートルの規模で、墳丘の一部に葺石が見られます。古墳の年代について、指定時に「7世紀初頭から中期」と報告されましたが、『山口村誌』では「5世紀終末までは遡らない様」としており、位置付けが定まっていません。昭和32年に行われた発掘調査で須恵器、土師器、刀子が出土しました。 かつてこの古墳の北側にもう1基古墳が存在していたと云われていますが、現在では消滅してしまっており、その姿は確認できません。 |
名勝
市指定(5件)
| 名称 | データ | 解説 |
|---|---|---|
|
(ふどうけいこく)
|
員数:1 指定年月日:昭和51年1月20日 所在地:中津川市付知町1区小谷より出ケ谷の間 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
仙樽の滝頭より不動滝下50メートルの区間 |
|
(ぼうずいわ)
|
員数:1 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市田瀬 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
矢平の林道を上って行くことしばし、滅多に人通りのない山の斜面の西方に向って立っている岩が、ちょうど法衣をまとった僧に似ているところから、坊主岩と呼ばれるようになりました。 |
|
(しんねざめ)
|
員数:1 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市田瀬樋之口 マップ:googleマップ |
田瀬樋之口地内付知川の両岸約150メートルにわたって見事な岩石の景観と渓谷美を見せています。1億年以前の火山活動で生成されたもので、濃飛流紋岩(石英斑岩)が主体となっています。 |
|
(ふどうたき)
|
員数:1 時代:不明 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:岐阜県中津川市福岡字田之尻 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:田之尻町内会 |
この不動滝は真東に向かって位置していることから、密教修験者の浄域として尊ばれた。年代が定かではないが、紀州の行者がこの滝を見つけ不動明王を祀ったといわれている。 滝に向かって左側の岩場には不動明王を表す梵字碑が造立され、その下に火炎を背に憤怒の形相をした不動明王の造像が滝しぶきに濡れ、かつての密教行者の修験場であった痕跡を今にとどめている。 |
|
(ゆのしまらじうむこうせん)
|
員数:1 時代: 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市高山 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
鉱泉の発見の時期は定かではありませんが、江戸時代の「高山村湯之島入湯願書」などの記録があり、古くから利用されています。大正5年には俳壇の巨匠高浜虚子とその門人が来遊し、吟詠しています。 |
天然記念物
国指定(4件)
| 名称 | データ | 解説 |
|---|---|---|
|
(さかもとのはなのきじせいち)
|
員数:2,720.67平方メートル 指定年月日:大正9年7月17日 所在地:岐阜県中津川市千旦林 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
ハナノキはカエデ科の植物で、4月に濃い紅色の花が集まって咲き、秋の紅葉も美しい。この自生地には30余株あり、幹の大小、高低は様々で、一番太いものは根元周囲2.8メートル、目通周囲2.3メートル、樹高16メートルです。ここは大正元年に日本で初めてハナノキの自生地として植物学雑誌に報告され、昔から地元の人たちによって大切に守られています。 |
|
(かしものすぎ )
|
員数:1 目通り13メートル、樹高30.8メートル 指定年月日:大正13年12月9日 所在地:中津川市加子母字池ノ森687 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
地蔵堂の裏にあるこのスギは、推定樹齢千数百年といわれ、目通り周囲13メートル、樹高30.8メートルの巨樹です。 言い伝えによると、建久年間(1190年から1198年)に源頼朝が江馬与四郎を訪ねた折に、枝を逆さにさしたのが根付いて、大杉になったといわれています。 |
|
(たるぼらのしだれもみ)
|
員数:1 指定年月日:昭和12年12月21日 所在地:岐阜県中津川市付知町 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
枝が下に垂れ下がっていることからシダレモミという名がつけられており、モミの木でこのように枝が下に垂れ下がっているのは日本でもこの木1本しかなく珍しいということで、国の天然記念物に指定されている。 |
|
(ひとつばたごじせいち)
|
員数:1 317.4平方メートル 目通周囲 1.4メートル、樹高 13メートル 指定年月日:大正12年3月7日 所在地:中津川市蛭川4129-53 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
ヒトツバタゴはモクセイ科の植物で、国内での分布は木曽川中流域と対馬のみ。5月ごろ四裂して細く白い花が咲き、満開の時は雪のようである。非常に珍しく見慣れない木であるため、「ナンジャモンジャの木」とも言われている。 和田川の左岸に自生しており、東側が桧林で囲まれていた影響で、川に面した側の樹勢がよい。樹齢は100年以上と推定される。 |
県指定(14件)
| 名称 | データ | 解説 |
|---|---|---|
|
(えなじんじゃのめおとすぎ)
|
右側:目通周囲 5.48メートル、樹高 46メートル 左側:目通周囲 6.29メートル、樹高 47メートル 指定年月日:昭和41年9月14日 所在地:中津川市中津川3786-1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:恵那神社 |
社の前にある2本の杉の老木で、樹齢は判明しないが、今も樹勢はさかんである。 |
|
(せとのかや)
|
員数:1 目通4.5メートル、樹高18.2メートル 時代: 指定年月日:昭和44年8月5日 所在地:中津川市瀬戸670-2 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
地上3.3メートルのところで幹が2本に分岐しています。昭和54年10月の台風によって双幹のうち1本の上部約6メートルが折損したが樹勢はさかんです。 |
|
(じせいのひとつばたご)
|
員数:1 目通周囲 1.25メートル、樹高 11.2メートル 指定年月日:昭和33年12月14日 所在地:中津川市苗木1880-1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
ヒトツバタゴはモクセイ科の植物で、国内での分布は木曽川中流域と対馬のみです。5月ごろ四裂して細く白い花が咲き、満開の時は雪のようです。非常に珍しく見慣れない木であるため、「ナンジャモンジャの木」とも言われています。 |
|
(おおみかやのき)
|
員数:2 南側:目通3.5メートル、樹高8.8メートル 北側:目通2.9メートル、樹高13.2メートル 指定年月日:昭和33年12月14日 所在地:中津川市瀬戸1009-1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
このカヤは、普通のものより種子が大きく、毎年2月苗木遠山家から徳川幕府へ献上物として用いられました。また遠山家で毎年正月に飾りとして使われ、大正8年まで続いていたといわれています。 |
|
(いわやどうのしでこぶしぐんせいち)
|
指定面積 2,181平方メートル 指定年月日:(県)平成20年1月15日(市)昭和58年 8月18日 所在地:岐阜県中津川市千旦林1596-4 ほか 所有者、保持者等:個人 |
この岩屋堂のシデコブシは、自生地としては北限に位置し、約500本余りのシデコブシが自生し、規模は最大である。春に見事な花を咲かせます。 |
|
(しんちゃやのじせいひとつばたご)
|
員数:1 目通1.3メートル、樹高10.5メートル 指定年月日:昭和44年8月5日 所在地:中津川市落合1459-1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
岩場の湿地で付近にはナラが多い。1メートルのところで幹が2本に分岐している。 |
|
(ちょうらくじのいちょう)
|
員数:1 目通周囲8.2メートル、樹高28メートル 時代:平安 指定年月日:昭和42年2月14日 所在地:中津川市阿木5864-3 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:長楽寺 |
地上2.5メートルの高さで幹が4本に分かれています。分かれた幹のうち太いものは目測4メートルくらいであり、樹勢旺盛で年々伸びつつあります。樹齢は800年以上といわれています。 |
|
(いそさきじんじゃのすぎ )
|
員数:1 目通6.8メートル、樹高30メートル 指定年月日:昭和40年9月7日 所在地:中津川市上野本郷433 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:上野区 |
磯前神社の社殿後方右側にあります。伊勢湾台風によりいくらか枝が損なわれています。 |
|
(さかしたのもみらん)
|
員数:1 指定年月日:昭和47年12月13日 所在地:中津川市坂下196 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
このモミランはカヤの木に着生しています。モミランは暖地性植物であり、主に紀伊・四国でみられるため、県下では極めて珍しいです。 葉は小形で楕円形をしており、3から4月ごろ黄緑色の花をつけます。 |
|
(さかしたのはなのきぐんせいち)
|
員数:1 約200本 指定年月日:昭和47年12月13日 所在地:中津川市上野560-1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
椛の湖の北側にある湿地帯に群生しています。目通周囲0.5から0.6メートルのものが多く、樹高は15メートル前後。このように規模の大きいハナノキ群生地は県下でも稀です。 |
|
|
員数:1 指定年月日:昭和37年2月12日 所在地:中津川市蛭川5735-1-1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
紅岩は南側にダイダイゴケ属の一種が寄生し橙色を呈し、遠望すると紅色に見えることから紅岩と名付けられました。 |
|
(はなのきじせいち)
|
員数:1 約40本、6,693平方メートル 指定年月日:昭和47年6月17日 所在地:中津川市蛭川 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
蛭川奥渡公民館から高徳寺に通ずる坂道のわきに小さな溜め池を囲む湿地帯があり、そこに群生しています。 |
|
(しだれがき)
|
員数:1 指定年月日:昭和47年6月17日 所在地:中津川市蛭川 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
この木は枝が垂れ下がる珍しい性質があります。果実は小さく渋みが強い珍種です。 |
|
(かみやまぐちのすわじんじゃしゃそう)
|
員数:1 3143.85平方メートル 指定年月日:平成18年9月5日 所在地:中津川市山口731番地1、732番地1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:宗教法人諏訪神社 |
この社叢にはスギ、ヒノキ、カシ、サカキなど60種類以上の植物が自生しており、極めて珍しい樹木であるシダレエノキも存在している。 暖帯性から温帯性に至る樹種構成を示し、岐阜県と長野県境という内陸寒冷地においてはきわめて貴重な植生である。 |
市指定(52件)
| 名称 | データ | 解説 |
|---|---|---|
|
(かいしょざわのしでこぶしぐんせいち)
|
員数:66株(181本) 1,622平方メートル 指定年月日:昭和58年8月18日 所在地:中津川市手賀野169番3他 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
シデコブシはモクレン科の植物で、一名をヒメコブシといい、4月上旬頃に径7~10センチメートルの白色または淡紅紫色の花をつけます。 |
|
(しんめいじんじゃのおおすぎ)
|
員数:1 目通6.5メートル、樹高9.2メートル 指定年月日:昭和46年10月28日 所在地:中津川市苗木1112-1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:神明神社 |
樹齢は判明しないが、寛文2年(1662)8月落雷のため樹幹頂点から裂傷したといわれ、当時既に相当の老木であったと推定されます。 |
|
(まるやまじんじゃのふないわ)
|
員数:1 長さ12メートル、高さ6メートル 指定年月日:昭和46年10月28日 所在地:中津川市苗木3342 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:丸山神社 |
丸山神社の南側に巨岩があり、その形状が鮒の形に似ているところからふな岩と呼ばれています。 |
|
(かりやどのひとつばたご)
|
員数:1 目通周囲 1.47メートル 樹高 17.3メートル 指定年月日:平成18年5月31日 所在地:中津川市苗木4547-6 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
ヒトツバタゴはモクセイ科の植物で、国内での分布は木曽川中流域と対馬のみです。5月ごろ四裂して細く白い花が咲き、満開の時は雪のようです。非常に珍しく見慣れない木であるため、「ナンジャモンジャの木」とも言われています。 南向きの傾斜地に自生し、周囲が雑木で囲まれていた影響で、地上から約6メートルのところから枝が分岐し、枝葉が少なくなっています。 |
|
(いぐみのしでこぶし)
|
員数:1 指定年月日:平成18年8月31日 所在地:中津川市苗木612-1-1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
溜池の岸に自生し、樹高約11メートル・目通周囲約1.5メートルを有し、樹齢は100年を越えると推定され、シデコブシの単独木として県下でも最大級のものです。 |
|
(はちまんじんじゃのひとつばたご)
|
員数:1 目通周囲 1メートル 、0.84メートル 樹高 22メートル 指定年月日:昭和46年10月28日 所在地:中津川市千旦林641 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:八幡神社 |
ヒトツバタゴはモクセイ科の植物で、国内での分布は木曽川中流域と対馬のみです。5月ごろ四裂して細く白い花が咲き、満開の時は雪のようです。非常に珍しく見慣れない木であるため、「ナンジャモンジャの木」とも言われています。 この木は根元で2幹に分かれています。 |
|
(あぎのしょうにゅうどう)
|
員数:1 洞穴奥行49メートル以上、穴内の高さ0.3~1.4メートル 指定年月日:昭和57年4月8日 所在地:中津川市阿木3191-3 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
この鍾乳洞は、高低の変化が大きく、石灰岩は、新生代新第三期の中新生にできた具殻石灰岩である。(注) 現在は危険につき立入禁止です |
|
(いいぬましんめいじんじゃのめおとすぎ)
|
員数:2
指定年月日:平成20年12月19日 所在地:中津川市飯沼1363番地 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:神明神社 |
飯沼神明神社内にある2本の大杉。雄株樹高40メートル、幹周7メートル。雌株樹高40メートル、幹周7.5メートル。 |
|
(むかいやまのモリアオガエルせいそくち )
|
2,099平方メートル 指定年月日:昭和51年8月26日 所在地:中津川市神坂2900-72 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
モリアオガエルは日本固有のカエルで、梅雨期になると、特定な場所の池や沼に集まって、夜間水辺の木や草に昇って300~500個の卵を産みます。ふ化した幼生が1センチメートル位に成長すると池や水たまりの中へ落ちるという特殊な産卵習性をもっています。 |
|
(まごめのひとつばたご)
|
員数:2
指定年月日:昭和63年10月18日 所在地:岐阜県中津川市馬籠 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
ヒトツバタゴはモクセイ科の植物で、国内での分布は木曽川中流域と対馬のみ。5月ごろ四裂して細く白い花が咲き、満開の時は雪のようである。非常に珍しく見慣れない木であるため、「ナンジャモンジャの木」とも言われている。 |
|
|
員数:1 目通2.3メートル、樹高25メートル 指定年月日:平成元年8月24日 所在地:中津川市馬籠4817-12 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
ハナノキはカエデ科の植物で、4月に濃い紅色の花が集まって咲き、秋の紅葉も美しい。 日本固有種で、県内では美濃地方東部の東濃地域に分布しています。 |
|
(いそさきじんじゃのいちょう)
|
樹高13メートル 目通周囲4.3メートル 指定年月日:昭和40年7月3日 所在地:中津川市上野本郷433 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:上野区 |
境内にある大イチョウ。坂下地区で最大のイチョウとして、昭和40年に指定される。 |
|
(めおとはなのき )
|
員数:2 目通2.06メートル、樹高23.5メートル/目通1.55メートル、樹高27.5メートル 指定年月日:昭和47年4月1日 所在地:中津川市坂下上外 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
上外地区の最奥部に近い場所に並立する二本のハナノキ。 |
|
(かみそでのひとつばたご)
|
員数:1 目通周囲 1.21メートル 樹高 13メートル 指定年月日:平成5年3月25日 所在地:中津川市坂下字上外 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
ヒトツバタゴはモクセイ科の植物で、国内での分布は木曽川中流域と対馬のみ。5月ごろ四裂して細く白い花が咲き、満開の時は雪のようである。非常に珍しく見慣れない木であるため、「ナンジャモンジャの木」とも言われている |
|
(なかそでのひとつばたご)
|
員数:2 目通周囲 0.68メートル 樹高 16.2メートル
樹高 17.2メートル 指定年月日:昭和47年4月1日 所在地:中津川市坂下字中外 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
ヒトツバタゴはモクセイ科の植物で、国内での分布は木曽川中流域と対馬のみ。5月ごろ四裂して細く白い花が咲き、満開の時は雪のようである。非常に珍しく見慣れない木であるため、「ナンジャモンジャの木」とも言われている。 |
|
(なかそでのひとつばたごじせいち)
|
員数:16 指定年月日:昭和47年4月1日 所在地:中津川市坂下字中外 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
ヒトツバタゴはモクセイ科の植物で、国内での分布は木曽川中流域と対馬のみです。5月ごろ四裂して細く白い花が咲き、満開の時は雪のようです。非常に珍しく見慣れない木であるため、「ナンジャモンジャの木」とも言われています。 |
|
(たじりばしのひとつばたご)
|
員数:1 目通周囲 0.8メートル 樹高 10.7メートル 指定年月日:昭和47年4月1日 所在地:中津川市坂下字上外 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
ヒトツバタゴはモクセイ科の植物で、国内での分布は木曽川中流域と対馬のみ。5月ごろ四裂して細く白い花が咲き、満開の時は雪のようである。非常に珍しく見慣れない木であるため、「ナンジャモンジャの木」とも言われている |
|
|
員数:1 樹高16メートル 目通周囲4.3メートル 指定年月日:平成5年3月25日 所在地:中津川市坂下東町 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
榧の木の古木。オオカヤ蘭が寄生していると言われています。県道の田立へ向かう道上にあり、東濃でも有数の大木である。榧の木は大木が多いが、成長が極めて遅い。 |
|
(やぶちのしでこぶし)
|
樹高15メートル 目通周囲1.2メートル 指定年月日:平成9年3月3日 所在地:中津川市坂下字矢渕 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
矢渕の渡の旧跡の北東側にあたる竹藪の中に自生する。市内の他の地区にも自生は認められるが、その中でも大形樹の一つと考えられる。 |
|
|
員数:1 目通3.1メートル 樹高15メートル 指定年月日:昭和43年5月25日 所在地:中津川市川上字三ツ山1053 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:国有林 |
ハナノキはカエデ科の植物で、4月に濃い紅色の花が集まって咲き、秋の紅葉も美しい。 日本固有種で、県内では美濃地方東部の東濃地域に分布しています。 |
|
(すいむじんじゃのいちい(めぎ))
|
樹高7メートル 目通1.85メートル 指定年月日:昭和51年7月20日 所在地:中津川市加子母小郷554-1(牧水無神社) マップ:googleマップ 所有者、保持者等:小郷区 |
イチイ(一位)の木は、古来より神官が持つ笏(しゃく)の材料として使われています。 一位の位にちなみこの名が付けられました。神にかかわる縁起木とされております。 |
|
(すいむじんじゃのいちい(おぎ) )
|
樹高12メートル 目通1.75メートル 指定年月日:昭和51年7月20日 所在地:中津川市加子母小郷554-1(牧水無神社) マップ:googleマップ 所有者、保持者等:小郷区 |
イチイ(一位)の木は、古来より神官が持つ笏(しゃく)の材料として使われています。一位の位にちなみこの名が付けられました。神にかかわる縁起木とされております。 |
|
(すいむじんじゃのすぎ)
|
樹高30メートル、目通4.7メートル 指定年月日:昭和51年7月20日 所在地:中津川市加子母小郷554-1(牧水無神社) マップ:googleマップ 所有者、保持者等: |
水無神社本殿の裏に自生し、神社創建時からの境内木です。 牧水無神社は元和7(1621)年に飛騨国一宮水無神社から分社したものです。 |
|
(わかみやはちまんじんじゃのすぎ)
|
樹高33メートル、目通4.5メートル 指定年月日:昭和51年7月20日 所在地:中津川市加子母番田 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:番田 |
加子母地域の番田にある八幡神社の境内に自生しています。 神社は大雀命(おうささぎのみこと)を祭神とし、棟札から享保12(1727)年の建立と考えられます。 |
|
(ふたわたりのまつ)
|
樹高15メートル 目通直径1メートル 指定年月日:昭和55年1月17日 所在地:中津川市加子母二渡 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
加子母地区二渡の字川西に自生する赤マツの大木です。永い年月の風雪のため枝や幹の枯渇が進んでおり、樹齢はおよそ300年といわれています。 |
|
(すいむじんじゃのおおすぎ)
|
員数:1 目通7.2メートル 樹高27.5メートル 指定年月日:昭和49年3月26日 所在地:中津川市付知町字富田3875 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:水無神社 |
推定樹齢約1000年、落雷のため上部が折れています。 |
|
(くらやじんじゃのむくろじ)
|
員数:1 目通3.7メートル 樹高14メートル 指定年月日:昭和51年1月20日 所在地:中津川市付知町1940倉屋神社境内 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:倉屋神社 |
田口庄屋家のお宮・倉屋神社に生えている。お宮創建のとき、境内に計画的に植えられたらしいので、17世紀初めか16世紀後半から生えていたと推測される古木である。 |
|
(いでのこじのきそおおひのきのひょうほん)
|
員数:1 直径2.38メートル、重さ500キログラム 指定年月日:昭和51年1月20日 所在地:中津川市付知町字護山1594 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:護山神社 |
昭和29年(1954)に出ノ小路山で伐採された樹齢950年の「日本一の大ヒノキ」と呼ばれる標本です。 |
|
(とちのきおよびきせいしだるい)
|
員数:1 目通4.6メートル、樹高20メートル 指定年月日:昭和56年4月18日 所在地:中津川市付知町字島畑 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
古くから根本に祠をまつってあがめてきた「神木」です。寄生シダが9種類やどっています。なかでもスギラン、イワオモダカは貴重なものです。 |
|
(つけちのひとつばたご)
|
員数1 目通周囲 1.65メートル、樹高 20.5メートル 指定年月日:平成7年7月17日 所在地:中津川市付知町字小林 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
ヒトツバタゴはモクセイ科の植物で、国内での分布は木曽川中流域と対馬のみです。5月ごろ四裂して細く白い花が咲き、満開の時は雪のようです。非常に珍しく見慣れない木であるため、「ナンジャモンジャの木」とも言われています。 |
|
(なんぐうじんじゃおおすぎ)
|
員数:2 北側:目通4.26メートル、樹高32メートル 南側:目通4.19メートル、樹高9.6メートル 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市田瀬1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:南宮神社 |
樹勢はきわめて旺盛で、本殿の前に揃って立つこの2本が、境内木の王者の風格をもっております。 |
|
|
員数:1 目通3.3メートル、樹高18メートル 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市田瀬 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:付知川河川敷 |
カエデ科の落葉高木で、中部日本に稀に樹生する希少な植物です。葉は浅く三裂、雌雄異株。春、葉に先立って濃紅色の美しい花をつけ、紅葉も美麗です。樹皮又は葉を、煎じて洗顔に用いることもあります。 |
|
|
員数:1 目通2.44メートル、樹高29メートル 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市福岡 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:福岡財産区 |
カエデ科の落葉高木。木曽川流域の山間の湿地に自生する落葉高木で、雌雄異株。別名「ハナカエデ」ともいい4月初旬のまだ葉の出ない前に開花します。葉は浅い三裂をなし翼果を結びます。 |
|
(みさしまのひとつばたご)
|
員数:1 目通周囲 2メートル、樹高 16メートル 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市下野字見佐島 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
ヒトツバタゴはモクセイ科の植物で、国内での分布は木曽川中流域と対馬のみ。5月ごろ四裂して細く白い花が咲き、満開の時は雪のようである。非常に珍しく見慣れない木であるため、「ナンジャモンジャの木」とも言われている。 |
|
(あじめどじょうせいそくち)
|
員数:1 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:付知川 樋之口橋~下野橋下流(柏原川合流付近) マップ:googleマップ 所有者、保持者等: |
アジメドジョウは、中部日本の一部の河川に生息するドジョウ科の魚です。 中でも、岐阜県の山間部・福井県九頭竜川・木曽川上流部では古くから「アジメ(味女)」の名で広く地元民に親しまれ、珍味とされてきました。 現在、生息数が減少したため、保護区域が設定されています。 地元中津川市下野の生物学者丹羽彌(ひさし)氏は、長年アジメドジョウの研究に尽力され、「アジメ博士」の名で広く知られています。 |
|
(ふくおかのひとつばたご)
|
員数:1 目通周囲 1.2メートル、樹高 13メートル 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市福岡 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
ヒトツバタゴはモクセイ科の植物で、国内での分布は木曽川中流域と対馬のみ。5月ごろ四裂して細く白い花が咲き、満開の時は雪のようである。非常に珍しく見慣れない木であるため、「ナンジャモンジャの木」とも言われている。 |
|
(ときわじんじゃしゃそう)
|
員数:1 指定年月日:昭和48年11月3日 所在地:中津川市高山1585 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:常磐神社 |
下森に金山比古神を祀った南宮大明神、御殿前の地に菊理比賣神を祀った白山大権現、熊野平の地に須佐之男之神を祀った熊野権現がありました。 この三社を養老元年に現在の常磐の地に合祀し、産土神として南宮神社として、奉齋しました。その後、元和8年に豊受比賣大神を、正保元年には菅原大神を奉齋して祀りました。明治2年に神殿(神明造)を改築し、高山地内に散在する小神社を合祀して社名を常磐神社と改称された。 |
|
(わかやまのしでこぶし)
|
員数:2 北:樹高11メートル、目通0.86メートル 南:樹高10メートル、0.91メートル 指定年月日:平成7年4月1日 所在地:中津川市高山字若山 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
「シデコブシ」はハナノキ、ヒトツバタゴなどと同様希少固有種で岐阜県東濃地方を中心に生育しています。土地開発が進行する中、これら原植物種の絶滅が危惧されており、希少固有種を保存しようとする声が高まっています。この「シデコブシ」は福岡町高山に自生し花弁数が18から24枚となっています。 |
|
(いちのせのひとつばたごじせいち)
|
員数:1 目通1.03メートル、樹高10メートル 指定年月日:昭和31年7月12日 所在地:中津川市蛭川 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
この木は、県道と木積沢線の分岐点にあり、昭和31年に指定。 |
|
(はなのきじせいち)
|
員数:1 目通0.85メートル、樹高10メートル 指定年月日:昭和31年7月12日 所在地:中津川市蛭川 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
この樹は樹齢150年以上と推定され、元は双幹であったが今は1本となっています。 |
|
(たはらじりのひとつばたご)
|
員数:1 目通0.85メートル、樹高10メートル 指定年月日:昭和48年1月18日 所在地:中津川市蛭川5283-2 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:岐阜県 |
田原尻のバス停前、小川に面した県道の路側にあります。根本から2本に別れています。 |
|
(しみずのおおまつ)
|
員数:1 指定年月日:昭和48年1月18日 所在地:中津川市蛭川679-1 所有者、保持者等:中津川市 |
今洞の笠置林道の入り口から10m右に5m付近にあり、種松として残ったまっすぐ伸びた木です。 |
|
(おくどのおおひのき)
|
員数:1 目通3.2メートル、樹高20メートル 指定年月日:昭和48年1月18日 所在地:中津川市蛭川5485 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:奥渡区 |
奥渡地区の中央の道端に立つ大きな1本のヒノキ。昭和48年指定。 |
|
(さんしろうのおおすぎ)
|
員数:1 目通3.8メートル、樹高36メートル 指定年月日:昭和48年1月18日 所在地:中津川市蛭川1357-1 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:中津川市 |
蛭川遠ヶ根の田口清次郎は字大博士の三四郎那木において旧蛭川村有林として初めて植林を行いました。植林された数百本のスギは、明治28年(1895)小学校を殿塚に改築する際、明治45年(1912)村営電気事業創設時に電柱として、また昭和7年(1932)の大洪水時に流失した橋梁の部材として使用されました。本指定物件は植樹された内、唯一残ったものです。 |
|
(いまぼらのおおいちょう)
|
員数:1 目通3.4メートル 樹高19メートル 指定年月日:昭和55年8月27日 所在地:中津川市蛭川832 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:岐阜県 |
蛭川にただ一つの大イチョウの木です。中切の町を西に進むと前方に見えてきます。雄の木。昭和55年指定。 |
|
(いまぼらのひとつばたごぐん)
|
員数:3 目通1.2メートル 樹高10メートル
目通0.86メートル 樹高14メートル 幹周囲1.27メートル、樹高9メートル 指定年月日:昭和60年5月17日 所在地:中津川市、個人 マップ:googleマップ |
今洞地区にある、3本からなる大きなヒトツバタゴの木。春になると見事な白い花を咲かせます。 |
|
(いまぼらのしだれざくら)
|
員数:1 目通1.16メートル 樹高17メートル 指定年月日:昭和61年5月20日 所在地:中津川市蛭川 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
今洞地区の親王塚地内にあります。 |
|
(かんばせのひとつばたご)
|
員数:1 目通周囲 1.07メートル、樹高 21.8メートル 指定年月日:平成18年5月31日 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
ヒトツバタゴはモクセイ科の植物で、国内での分布は木曽川中流域と対馬のみ。5月ごろ四裂して細く白い花が咲き、満開の時は雪のようである。非常に珍しく見慣れない木であるため、「ナンジャモンジャの木」とも言われている。 湿潤な沢地に自生し、地上から約2mのところから枝が長く分岐しているが、主幹に比べて細い。 |
|
|
員数:1 目通5.5メートル 樹高10メートル 指定年月日:平成元年11月30日 所在地:中津川市山口 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
カヤはイチイ科に属し、山麓から低地に生えている常緑針葉樹です。 このカヤの木は一部台風による枝の損失があるものの、山口地区内の他のものと比較して樹齢が古く、樹勢がよく枝張りも大きいです。 |
|
|
員数:1 周囲1.7メートル 樹高5メートル 指定年月日:平成元年11月30日 所在地:中津川市山口 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
山口地区はツバキの自生木が多く、ツバキ油を採取したり観賞用として親しまれてきたことから、昭和63年に旧山口村の村木に選定されています。 |
|
|
員数:1 1.14メートル 樹高13メートル 指定年月日:平成9年7月10日 所在地:中津川市山口 マップ:googleマップ 所有者、保持者等:個人 |
この桜はカスミザクラとヤマザクラの交雑種と考えられる貴重な存在です。開花はカスミザクラやヤマザクラに比べやや遅く、4月下旬から5月上旬です。 |
|
|
員数:1 指定年月日:平成5年6月3日 所在地:中津川市賤母 |
苗木出身でアマチュア鉱物研究家の草分けである長島乙吉氏(1890-1969)が、1929(昭和4)年に旧・山口村のペグマタイトから発見した希元素鉱物の一種です。1936(昭和11)年、東京大学の木村健二郎博士(1896-1988)らの分析で、リンと希土類元素(レアアース)に富むジルコンの変種と判明し、産地に因み「山口石」(Yamaguchilite) と命名されました。ジルコンの変種であるため、「山口石」の名は、現在は正式な鉱物名としては使われていません。 |
無形文化財有形民俗文化財無形民俗文化財史跡名勝天然記念物関連サイト
- 国指定文化財等データベース(文化庁ホームページより) 全国にある国指定文化財や国登録文化財等について触れています。
- 岐阜県文化財図録(岐阜県ホームページより) 岐阜県にある、国及び県指定文化財について触れています。
この記事に関するお問い合わせ先
文化スポーツ部文化課
電話番号:0573-66-1111(内線4303)
メールによるお問い合わせ





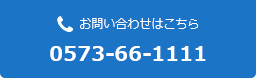
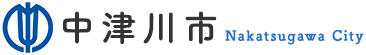
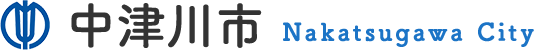
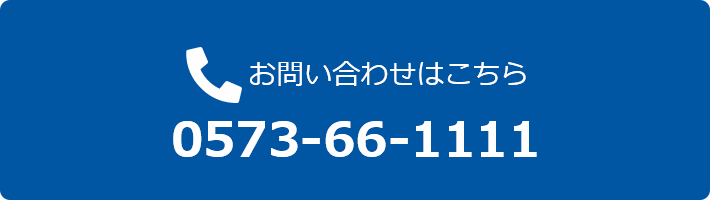

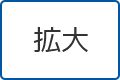


















































































































































































































































































































更新日:2024年07月25日