構造改革特区とは
構造改革特区について
「この規制がなければ、こんなことができるのに......」
経済活性化の切り札として... また規制改革を目的として...
規制緩和により実施したい、そんなアイデアをお持ちのNPO、民間団体、企業等の皆様のために...
「構造改革特区制度」 は作られました。
構造改革特区とは、構造改革特別区域法 (平成14年12月18日法律第189号)に基づいて、区域を限定してその地域の特性に注目した規制改革を実施するものです。
Q1 構造改革特区とは?
一言で言うと...
ある特定の地域にだけ全国一律の規制とは違う制度を認めることで、その地域の経済、社会を活性化させよう!という仕組みです。 これまでの日本の制度は、「全国一律みな同じ」がほとんどでした。
また、中央官庁は実際のビジネスの現場をみることはめったにありませんので、昔作った制度が実態に合わなくなったりしても気づかないことがあります。
例えば...農業が中心産業の地方では高齢化が進んで担い手がいなくなってしまっていることがあります。
このような担い手がいなくなった農地で、食品会社が自ら農業を行い、そこで採れた作物を加工し、自社のブランドをつけて販売すれば、その地方の経済活性化につながるかもしれません。
でも、このようなビジネスは、今の制度ではできないのです。
このように全国一律の規制改革がなかなか進まない分野について、地域を限定した形で規制改革を進め、その地域の活性化を図るとともに、成功事例を全国的な規制改革へつなげることにより、我が国全体の経済活性化を図ることを目的としています。
ただし県や市町村等が自ら条例の制定、許認可等を行うことで実施可能なもの、税の減免、非課税措置等、単なる税財政に関する優遇を求めるもの等は対象にならないことになっています。
Q2 手続きの仕組みは? 制度の内容は?
基本理念
- 「知恵と工夫の競争による活性」と「自助と自立の精神」を尊重します。
国があらかじめモデルを示すのではなく、自立した地方がお互いに競争していく中で経済社会活力を引き出していけるような制度への転換を促します。 2「規制は全国一律でなければならない」という考え方から、地域の特性に応じた規制を認めるという考え方への転換を進めます。
地方の自発的な立案を可能にするため、可能な限り幅広い規制を特例対象としています。 3特例措置の導入によって、構造改革特区内外において発生する可能性がある弊害を防止するための措置は、地方公共団体(県・市町村等)が主体的に対応します。 4地方の自発性を前提とするため、国による財政措置は原則としてありません。
ポイント
- 特区において特例措置を講じることが可能な規制については、あらかじめ幅広くリストとして明示し、地方公共団体がその中から選択できます。
(リストについては、地方、民間からの提案に基づき定期的に追加) - 内閣における手続き、決定の一元化
- 特区において講じられた規制の特例措置は一定の期間後、国が評価を行い、全国レベルで規制改革を行うべきものは、全国レベルの規制改革に拡大できます。
「提案」とは?
提案とは、新たなアイデアを思いついて事業を行おうとした時に、支障となる法律や規制を緩和するため、内閣官房構造改革特区推進室にどのように緩和してほしいか提案することです。
提案は、地方公共団体(県、市)、一部事務組合、民間事業者、NPO、個人の誰でも国へ直接提案できます。
提案は、単独で提案できますし、県や市との共同提案もできます。
提案の受付窓口は、「内閣官房構造改革特区推進室」です。 これらの提案に基づき、国の構造改革推進本部で検討後、関係省庁との協議を経て「特区」として新たに項目(規制の特例措置)が追加されたり、「規制緩和」され「全国で実施する項目」に追加されるようになります。
「申請」とは?
規制緩和項目の中からその地域に合った項目を選び、具体的な特区計画をつくって、それを認定するよう内閣官房構造改革特区室に申請することです。
この申請は地方公共団体のみ(県、市町村)です。 民間事業者等が直接認定申請を行うことはできません。 しかし、特区制度を利用したい民間事業者の方は、地方公共団体(県、市町村)に対し、構造改革特別区域の認定申請のための申し出をすることが出来ます。
申し出を受けた地方公共団体(県、市町村)は、国に対して申請するか否かの決定をしたうえで、申し出者に回答することになっています。
「提案」と「申請」の違いは?
構造改革特区に認定されるためには、申請手続きを行う必要があります。
しかし、規制緩和のためのアイデアを出す「提案」と「申請」とは、全く流れの異なるものです。
「提案」=法律などにより規制されている内容の緩和を国に提案して認めてもらうことです。 どなたでも出来ます。
「申請」=既に提案によって認められた規制緩和項目を使って実際に事業を行うため、地方公共団体(県、市町村)が行うものです。
(特区の認定を受けるためには、「提案」は必ずしも行う必要はなく、「提案」をしているか、していないかは認定にあたって有利にも不利にもなりません)
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室政策課
電話番号:0573-66-1111(内線 331・332)
メールによるお問い合わせ





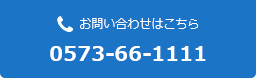
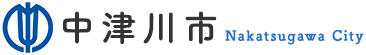
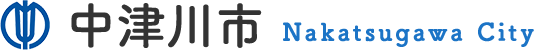
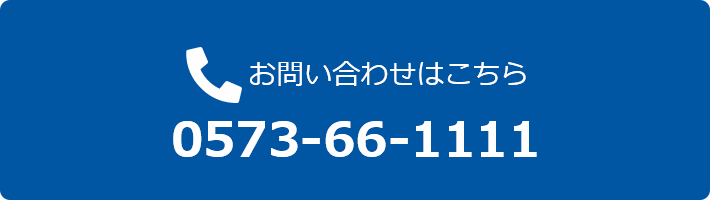

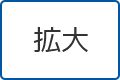



更新日:2022年10月19日