インフルエンザの流行に注意しましょう
季節性インフルエンザは流行性があり、いったん流行が始まると、短期間に多くの人へ感染が拡がります。特に、高齢者の方や基礎疾患のある方が感染すると、重症化するおそれがあります。インフルエンザをはじめとする感染症の予防には「手洗いの徹底」と「マスクの着用を含む咳エチケット」などが有効です。インフルエンザについて知り、一人一人が予防対策に取り組みましょう。
インフルエンザと風邪の違いは?
普通の風邪
多くは、のどの痛み、鼻水、くしゃみや咳などの症状が中心で、全身症状はあまりみられません。発熱もインフルエンザほど高くありません。
インフルエンザ
インフルエンザウイルスに感染することで起こり、38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身の倦怠感などの症状が比較的急速に現れるのが特徴です。合わせて普通の風邪と同じように、のどの痛み、鼻水、咳等の症状もみられます。お子さんはまれに急性脳症を、高齢者の方や免疫力の低下している方は肺炎など重症になることがあります。
インフルエンザの予防法
外出後の手洗い
流水、石鹸による手洗いは手指についたインフルエンザウイルスを除去する有効な方法です。インフルエンザにはアルコール製剤による手指衛生も効果があります。
適度な湿度の保持
空気が乾燥するとのどの粘膜の防御機能が低下し、インフルエンザにかかりやすくなります。特に乾燥しやすい室内では、加湿器などを使い適切な湿度(50~60%)を保つことも有効です。
休養とバランスのとれた栄養摂取
体の抵抗力を高めるために、十分な休養とバランスのとれた栄養摂取を日ごろから心がけましょう。
流行期には人混みへの外出を控える。咳エチケットも忘れずに
インフルエンザの流行期には、特に高齢者の方や基礎疾患のある方、妊婦、体調の悪い方は人混みへの外出を控えましょう。人混みに出かけるときには、ある程度、飛沫感染等を防ぐことができる不織布製のマスクを着用することも1つの防御策です。うつらない為にも人にうつさない為にもマスク着用を含めた「咳エチケット」を心がけましょう。
室内ではこまめに換気をする
換気は季節を問わず、また新型コロナウイルス対策としても十分な換気が重要です。
窓開けによる換気のコツ
対角線上にあるドアや窓を2ヶ所開けると効果的な換気ができます。窓が1つしかない場合は、部屋のドアを開けて、扇風機などを窓の外に向けて設置しましょう。
冬場の換気の留意点
- 暖房器具を使いながら換気を行いましょう
- 暖房器具の近くの窓を開けると入ってくる冷気が暖められ室温の低下を防ぐことができます。
- 短時間に窓を全開にするより、一方向の窓を少しだけ開けて常時換気を確保する方が、室温変化を抑えられます。この場合でも暖房で室内・室外の気温差が維持できれば、十分な換気量を得られます。
- 人がいない部屋の窓を開け、廊下を経由して、少し暖まった空気を取り入れることも、室温を維持するために有効です。
インフルエンザにかかった時の対応
- 人混みへの外出を控え、無理をして学校や職場等に行かないようにしましょう
- 安静にして、休養をとりましょう。特に睡眠を十分にとることが大切です。
- 水分を十分に補給しましょう。お茶でもスープでも飲みたいもので結構です。
- 高熱が続く、呼吸が苦しい、意識状態がおかしいなど具合が悪ければ早めに医療機関を受診しましょう。
- 咳やくしゃみのある時は、「咳エチケット」を徹底しましょう。
咳エチケット
咳やくしゃみを人に向けて発しない、咳やくしゃみの出る時はできるだけ不織布マスクをする、マスクがない場合はティッシュやハンカチなどで口と鼻を覆う、手のひらで咳やくしゃみを受けた時はすぐに手を洗う
どのくらいの期間外出を控えればよい?
一般的に、インフルエンザ発症前日から発症後3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出するといわれています。 排出されるウイルスの量は解熱とともに減少しますが、解熱後もウイルスを排出すると言われています。排出する期間に個人差がありますが、咳やくしゃみの症状が続いている場合には、不織布マスクをするなど、周りの方へうつさないように配慮しましょう。
学校保健安全法の出席停止期間
学校保健安全法では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としています(ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときはこのかぎりではありません)
予防接種
インフルエンザ予防接種には対象者によって予防接種法上の「定期接種」と「任意接種」があります。予防接種を希望する方は、かかりつけ医とよくご相談の上、接種を受けるかどうかご判断ください。
定期接種
重症化予防を目的に、主に65歳以上の方を対象に予防接種法における定期接種が行われます。以下の対象者の方には接種費用の一部助成があります。
- 65歳以上の方
- 60歳〜64歳で以下に該当する方
心臓、腎臓、呼吸器の機能障害、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害があり、身体障害者手帳1級相当の方。
任意接種
上記の対象者以外の方は任意接種となり、接種を実施する医療機関等で自費により接種を受けることができます(1歳〜高校3年生の方は接種費用の助成が受けられます)
(注)「インフルエンザ予防接種(定期接種)」と「子どもインフルエンザ予防接種費用助成」に関する詳細については下記リンクからご確認ください
この記事に関するお問い合わせ先
医療福祉部健康課
電話番号:0573-66-1111
内線:予防保健係623・健康支援係(母子)626・健康支援係(成人)627
メールによるお問い合わせ





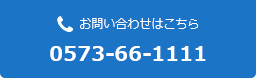
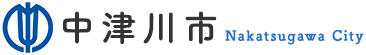
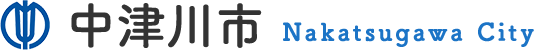
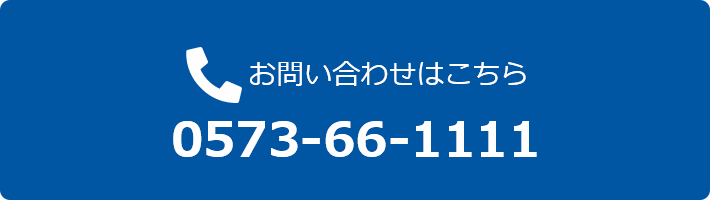

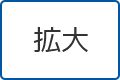



更新日:2025年10月14日