杵振り花馬祭り

鮮やかな赤、黄、青色の笠と衣装を身に纏い幾百年の伝統を受け継ぐ杵振り踊り
賑やかなお囃子と力強く響く花馬唄。石段を駆け上がる神馬と花馬
山里のお祭りをぜひご覧ください
安弘見(あびろみ)神社例大祭に奉納される、杵振り踊り(県重要無形民俗文化財)は毎年4月16日に一番近い日曜日に行われます。杵振り踊りの行列の構成は、稚子、鬼、天狗、おかめ、ひょっとこ、杵振り、お囃子、蠅追い、大獅子と総勢約150人。蛭子座から安弘見神社までの2キロメートルを練り歩きます。

赤・黄・青の市松模様の臼をかたどった縦長の笠をかぶり、赤いはっぴに白いたすきをかけ水玉模様のかるさんに黄色のはばき姿の若者が、勇ましい太鼓の音に合わせ、「ソーイ」「ソーイ」のかけ声とともに杵を振りながら練り歩きます。
令和7年の杵振り花馬祭りの開催内容
日時
令和7年4月13日(日曜日) 10時15分〜16時30分
場所
安弘見神社
主なスケジュール
10時15分〜 神事(安弘見神社)
11時00分頃 神楽舞(安弘見神社)
12時20分頃 杵振り出発(蛭川総合事務所付近)
13時00分頃 神馬・花馬出発(蛭川総合事務所付近)
14時00分頃 子ども杵振り・子ども手踊り(安弘見神社)
14時40分頃 杵振り到着(安弘見神社)
14時45分頃 花馬唄披露(安弘見神社)
15時00分頃 婦人手踊り(安弘見神社)
15時30分頃 杵振りクライマックス「大獅子の洞入り」(安弘見神社)
16時10分頃 神馬・花馬 花取り・駆け上がり(安弘見神社)
16時20分頃 餅投げ(花馬駆け上がり終了後)
8時20分〜11時30分まで こどもみこし
7時00分〜14時00分まで 厄年みこし
前夜祭
17時00分〜 神事(安弘見神社)
19時00分〜 手筒花火(安弘見神社境内)
杵振り踊りの由来と伝承
蛭川の人たちや出身者の心の支えになっているものに「杵振り踊り」があります。 杵振り踊りは杵振り祭りとも云われ、獅子舞に付随した踊りとして伝わっています。 今では、その逆に獅子舞が杵振り踊りに付随したようになっていて、派手な衣装と奇妙な形をした笠、紅と黒に塗り分けた杵を軽妙にあやつりながら、金幣社安弘見(あびろみ)神社の大祭(4月16日に一番近い日曜日)に奉納されます。
杵振り踊りの起源
杵振り踊りの起源は400年とも600年とも云われ、はっきりしません。 『昔ヨリ蛭川之杵フリ祭リトゆふて名高祭典デス フリ獅子は昔御嵩薬師祭典の伝を習請たると言事 角くとしたること不分明』と明治後期の記録帳に書き残してあるのが唯一の記録です。 廃仏毀釈以前は、牛頭天王社(明治改元後は安弘見神社に改名)の中に薬師堂があり、杵振り踊り、獅子舞はこの薬師堂の祭りで、8月15日(旧暦)と決まっていました。 獅子舞に杵振り二人が随行することが例となっていましたが、現在のように多人数になったのは大正8年~9年(1919~1920)のころといわれています。 もとは五穀豊穣を願って踊ってきたものと伝えられ、臼を思わせる笠と穀物を搗く杵はこの願いに最も密接につながっていることでもわかります。 また、「剣の舞」が転化したものだとも言われていますが、それは蛭川に伝わる南朝伝説に由来するものです。
お問い合わせ
蛭川観光協会事務局 (蛭川総合事務所内 電話:0573-45-2211 )
この記事に関するお問い合わせ先
市民部蛭川総合事務所
電話番号:0573-45-2211
ファックス:0573-45-2477
メールによるお問い合わせ





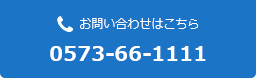
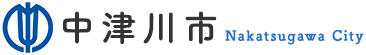
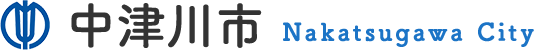
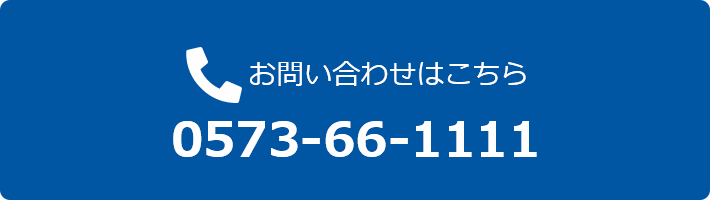

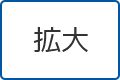



更新日:2025年04月10日