ひとつばたご
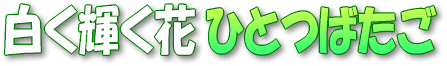
ひとつばたごめぐり
蛭川地内のひとつばたごを巡りながらウオーキングができる「ひとつばたごめぐり案内図」を配布しています。
ひとつばたごの見頃は、5月の連休から中旬頃です。

令和6年5月10日現在(自生地:長瀞)

令和6年5月10日現在(自生地:一之瀬)

令和6年5月10日現在(自生地:今洞)

昨年の開花状況

昨年の開花状況
ひとつばたごとは?
「ひとつばたご」は別名「ナンジャモンジャ」、英語名「Snow-flower-Fringe tree」といい、蛭川の人ならほとんどの人が知っている樹木です。
旧蛭川村では、この「ひとつばたご」を村の木と指定(昭和48年5月25日制定)し、地域内の自生木の多くを天然記念物として大切に保護してきました。
ひとつばたごは、日本では岐阜県の東濃地方と愛知県、長野県の一部、そして長崎県対馬の北端にのみ自生しています。岐阜県東濃地方では、木曽川、土岐川(庄内川)筋に多く自生しています。 なお蛭川を含む東濃地域、周辺の市町村でも多くの自生地が天然記念物として指定され大切にされています。
最近、近畿地方で泥炭化された20万年ほど前の木が発見されています。泥炭化された木が発見されたということは、当時ひとつばたごが繁茂していたことを意味します。このように、古い時代には広い範囲に分布していましたが、今では一部の限られた地域にだけ残っている生物を遺存種といい、ひとつばたごの自生地が地球の成り立ちや植物の分布をひも解く鍵であるといわれています。
ひとつばたごの語源
ひとつばたごは、「ヒトツバ」と「タゴ」にその意味を分けることができます。ヒトツバは、一つ葉と書きます。タゴは、田子と書き、田んぼのはざ木という道具と、トネリコを意味します。トネリコは複葉です。よってひとつばたごは、一つ葉のトネリコ(複葉)ということになります。 なぜ雪の花とも呼ばれるのでしょうか。ひとつばたごは学名を「Chion anthus retusus」(キオナントスレトゥースツ)とラテン語でいいます。Chionは「雪」を、anthusは「花」を、retususは「ややへこんだ形」とか「葉の先が鈍く尖っている」とかいう意味です。学名を直訳すると「葉がややへこんだ形の、先が鈍く尖った雪のような花」となります。現物はまさしくそのとおりです。
現在の東京神宮外苑のあたり、江戸時代、青山六道辻にあったというひとつばたごは場所がよいため、非常に高名になり″六道木″と呼ばれていたようです。しかし、ほんとうの名前がわからないため「なんじゃもんじゃ」と呼ばれるようになったそうです。「なんじゃもんじゃ」といわれるようになったのもそんなに古くはなく、明治の終わり頃ということです。 「なんじゃもんじゃ」はひとつばたごだけを呼ぶだけではないと、民俗学者の柳田國男氏は″なんぢゃもんぢゃの樹″の中に書いています。クスノキとかアブラチャンの大樹なども「なんじゃもんじゃ」と呼ばれています。
ひとつばたごの雌雄性・・・雌雄異株ではない
ひとつばたごは、合弁花類のうちモクセイ科に属する落葉高木です。樹高は15~20メートル。胸高直径50~60センチメートルにもなります。幹は直立してよく分枝し、樹皮は灰褐色です。
たいていの植物図鑑には『雌雄異株』とありますが、一株だけ立っているひとつばたごでも実をつけます。蛭川産のひとつばたごにも雌雄異株はありません。今まで雌株と思われていたものは、おしべ、めしべを備えた両性化株なのです。
蛭川中学校の校章はヒトツバタゴ

蛭川中学校の校章
蛭川中学校の校章は、ひとつばたごの花がデザイン化されています。 昭和22年(1947年)新制中学校が発足すると、学校では校章づくりに取りかかりました。当時そのデザインを考案した林芳樹さんは、次のように話していました。(引用:蛭川村報 平成元年(1989)5月号)
「私は代用教員で赴任していました。新制中学になったものの記章に適当なものがなく、早速作らねばと奥田穂浪校長が先生方らと相談され、"蛭川村にはひとつばたごという国の天然記念物がある。その花をなんとか記章にできないか"とひとつばたごの貴重なことを話されました。私はそれまでひとつばたごのことは知らず、そこで牧野植物図鑑にあったところ、1本の枝に3つの花がついているのが載っていました。これを基に図案化して採用されたというわけです。三角形は恵那高の校章など多くに使われていて平凡になってしまいました。私としてはもう少しユニークなものをと考えていたんですけどね・・・。 とにかく記章の注文も私にまかされまして、わざわざ東京の神田まで出掛けて行って、多くの旧制高校の記章を作っている専門の業者に頼んできました。出来たものは少し大きすぎるということで、男子生徒にはあまり歓迎されなかったようですが、私たちのあこがれの旧制高等学校と同じ大きさだということをよく話しておきました」
国指定天然記念物・長瀞(ながとろ)のひとつばたご
概要
- 所在地 中津川市蛭川4129-53
- 国天然記念物指定年月日 大正12年3月7日
- 目通周囲 1.4メートル
- 樹高 13メートル
- 枝張り 約10メートル
初夏に雪を被ったように真っ白な花を咲かせる不思議な植物「ヒトツバタゴ」。その姿が珍しいことから「なんじゃもんじゃ」とも呼ばれています。ヒトツバタゴは限られた地域のみ自生する植物で、日本では東濃地域と愛知県、 長崎県対馬市の一部でしか自生していません。東濃地域の中でも、特にここ蛭川の地にはたくさんの自生木が残っています。 奈良井区長瀞(ながとろ)に自生しているヒトツバタゴは樹齢100年を越え、高さ約13メートル、枝張り約10メートルという巨木です。国の天然記念物に指定され、「白い花の咲く里ひるかわ」を象徴する存在となっています。満開になると、雪が降ったように真っ白に咲きます。 ひとつばたごはモクセイ科の落葉樹で、国内での分布は木曽川中流域と対馬のみです。
5月中下旬に四裂して細く白い花が咲き、満開の時には雪のようです。非常に珍しく見慣れない木であるため、「ナンジャモンジャの木」ともいわれます。
和田川の左岸に自生しており、東側がひのき林で囲まれていた影響で、川に面した側の樹勢がよくなっています。樹齢は100年以上と推定されます。以前はこの周辺の和田川沿いに数本自生していましたが、現在ではこの木のみです。

長瀞(ながとろ)のひとつばたご
(平成20年5月17日撮影)

ライトアップされた『長瀞のひとつばたご』

ひとつばたごのアップ
蛭川のひとつばたご
蛭川では、あちこちでひとつばたごを見ることができます。ひとつばたごは蛭川の人たちにより大切に守られ、毎年白く輝く花を咲かせるのです。
長瀞のひとつばたご

撮影日
平成18年5月31日
備考
奈良井区長瀞に自生しているひとつばたご。樹齢は100年を越え、高さ約14メートル、枝張り約12メートルという巨木である。国の天然記念物に指定され、「白い花の咲く里ひるかわ」を象徴する存在になっている。
今洞のヒトツバタゴ群

撮影日
平成18年5月31日
殿塚のひとつばたご

撮影日
平成18年5月31日
備考
旧田口商店前
樺瀬のひとつばたご

撮影日
平成18年5月25日
備考
平成17年に周りの木を切ったら見つかったひとつばたごの自生木。目通周囲1.07メートル、樹高21.8メートル、枝張り(北5.5メートル・南6.0メートル・東9.0 メートル・西7.5 メートル) 湿潤な沢地に自生している。地上から約2メートルから枝が長く分岐しているが、主幹に比して細い。支障木によって日光を遮られていた影響で、枝葉は疎らであるが、県下では最も高いひとつばたごである。
勤彊の碑の裏のひとつばたご

撮影日
平成18年5月25日
備考
総合事務所西駐車場
ひとつばたごの自生木

撮影日
平成18年5月25日
備考
ひとつばたご・シデコブシ・ハナノキの3種類の貴重な遺存植物が一カ所にそろっている場所に咲くひとつばたご。
田原尻のひとつばたご

撮影日
平成18年5月25日
備考
商工観光案内板そばのひとつばたご
博石館横のひとつばたご

撮影日
平成18年5月24日
備考
市指定天然記念物指定日:昭和48年1月18日
樹齢は不明で、高さは約10メートル。目通り(太い方の1本)85センチ。
一之瀬のひとつばたご

撮影日
平成18年5月24日
備考
市指定天然記念物指定日:昭和31年7月12日
樹齢は不明。高さ約10メートル、目通り1メートル。県道恵那蛭川東白川線の通りにあります。
小学校石垣下のひとつばたご

撮影日
平成18年5月19日
備考
総合事務所前
この記事に関するお問い合わせ先
市民部蛭川総合事務所
電話番号:0573-45-2211
ファックス:0573-45-2477
メールによるお問い合わせ





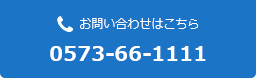
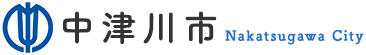
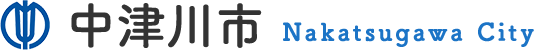
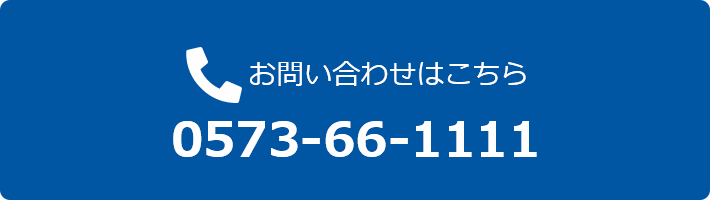

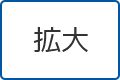



更新日:2025年04月08日