汚泥コンポスト
概要
私たちが毎日出す生活排水から生まれる「おでい」。この汚泥を循環利用するいろいろな方法があります。まず、身近な資源であるおでいの農地還元からはじめの一歩を踏み出してみませんか?
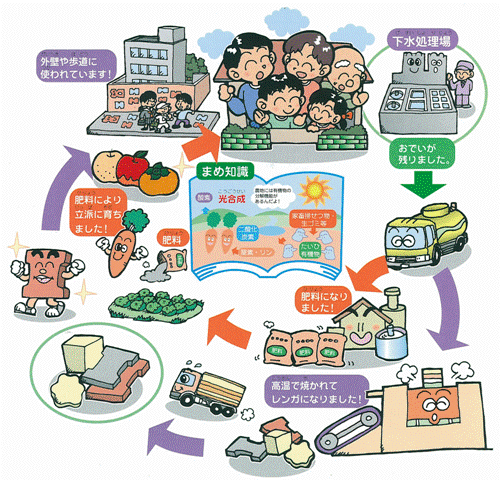
汚泥とは
みなさんは「おでい」と聞いて、どう感じられますか? ここでは、「農業集落排水おでい」と呼ばれているもののこと。 汚泥のリサイクルは農村での生活はもとより、地球のエコロジーとも深く関わっています。
環境保全活動を行なっていくうえで、よく使われるスローガンに、「Think Globally,Act Locally(地球規模で考え、地域規模で行動しよう)」という言葉があります。 私たちにまずできるのは、地球環境を知り、身近なことから行動すること。
汚泥のリサイクルがそのひとつになりうるということを考えてみてください。
汚泥を知ることは環境を知ること
汚泥(おでい)は「汚れた泥」ではありません。
あまり知られていませんが、汚泥は私たちが毎日出す生活排水から生まれるものなのです。生活排水は養分(糖分のようなものと考えてください)が多く含まれるので、微生物に食べてもらって浄化することが必要です。
そして、微生物の死骸が沈殿し、「おでい」(有用な地域資源)となります。この汚泥処理の仕方がいま問題になっています。
地域の環境づくりは、地球のエコロジー
私たちが暮らす"地球"。その環境が危機的な状況にあることは、新聞やテレビなどで毎日報道されています。循環型社会の構築は、環境保全のうえで大切なことなのです。
農業・農村の未来は環境とともに
かつて、農村は理想的な循環型社会を実践する共同体でした。現在の農村でも、農業を核としたリサイクル活動を通して循環型社会をつくることができるはずです。
汚泥の農地還元からはじまるリサイクルの環
農村の生活排水をきれいにして、自然へ還す。農業集落排水施設は、農村においてとても大切な役割を果たしています。そして、そこから発生するおでいは肥料として農地に還元できるのです。
Let's Begin! さあ、はじめようドロコロジー
汚泥を農地へ還元するために、いろいろ考えてみました。自分たちの地区にあった循環を自分たちで考えて実行していきましょう。
さあ、みなさんもできることからはじめてみませんか?
注:ドロ+エコロジー=ドロコロジー(造語です)
「汚泥コンポスト」
汚泥コンポストとは
農業集落排水(農集)の処理場は、微生物の力を借りて汚水を浄化しています。この微生物はどんどん増殖するため、増えすぎた微生物やその死骸が汚泥となり排出されています。
この汚泥を発酵し、肥料にしたものをコンポストといい、その施設をコンポスト施設といいます。このコンポスト施設は、含水比98.5%と泥水状態である生汚泥を脱水作業により粘土状(含水比85%程度)にし、次の工程である発酵槽へ送り含水比40%程度まで発酵乾燥させます。
この発酵させる段階で48時間以上温度を65度に確保させ、汚泥中に含まれている病原菌類や雑草などの種子を死滅させ不活性化することで、肥料としての安全性が保たれます。
また、この肥料を使用するためには、肥料の品質の確保等に関する法律による普通肥料としての登録が義務付けられており、この中で、肥料成分や重金属の値などを表示しています。
(注記)重金属は処理の過程で含まれるものではなく、人間の食べる物の中に含まれているものであり、その量は基準値以内です
使用方法(野菜)
- 「おでいコンポスト」は基肥として用い、施用量は窒素成分量で化成肥料の等量~2倍量とする。
| 作目 | 現物量 | 窒素量 | (参考) 化成肥料での窒素量 |
|---|---|---|---|
| 夏秋トマト(春撒き) | 基肥 23キログラム/アール | 0.75キログラム/アール (化成肥料の1.5倍量) | 0.5キログラム/アール |
| 白かぶ(春撒き) | 基肥 60キログラム/アール | 2キログラム/アール (化成肥料の2倍量) | 1キログラム/アール |
| 白かぶ(秋撒き) | 基肥 30キログラム/アール | 1キログラム/アール (化成肥料の等量) | 1キログラム/アール |
| ハクサイ(秋撒き) | 基肥 45キログラム/アール | 1.5キログラム/アール(化成肥料の等倍量) | 1.5キログラム/アール |
花き(花壇苗の場合)
- 春植え花壇では、窒素成分量で化成肥料の2~4倍量の範囲で施用する(肥料が必要な花きと、肥料が多すぎると栄養過多で花が減少する花きがあるので、2~4倍量の範囲内で調整する)。定植後1ヶ月以上経過した頃から、生育状況により追肥を行なう。
- 秋植え花壇では、窒素成分量で化成肥料の4~6倍量の範囲で施用する。6倍量を施用すれば、春、地温が上昇するまでは追肥の必要はない。
| 作目 | 現物量 | 窒素量 | (参考) 化成肥料での窒素量 |
|---|---|---|---|
| サルビア(春植え) | 基肥 120キログラム/アール | 4キログラム/アール (化成肥料の4倍量) | 1キログラム/アール |
| ペチュニア(春植え) | 基肥 120キログラム/アール | 4キログラム/アール (化成肥料の4倍量) | 1キログラム/アール |
| マリーゴールド(春植え) | 基肥 60キログラム/アール | 2キログラム/アール (化成肥料の4倍量) | 0.5キログラム/アール |
| パンジー(秋植え) | 基肥 120~180キログラム/アール | 4~6キログラム/アール (化成肥料の4~6倍量) | 1キログラム/アール |
| ビオラ(秋植え) | 基肥 120~180キログラム/アール | 1.5キログラム/アール (化成肥料の4~6倍量) | 1キログラム/アール |
(注記)「おでいコンポスト」施用と同時に、塩化加里1.7キログラム/10アールを施用すると、より良い効果となる。
水稲の場合
- 「おでいコンポスト」は基肥として用い、穂肥は化成肥料を慣行どおり行なう。含まれる窒素の肥効は緩やかであるが、一発施肥が可能なほどではない。
- 施用量は、窒素成分量で慣行の化成肥料の2倍量程度とする。
| 品種 | 現物量 | 窒素量 | (参考) 化成肥料での窒素量 |
|---|---|---|---|
| コシヒカリ | 基肥 210キログラム/10アール | 7キログラム/10アール (化成肥料の2倍量) | 3.5キログラム/10アール |
注意点
野菜の場合
- 加里はほとんど含まれていないので、化成肥料での窒素量と等量の成分量となるよう、別途塩化加里等を施用する。
- トマトのように窒素量の適正域が狭い作物では、過剰施用とならないよう留意する。
- 生育に過不足を生じた場合は追肥の施用時に調整する。
花き(花壇苗)の場合
- 加里はほとんど含まれていないので、化成肥料での窒素成分量と同量以上を塩化加里等を用いて施用する。
- 地温により肥料成分の溶出速度が左右される。特に地温が高い夏期には、施用後、1週間程度で一気に溶出してくることから、過度の施用(窒素成分量で化成肥料の6倍量以上)は濃度障害を招く恐れがあるので注意する。
- 逆に、地温が低い冬期での施用は溶出が抑えられるので、窒素成分で化成肥料の4~6倍量を施用してもよい。
水稲の場合
- 加里はほとんど含まれていないので、化成肥料での窒素量と等量の成分量となるよう、別途塩化加里等を施用する。
留意事項
- 基肥は化成肥料と同時期に施用し、追肥は原則として化成肥料を使用する。
- リン酸を多量に含むので、リン酸肥料は別途施用する必要はない。
- 吸湿により、ペレットが泥状化し均一な散布が困難になるので、乾燥した場所に保管する。
- 重金属(ガドミウム、鉛)の土壌への蓄積は、3年間の連用では認められなかった。
- 製造日によって成分に多少の変動があるので、追肥による調整が必要な場合がある。
- 加里をほとんど含まないので、加里を豊富に含まないあるいは不明な圃場では、別途施用することが望ましい。
コンポスト施設稼働状況
中津川市では、市町村合併後10地区で農集処理場が稼動しています。処理場では受益者や希望者にコンポストを無料で配布しています。コンポスト化している施設は次のとおりです。
川上地区(肥料登録H14年4月25日)
コンポ菜花良(なかよし)登録証 (PDFファイル: 13.6KB)
コンポ菜花良(なかよし)分析結果報告書 (PDFファイル: 305.3KB)
コンポ菜花良(なかよし)放射性物質測定結果 (PDFファイル: 226.1KB)
田瀬地区(肥料登録H17年5月10日)
たせコンポ分析結果報告書 (PDFファイル: 298.0KB)
たせコンポ放射性物質測定結果 (PDFファイル: 224.5KB)
坂本北部地区(肥料登録H16年3月10日)
夢コンポ分析結果報告書 (PDFファイル: 296.9KB)
夢コンポ放射性物質測定結果 (PDFファイル: 224.9KB)
高山地区(肥料登録H20年9月25日)
たかやまコンポ分析結果報告書 (PDFファイル: 300.5KB)
たかやまコンポ放射性物質測定結果 (PDFファイル: 224.1KB)
阿木地区(肥料登録H22年4月26日)
若あゆコンポ分析結果報告書 (PDFファイル: 297.7KB)
若あゆコンポ放射性物質測定結果 (PDFファイル: 224.5KB)
問い合せ先
中津川市浄化管理センター 電話番号0573-65-7344 ファックス0573-62-6168
この記事に関するお問い合わせ先
環境水道部下水道課
電話番号:0573-66-1111
(内線:計画係522・整備係531,532・管理係523,525)
メールによるお問い合わせ





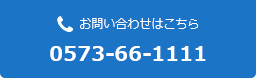
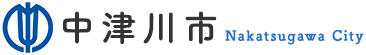
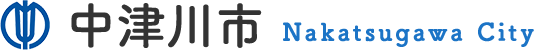
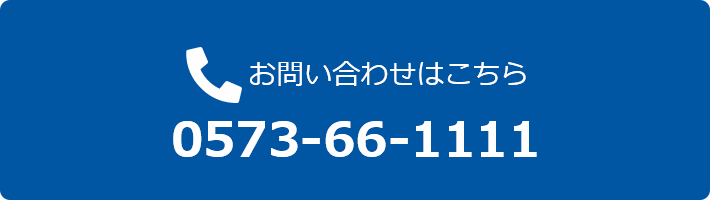

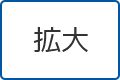



更新日:2025年08月12日