地震や風水害で被害にあってしまったときの証明
片付け前にやるべき大事なこと
自然災害(地震や風水害)で自宅が被災したら、何から手をつけていいかわからず、とりあえず片付けから始める方が多いことと思います。しかし、被災した自宅を片付ける前に、まずは、家の被災状況を写真で記録しておいてください。
り災証明書は各種被災者支援策の適用の判断材料等として、り災届出証明書は被災者自身が加入している保険請求等に活用されていますので、修理や片付けをしてしまうと証明が困難となるため、現場保存が望ましいですが、復旧を急がれる場合、写真を撮影しておいてください。
主な証明書の活用先
必ず支援等を受けられるとは限りませんが、主に次のようなものがあります。詳しくは、支援等を実施している各申請先にご確認ください。
- 給付:被災者生活再建支援金、義援金等
- 融資:住宅金融支援機構融資、災害援護資金等
- 減免・猶予:税、保険料、公共料金、ごみ処理等
- 現物給付:災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与、住宅の応急修理制度等
- その他:被災者が加入している保険請求等
証明書の種類
り災証明書とは、地震や風水害で所有する住家が被害を受けた場合、その被害の程度を証明するものです。
り災届出証明書とは、地震や風水害により被災した事実を証明するものであり、被害の程度を証明するものではありません。人的被害や家屋(住家以外の車庫・カーポート・物置)、堀、土地、門扉などの付帯物、家財などを証明の対象としています。
火災に起因する被害は、各消防署にて証明発行を行っています。
り災証明書の住家被害の程度
被害の程度には、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の5種類があります。準半壊に至らない(一部損壊、床下浸水)被害の程度は、ほとんどの場合、支援の対象外とされています。
被災写真を撮るポイント
- 撮る前には
- カメラの日時設定は正確にしておき、写真に撮影日時の記録を残しましょう。
- 最初に撮影する箇所と撮影の順序をあらかじめ決めておくと整理が容易になります。
- 被害を受けた部屋・箇所は全て撮影しましょう。
- 建物の全景を撮る
- 遠景で建物全体を周囲4面から撮影します
- 浸水した深さを撮る
- メジャーを使って、地面や床面から水が浸かった深さが分かるように撮影
- 上の状態で、測定場所が分かるように遠景を撮影
- 上の状態で、メジャーの目盛りが分かるように近景も撮影
- 被害箇所や被害にあった家財を撮る
- 被害箇所ごとに遠景と近景の2枚セットで撮る
- 何の被害箇所を撮影したのかが分かるように指を差して撮るとよい
- 主な撮影する被害箇所は、外壁・屋根・基礎・内壁・天井・床・ドア・窓・キッチン・浴室・トイレなど
- ご自身が加入する保険請求に使用する場合は、対象となる家財などの撮影も行いましょう
- その他、特にチェックする箇所
- 地震の場合
- 屋根がデコボコしていないか
- 屋根瓦のズレや破損、落下がないか
- 壁の剥離や亀裂が入っていないか
- 基礎の部分に幅0.3ミリ以上のひび割れがあるか
- 柱や住家全体が傾いていないか
- 柱に損傷がないか
- 衛生設備(キッチン、洗面台、トイレ、浴室等)の損壊
- 水害の場合
- どこまで浸水したのか
- 床や畳、壁に被害がないか
- 地震の場合に例示したような被害
- 地震の場合
り災証明書・り災届出証明書の発行
申請できる人
建物の所有者及び居住する世帯主(借家人)
申請時に用意するもの
- 申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 被害状況が分かる写真
- 委任状(被災者以外の方が申請する場合は、被災者からの委任状が必要です。)
発行手数料
無料ですが、1世帯1枚のみ発行いたします。複数の支援を受けられる場合は、コピーしてご使用ください。
り災証明書発行の流れ
- 被災者から(健康福祉会館1階の社会福祉課)へ発災から3か月以内に申請
- 被害状況の現地調査と判定(職員がお伺いします)
- 現地で事実が確認できない場合は、証明は発行できません。
- 証明書の発行、受取り
- 申請から発行までおおむね2週間です。り災状況や調査内容によっては発行に時間がかかることがあります。
申請書様式
この記事に関するお問い合わせ先
総務部防災安全課
電話番号:0573-66-1111
(内線:生活安全係162・防災対策係165・消費生活相談係167)
メールによるお問い合わせ





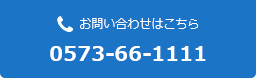
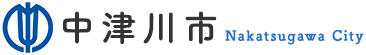
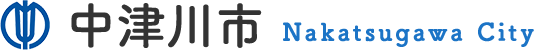
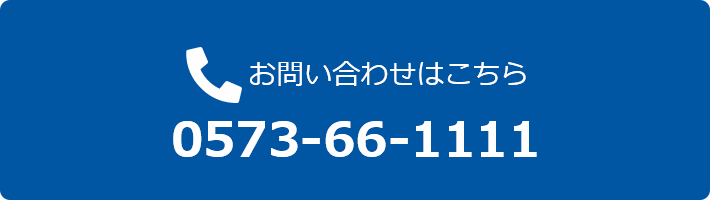

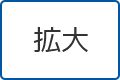



更新日:2022年06月06日