地域の由来・歴史
由来
阿木に屏風岩と呼ばれる史跡があり、その岩陰でお産をされた神様が休まれた時に、ここは「あんき」だといわれ、このことから阿木の呼び方が始まり、「あんき」→「安気」→「安岐」→「安木」→「阿木」と変わってきたといわれている。
一番古い文献にある恵奈六郷では「安岐」が使われている。
歴史(年表)
平成の大合併以前に、この地域でも明治の大合併と昭和の大合併の際にいくつかの市町村の合併が行われ、現在の状況に至っています。
阿木地区は昭和の大合併のさなか、昭和32年11月1日に中津川市と合併しました。現在も「阿木」と「飯沼」の二つの大字があります。このいずれも、徳川時代においては村と称していました。
徳川時代
元禄15年(1702年)、石川(後に松平と改称)能登守が信州・小諸より岩村(岩村藩)に移り住むように命じられたとき、阿木村・飯沼村の両村ともその領地となりました。
石高は阿木村、同枝郷福岡新田・広岡新田・青野村・両伝寺村をあわせ2027石2斗1升9合、飯沼村、同枝郷大野村をあわせて456石2斗をそれぞれ納米していました。
(注)郷
律令制における地方行政の単位。郡の下の最下位の単位である里(り)を奈良時代に改めたもので、後に下へ村が設けられ、数村を合わせて郷と呼ぶようになった。
(注)石高
1石は10斗であり、よって100升、1000合ということになる。米1合がおおむね1食分であるので、1石は1人が1年間に消費する量にほぼ相当する(365日×3合/日=1095合)。
大区小区制時代
明治4年7月には、廃藩置県により笠松県の管轄となりましたが、同年11月に大区12、小区175に区割りされた岐阜県と改められ、両村とも第12大区第7小区に属することになりました。
(注)大区小区制
明治時代の1872年に施行された地方制度で、府県の下に大区をおき、大区の下に小区をおくものである。
大区には区長、副区長をおいた。小区には戸長と副戸長をおき、これには江戸時代の村役人(庄屋・名主)や町役人(年寄など)、大庄屋などの経験者を任命した。区の名前には数字を用いた。
郡区町村編成時代
明治12年7月には、大小区制から郡制へ移行され、恵那郡役所の管轄となりました。
この間に前掲の大野村が飯沼村に、福岡新田・広岡新田・青野村・両伝寺村が阿木村へとそれぞれ合併しました。
町村制時代~現在
その後、明治17年に阿木・飯沼両村に連合役場が設けられ、次いで明治22年10月の町村制が実施される時には、両村組合役場が組織されました。
明治30年4月1日に、両村を合併して阿木村となり、昭和32年11月1日に中津川市との合併後も従来の村を各大字とし、現在に至っています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部阿木事務所
電話番号:0573-63-2001
ファックス:0573-73-0001
メールによるお問い合わせ





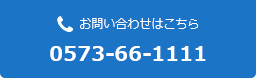
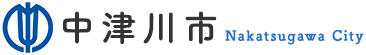
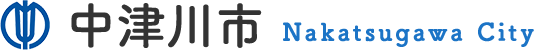
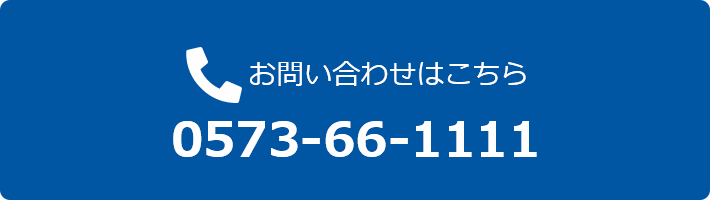

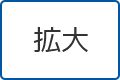



更新日:2022年03月17日