第4分団
八屋砥古墳群(はちやどこふんぐん)

八屋砥の通称・中根に古墳が4~5基ある。どれも直径10メートルくらいの円墳である。つくられた時代は調査がなされていないのではっきりしないが、今から1400年位前ではないかと思われる。村人はこの祖先が眠る古墳を拝みながら暮らしたのであろう。
打杭第1ため池

大正8年、阿木本郷耕地整理組合で作られたため池で、阿木の久須田と岩村に水を引いている。池の水は阿木川から取り入れている。
両伝寺検見坂入口(りょうでんじけんみざかいりぐち)

両伝寺から山野田へ通じる道で、山野田側が検見坂といわれ、むかし石高を決めたと言われている。石高によって年貢が決められた。
(注)石高:土地の表示に用いられた米の収穫高
(注)年貢:昔の税金で、米・麦・大豆などをおさめた。
橋場災害碑

阿木地区では昭和28年、32年、36年とほぼ4年ごとに集中豪雨による災害が発生した。中津川市に合併した昭和32年以降復旧工事が行われ、昭和40年4月に今のようになり、その記念としてこの碑が建てられた。 JAの前の橋はこのときの水害で道路や家が流されたなごりである。コンクリートの部分がもとの阿木川の川幅より倍になっていることがわかる。
道しるべ

昔の道路標識。『右へ・・・、左へ・・・』と書かれている。
久須田遺跡(くすだいせき)

平成2年に発掘が行われ、縄文時代中後期、古墳時代の遺物が出土した。
羽根坂

少し離れているが「高貝」という地名がある。ここで戦いがあって勝ったほうの軍勢がこの羽根坂まで来て分捕り品を焼いたため灰坂といったという。これが言い伝えの羽根坂であるが、「ハネ」というのは粘土が取れる土地をいうのでこの付近で粘土が取れたのであろう。
やかんころがし

むかしは杉の大木が繁り、昼でも薄暗い道であった。雨が降る日などにここを通るとやかんころがし(いたずらをするおばけ)がコロコロと落ちてくるといわれ、恐ろしいところでした。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部阿木事務所
電話番号:0573-63-2001
ファックス:0573-73-0001
メールによるお問い合わせ





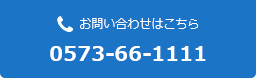
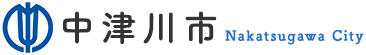
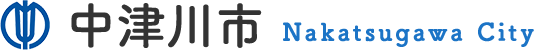
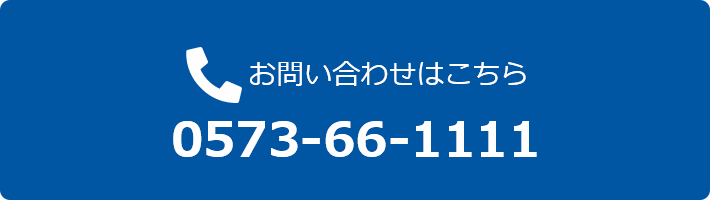

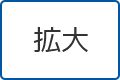



更新日:2021年06月14日