⦅資料紹介28》江戸しまん評判記 中
江戸しまん評判記 中 (えどじまんひょうばんき ちゅう)

間家資料目録No.1400

江戸の商人を役者に見立てて番付にしたものです。当館では「中」のみ所蔵ですが、本来は上、中、下の三冊本です。上巻には、凡例、江戸自慢惣役者目録、八文字足跡(はちもんじそくせき)による開口が述べられています。中巻には江戸自慢惣役者目録の「立役之部 極上上吉 越後屋八郎右衛門」から「上上 玉屋市兵衛」まで計22名の評判が記されています。下巻には「実悪之部 大上上吉 大坂屋平七」から「惣巻軸 極上上吉 白木屋彦次郎」まで39名の評判本文と「五十軒 版」と記され終わりとなります。
上巻に「高賀池内(たかがいけない)門人 柳荷五瀾(ごらん)、安永六ツのはつはる」とあり、安永六(1777)年の正月に刊行されました。中野三敏は「高賀池内の命名はおそらく平賀源内が利かせてあるに相異なく、その高弟柳荷五瀾は源内門人の代表格森島中良(ちゅうりょう)あたりを考えればちょうど良かろう」と述べています。1
開口を述べた八文字足跡についても「本書開口の筆者八文字足跡は、前年刊の初物評判記『福寿草』の開口も作っている。そして『福寿草』は既に春町か南畝あたりの関与した作であることも、明らかにされていた。春町・南畝、いずれもにしても、源内・中良とは一つ穴のむじなである。八文字足跡と名のる人物が、これら安永期を代表する戯作者の一人であることだけは、もはや確信できるだろう。」とも中野は述べています。2
この本の制作に平賀源内の門人森島中良や恋川春町、太田南畝等が関わっていたのでしょうか。
極上上吉 越後屋八郎右衛門
中巻の巻頭を飾るのは川柳伝にもよまれ、評判は三国一との呼び声高い「極上上吉 越後屋八郎右衛門」です。
越後屋は 現在の三越百貨店の元祖で、江戸で呉服店を開業しました。当時の呉服店の支払いは盆・暮の二節季払い、または12月のみの極月払いの掛け売りが慣習でしたが「現金かけねなし」の店頭販売での現金取引を奨励しました。その商売は大当たりとなり、やがて江戸の町人から「芝居千両、魚河岸千両、越後屋千両」とよばれ、一日千両を売り上げるほどに繁盛しました。

名物集商人大全
この本の後半に「名物集商人大全」(めいぶつしゅうあきんどだいぜん)と記された挿絵があります。15名の役者絵が描かれています。中巻からは「極上上吉 越後屋八郎右衛門」、「真上上吉 内田清左衛門」、「上上吉 伊勢屋四郎右衛門」、「上上吉 大坂屋孫吉」、「上上吉 四方忠兵衛」、「上上吉に少し足りない三舛屋平左衛門」、同じく「鱗形屋孫右衛門(兵衛)」「上上吉 豊嶋屋十左衛門」の計8名が描かれています。
前述の越後屋八郎右衛門は大内義弘の役者絵です。大内義弘は南北朝室町前期の実在した武将です。足利義満と対立して討伐され、堺にて戦死(応永の乱)しました。芝居における大内氏はつねに謀叛人として登場します。
五拾軒 版
下巻最後の「五拾軒 版」について、中野三敏は「この頃五拾軒といえば、同音で五十軒道、即ち日本堤から吉原の大門口までの入口を指す地名を、まず連想するのが常であろう。両脇に雑多な店が並び、その中の左側に、既に安永三(1774)年から蔦屋重三郎が本屋を開店し、安永四年からは「遊女名鑑」である吉原細見の板行を始めたばかりである。安永三年の『細見嗚呼御江戸』は鱗形屋という本屋の版ではあるが、源内が序文を書き、奥付には細見取次所として五十軒道蔦重の名も見えている。あえて本書を蔦重版にこじつけようというのではないが、内容や関係する人物の推量をおしすすめると蔦重の蔭も甚だ濃いということは言えそうにも思う」3と述べています。
「名物集商人大全」に描かれた鱗形屋孫右衛門(兵衛)は本蔵板元の役者絵となっています。鱗形屋の評判文には「細見門のいくさやぶれ、、」とも書かれており、吉原細見が鱗形屋から蔦重版へ移行していくことが推察されます。この「五拾軒 版」は蔦重版かもしれません。
当館では中巻のみの所蔵です。
1,2,3・・中野三敏『江戸名物評判記案内』岩波新書
参考
三井広報委員会・・・https//www.mituipr.com/history/edo/02/
古井戸秀夫『歌舞伎登場人物事典』白水社
中野三敏『江戸名物評判記集成』岩波書店
『広辞苑第五版』岩波書店
中津川市中山道歴史資料館
- 〒508-0041 岐阜県中津川市本町二丁目2-21
- 電話番号0573-66-6888
- ファックス0573-66-7021
- メールによるお問い合わせ






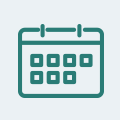
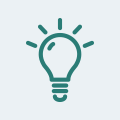







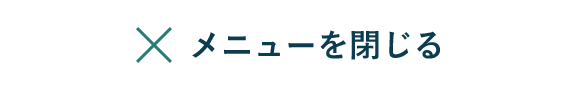
更新日:2025年08月23日