国民健康保険料
国民健康保険料の算定方式と納期が変わります
令和3年度から、前々年の所得を基に行っていた仮算定が廃止となり、前年所得を基に1年間の保険料を算定する本算定のみを行うこととなりました。
それに伴い、これまで【5月~翌年2月までの10期】であった納期が、【6月~翌年3月までの10期】となりました。
| 納期 | 納期限 |
|---|---|
| 1期 |
令和7年6月30日(月曜日) |
| 2期 | 令和7年7月31日(木曜日) |
| 3期 | 令和7年9月1日(月曜日) |
| 4期 | 令和7年9月30日(火曜日) |
| 5期 | 令和7年10月31日(金曜日) |
| 6期 | 令和7年12月1日(月曜日) |
| 7期 | 令和7年12月25日(木曜日) |
| 8期 | 令和8年2月2日(月曜日) |
| 9期 | 令和8年3月2日(月曜日) |
| 10期 | 令和8年3月31日(火曜日) |
前年所得が未申告の方には、市民保険課より「国民健康保険簡易申告書」を送付いたします。保険料軽減判定所得や保険給付にかかる所得区分を正しく判定するために必要なものですので、必ずご提出ください。
国民健康保険料算定の仕方
保険料は年度ごとに変わります 国民健康保険料は医療分、後期高齢者支援金分、介護分の保険料を3つの項目(所得割・均等割・平等割)ごとに計算し、それらを合計して一世帯ごとの年間保険料を算定します。
よって、一世帯の保険料額は、世帯(加入者)の前年中の所得額や、世帯の加入者数等に応じて年度ごとに変わります。
令和7年度の国民健康保険料が確定しました
令和7年度の国民健康保険料の料率改定を行い、今年度の国民健康保険料額が確定いたしました。
詳しくは、「令和7年度 国民健康保険料改定のお知らせ」をご覧ください。
納付の義務は世帯主に
保険料を納めるのは、国民健康保険の加入者であるなしにかかわらず、各世帯の世帯主です。
ただし、保険料がかかるのは加入者分のみとなります。
(注)国民健康保険に加入している方は、必ず所得の申告をしてください。たとえ収入がない場合でも申告が必要です。申告がないと軽減対象から除かれるなど、正確な保険適用ができません。
(注)農家が家畜市場で肉用牛を売却した場合、所得税、市県民税の所得割では免税所得の取り扱いとなりますが、国民健康保険では保険料算定所得としてみなされます。
市外から転入(税申告)された方の保険料
保険料の基礎となる前年の所得金額が未把握なため、前住所地(課税住所地)に所得の照会をして保険料を計算します。
所得状況が把握できない場合は、まず均等割額と平等割額で計算して通知し、所得状況が把握でき次第再計算をし、保険料に変更がある場合は、翌月に変更通知(納付書)をお送りします。
賦課決定の期間制限
平成27年度以降の国民健康保険料の賦課決定について、国民健康保険法第110条の2(平成27年4月施行)により、当該年度における最初の国民健康保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、賦課決定することができなくなりました。
そのため、遡って資格を喪失したり、過年度分の修正申告により、国民健康保険料が納めすぎとなった場合に、納付済み分を還付できなくなる可能性があります。
該当する方は速やかにお手続きをお願いいたします。 国民健康保険は相互扶助の制度で、もしものときの病気やけがの治療による経済的負担を軽減するため、保険料を出し合い、医療費に充てる相互扶助(助け合い)の精神をもとにした制度です。 国民健康保険は、みなさまの保険料によって成り立っています。
| 軽減基準所得 | 軽減割合 |
|---|---|
| 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 | 7割軽減 |
|
43万円+(30.5万円×被保険者数(注)) +(給与所得者等の数-1)×10万円 |
5割軽減 |
|
43万円+(56万円×被保険者数(注)) +(給与所得者等の数-1)×10万円 |
2割軽減 |
(注)同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。
低所得世帯の保険料の負担の軽減を図るため、一世帯内の加入者全員(擬制世帯主を含む)の前年中の所得の合計が、上記軽減基準所得以下の場合、均等割額と平等割額が軽減されます。
国民健康保険に加入している方は、必ず所得の申告をしてください。たとえ収入がない場合でも申告が必要です。申告がないと軽減対象から除かれるなど、正確な保険適用ができません。
国民健康保険料の減免制度
次のような事由により保険料を納付することが困難な場合、世帯の生活状況によって保険料額(全部又は一部)が減免される場合があります。
- 震災、風水害、火災、その他これに類する災害により被害を受けたとき
- 廃業、失業、疾病、その他の理由により所得が著しく減少すると認められるとき
- 特別障害者又は母子家庭の認定を受けているものの中で一定の所得以下のもの
- 社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度に移することにより、その被扶養者が国民健康保険被保険者になるとき
(ただし、国民健康保険の資格を取得した日において65歳以上の方) - 刑務所、留置所等に入っているため、医療の給付が受けられない場合
(注)減免を受ける場合には、申請書の提出が必要です。担当課の窓口までご相談ください。
(注)減免が適用された場合、手続きをとられた翌月以降の納期で保険料が調整されます。
(注)減免が適用された後でも、事実と異なることが判明した場合、減免の取り消しを行います。
非自発的に失業された方の国民健康保険料が軽減されます
対象となる方
離職日に65歳未満であって、離職日の翌日から翌年度末までの期間において
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受ける方
(注)雇用保険受給資格者証の離職理由が【11,12,21,22,31,32,23,33,34】に該当される方
軽減額
国民健康保険料は前年の所得などにより算定されます。
軽減は前年の給与所得をその30/100とみなして算定を行います。
軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です
(注)雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります
(注)国民健康保険に加入中は途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
届出に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付されます)
- 既に国民健康保険に加入されている方は国民健康保険被保険者証
- 新規で国民健康保険に加入される方は社会保険等資格喪失証明書
- マイナンバーカード
産前産後期間の国民健康保険料が軽減されます
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した国民健康保険被保険者
(注)死産、流産、人工妊娠中絶も含む
軽減される期間と保険料
出産する被保険者の出産予定月の前月から出産予定月の翌々月まで(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヶ月前から出産予定月の翌々月まで)の期間にかかる所得割保険料及び均等割保険料
届出に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 出産予定日または出産日がわかる書類(母子健康手帳など)
国民健康保険料の徴収猶予制度
著しく収入が減少し、国民健康保険料を納めることが困難になった場合など、一定の要件に該当する場合は申請により保険料の支払いを猶予する制度があります。
国民健康保険料徴収猶予申請書 (PDFファイル: 46.5KB)
(注)収入の減少を証明する書類(売上帳、現金出納簿、給与明細、預金通帳のコピー等)の添付が必要です。 詳しい申請方法については担当課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民保険課保険年金係
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
メールによるお問い合わせ





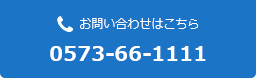
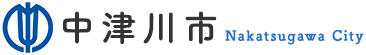
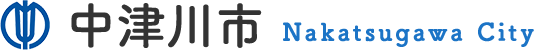
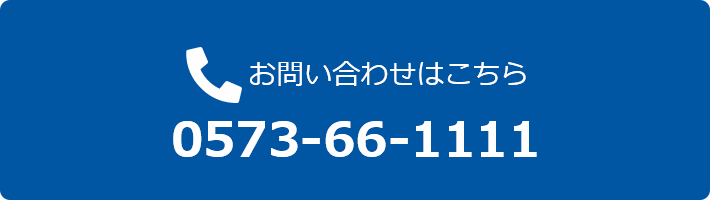

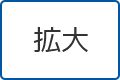



更新日:2025年06月23日