乳幼児の発達・発育
乳幼児期の発育・発達の目安や育児のポイント、お困りごとへの対応等を月齢別にのせています。育児の参考としてご覧ください。
3~4か月の赤ちゃん
昼夜の区別がつき、日中起きて過ごす時間が増えます。
体の成長
生まれた時と比べた伸び・・・身長は平均15センチメートル、体重は平均4.2キログラム大きくなります。
母子健康手帳(P46~P49)の成長曲線に記入してみてください。 大きい子も小さめの子もグラフに沿って増えていればよいです。
発達のみちすじ

運動の発達
- 1か月半から4か月:うつ伏せで45度頭をあげる
- 3か月以降:首がすわる
- 4か月以降:ねがえり
発達を促すあそび
腹ばいの体操
お母さんの見ているところで腹ばいの練習をしてあげましょう。腹ばいで顔をあげた時、目の前のお母さんと目が合うと赤ちゃんは喜び、長い間腹ばいでいられます。腕を広げすぎず、肩幅くらいの間隔で前にもっていくと、肘でしっかりと身体が支えられ、頭が上げやすくなります。
腕の体操

赤ちゃんにお母さんの親指を握らせて、他の4本の指は赤ちゃんの手首にかけます。片腕ずつ前から上にあげて下ろします。楽に上がるところまで行います。慣れてきたら両腕を同時に上げてクロスしましょう。
足の曲げ伸ばし体操

両足を一緒に曲げ伸ばしします。曲げる時は、赤ちゃんの息を吐くタイミングに合わせるつもりで行い、伸ばす時はお母さんの力をぬいて赤ちゃんにまかせます。赤ちゃんに声をかけながら赤ちゃんの足首や膝の裏を支えて行い、強く握ったり急に曲げないようにしましょう。
多いお困りごと
- 赤ちゃんに多いお悩み(湿疹、うんち、げっぷ、よく泣く、向きぐせ、しゃっくり)(PDFファイル:298.8KB)
- 生活リズム(リズム作りいつから始める?)(PDFファイル:257.6KB)
- 赤ちゃんの皮膚の病気・対処方法病気・対処方法(PDFファイル:280.2KB)
- 赤ちゃんの便秘(PDFファイル:80.8KB)
6~7か月の赤ちゃん
自分の意思で動けるようになり、だんだん行動範囲が広がる時期。赤ちゃんとのふれあい遊びが運動機能と心の発達をうながします。
体の成長
4か月からの身長・体重の伸び・・・身長は5センチメートル 体重は1キログラム大きくなります。 母子健康手帳(P46~49)の成長曲線に記入してみてください。 大きい子も小さめの子もグラフに沿って増えていればよいです。
発達のみちすじ

運動の発達
- 4か月から7か月:ねがえり
- 7か月以降:つかまり立ち
- 7か月半以降:はいはい
細かい動き
- 6か月以降:そばのオモチャに手を伸ばしてつかむ
- 6か月半以降:意味なくマママ・パパパと言う
人との関わり
- 5か月から8か月:「いないいないばあ」を喜ぶ
- 6か月半から8か月半:人見知り
発達には個人差があり幅があります。出来なくても大丈夫!関わり方については、保健センターにご相談くださいね。
運動機能の発達
ねがえり
仰向けの赤ちゃんの両手を支え、ゆっくりねじると、骨盤、背骨、肩がまわって寝返りになります。自力で寝返りのできない赤ちゃんは、両足を持ち上げると足と腰を片方向にねじります。そして手を足と同じ方向にちょっと引っ張るとクルリと寝返りします。左右交互にやってあげるうちに、自然と一人でできるようになります。
ずりばい
7~8か月ごろになると、興味のあるものに向かって、腹ばいのまま手と足を使って前に進み始めます。腹ばいの時に前から声をかけたり音の出るおもちゃで誘ったりしてあげましょう。
おすわり
6か月ごろは、一人座りがまだ不安定ですので、腰のあたりを支えてあげましょう。安定してきたら手を離して一人で座らせてあげましょう。8か月ごろには一人でお座りができるようになります。
心の発達を促すあそび
おもちゃあそび
おもちゃを赤ちゃんの目の前に出すと、手を伸ばしておもちゃを取ろうとします。遊び方の見本を見せてあげたり、赤ちゃんの手を持って一緒に遊んだりしてあげましょう。
いないいないばあ
赤ちゃんはいったん隠れた顔が思った通りに出てくると、喜びと安心感を味わいます。大人の顔を両手で隠したり、赤ちゃんの顔に布をかけたりしていないいないばあをしてあげましょう。
絵本
赤ちゃんは好奇心旺盛。絵本に触れることで、さらに興味が育っていきます。絵本に対する興味を育てるためにも、赤ちゃんと向き合ってゆったりと読んであげましょう。「読んで!」とアピールした時には、すぐこたえてあげましょう。お母さんが気持ちに応えてくれることを確認することで、信頼感が育ちます。
多いお困りごと
9~10か月の赤ちゃん
お座り~はいはい~つかまり立ちへと運動面で大きく変化のある時期です。心も「乳児から幼児」へ大きく成長します。しかし、行動範囲が広がり、興味が強くなることで、家の中での事故が起こりやすい時期でもあります。
体の成長
7か月のときと比べた伸び・・・身長はおよそ3.5センチメートル、体重はおよそ0.6キログラム大きくなります。
母子健康手帳(P46~49)の成長曲線に記入してみてください。 大きい子も小さめの子もグラフに沿って増えていればよいです。
発達のみちすじ

運動の発達
- 7か月半から10か月:はいはい
- 8か月から11か月:伝い歩き
- 7か月から10か月:つかまり立ち
細かい動き
- 9か月から12か月半:2本の指でつまむ
ことば
- 6か月から10か月:意味なくマママ・パパパと言う
- 7か月半から12か月半:身近な人が発した発音を真似ようとする
人との関わり
- 8か月から12か月:ばいばい・いやいやなどの身振りをする
発達には個人差があり幅があります。出来なくても大丈夫!関わり方については、保健センターにご相談くださいね。
10か月のポイント
安心感~子育ての基本です
赤ちゃんが出すサインを上手にキャッチし、たくさん話しかけたり、たくさん抱っこしたり、たくさん触ってあげてください。心や体を受け止めてもらえる事が"安心感"につながり、健やかな発達の基盤になります。
人見知り
8か月頃から知っているものと知らないものを区別するようになり、知らないものに対して不安が出てきます。興味はあるので抱っこや声掛けで安心させてあげる事で乗り越えられます。
指差し
10か月頃には要求の気持ちが育ち、身近な人に対し「要求の指(手)差し」が出てきます。赤ちゃんの目についたもの、指差ししたものは言葉に出して伝えてあげましょう。
共感の気持ち
お家の人と一緒に遊んで楽しい、認めてもらってうれしい共感の気持ち=「三項関係」は今後の人間関係の基盤を作ります。
あそび
10か月はやりとりあそびを楽しめるようになります。また、お家の人や友達のやる事をマネするようになります。おもちゃの「ちょうだい」「ありがとう」など受け渡しや、ボールのやりとりなどお家の人が一緒にあそんであげる事であそび方や共感の気持ちが育ちます。
家での事故
色々なものに手を伸ばしつかみ、口に入れることで、思わぬ事故が起こります。危険がないか、家の中の再チェックが必要です。危険な物は手の届かないところに片づけるなどの工夫をしましょう。
10か月起こりやすい事故と対応(PDFファイル:157.6KB)
1歳のころ
身長が伸びて指先も器用になり、自分で出来る事が増えてきました。また『自分でやりたい!』という意思が出てくるのがこの頃の特徴です。
体の成長
生まれた時と比べた伸び・・・身長は約1.5倍(約73~75センチメートル程度)、体重は約3倍(約9キログラム程度)
母子健康手帳(P46~49)の成長曲線に記入してみてください。 大きい子も小さめの子もグラフに沿って増えていればよいです。
発達のみちすじ

運動の発達
- 11か月半から1歳6か月:ほとんど転ばずひとりで歩ける
- 10か月半から1歳以降:ひとりで立つ
手先の発達
- 11か月から1歳6か月:コップから飲む
- 11か月から1歳以降:なぐり描き(持ち方:わしづかみ)
ことば
- 1歳以降:パパ・ママ以外に3語言う
- 10か月半から1歳以降:パパ・ママ以外に1つ言葉を言う
人との関わり
- 10か月から1歳以降:泣かずにほしい物をさす
- 10か月半から1歳以降:ボールのやり取り遊びをする
- 11か月から1歳以降:家事などをまねる
発達には個人差があり幅があります。出来なくても大丈夫!関わり方については、保健センターにご相談くださいね。
かかわり遊びのススメ
『自分で!』という意思が出てきて、だだこねが強くなったり、ひっくり返ったり...いろんな方法で自分の気持ちを示してくるので大変です。一緒に楽しみたい気持ちも育ち相手を求めてくるので、こんな遊びがおススメです。
- まてまてあそび
- ボール遊び
- 絵本 など
手づかみ食べのススメ
指先が器用になり親指と人差し指で物をつまめるようになります。この時期は手づかみ食べをどんどんさせてあげましょう。
目で見て、手でつかんで、口に運ぶ...この一連の動作が基になってスプーンなどの道具を上手に使えるようになります。汚れてもよい服や敷物の準備を。
ことばのこと
『マンマ』『ワンワン』など意味のある単語を口にする子が増えてきます。子どもが興味を持ったものに「○○(マルマル)だね」と目を見て反応してあげると、子どもの"伝えたい"気持ちが育ってきます。見る・触る・味わう...など、たくさんの経験を一緒にしてみてください
生活リズムのこと
早寝・早起きは子どもの心の安定や落ち着き、身体の成長を促します。 朝7時までに起き、夜は8時頃に寝られるよう、3度の食事の時間を整えましょう。寝る時間が遅くなっても、朝起きる時間は一定にしておくとリズムを整えやすいです。
1歳頃の食生活
エネルギーや栄養素のほとんどを食事からとれるようになる時期です(離乳の完了)。ただ、歯の本数や噛む力は発達段階にあるため、引き続き食べ物の大きさや固さに配慮が必要です。
お乳・ミルクのこと
お母さんに抱かれてお母さんの体温や匂いを感じて安心できる授乳タイムはお子さんの心の安定のために大切です。しかし「ぐずったら飲ませる」などのちょこちょこ飲みがあると、3度の食事の食欲を妨げ必要な栄養が体に入りません。お乳やミルクは牛乳に切り替えていきましょう。1日300ミリリットルを目安に、午前・午後のおやつに分けて飲ませます。夜のお乳は1歳3か月頃を目安に卒乳できるとよいです
哺乳瓶のこと
コップ飲みやストローが使えるようになる時期です。哺乳瓶の使用はやめていきます。はじめは小さめの浅めの口の広がったコップ(おちょこなどがお勧めです)に、少なめに入れたお水やお茶でチャレンジしましょう。初めはこぼすことも多いですが、すぐに飲めるようになります。お風呂で 遊びながら練習してもいいでしょう。
歯の健康
おおよそ上下の前歯が4本ずつ生えてきます。生え始めの時期は個人差があり、1歳を過ぎて生え始めるお子さんもいますのでこの通りでなくても心配はありません。
1歳歯科 仕上げ磨き始めていますか?(PDFファイル:535.3KB)
多いお困りごと
1歳生活リズムを整えるコツは?(PDFファイル:417KB)
1歳6か月のころ
一人で歩けるようになり全身遊びでバランス感覚が養われます。また『自分』の意思が育つ時期なので「いやいや」の対応に困る事も増えてくるのがこの時期です。
体の成長
身長は平均80.5センチメートル、体重は平均10キログラム。歯は16本。
母子健康手帳(P46~49)の成長曲線に記入してみてください。 大きい子も小さめの子もグラフに沿って増えていればよいです。
発達のみちすじ

運動の発達
- 1歳から:歩ける
- 1歳6か月前から:階段をのぼる
- 1歳6か月頃から:ボールをける
手先の発達
- 1歳過ぎから:スプーンを使って食べる
ことば
- 1歳から1歳6か月:パパ・ママ以外に3語言う
生活
- 1歳過ぎから1歳6か月過ぎ:簡単な家事のお手伝い
発達には個人差があり幅があります。出来なくても大丈夫!関わり方については、保健センターにご相談くださいね。
『自分』が育つ時期
何につけても「イヤ」「ダメ」という事が増え、おうちの方が手を焼く時期です。できない事もやりたがる等、対応に困るときは、お子さんのやりたい気持ちを受け止め、簡単な言葉でお話をしてあげてください。お子さんが自分の考えを言葉で表せるようになるまで、もう少し待っていてください。
ことばのこと
物に名前があることが理解でき、相手の問いかけに答えようとし始めます。丁寧に話を聞き、丁寧に話してあげる事で言葉の獲得に繋がっていくので、子どもの驚きや問いかけに共感しながら答えてあげましょう。
偏食・遊び食べ
食事を美味しく食べるためには「おなかが空いている事」が1番です。食事や間食は時間を決めて摂るように心がけましょう。また、「一緒に食べる人がいる」事も大切です。テレビは消して、会話と共に楽しみましょう。苦手な物は一口でも食べられたら褒めてあげると自信につながり食べられるようになる事もあります。食事時間は20分程と決めて、遊び出したら途中でも終了し、間食として出します。
トイレトレーニングの準備
この時期はオシッコを「ためる力」を育てましょう。膀胱や尿道は筋肉なので、お散歩や階段の昇り降りがおススメです。頻繁にトイレに連れて行くと「ためる力」は育ちません。オシッコの間隔が2時間くらい空いたらトイレに誘ってみましょう。
多いお困りごと
1歳6か月ことばが遅れていないかしら?(PDFファイル:77.1KB)
1歳6か月かんしゃくやパニックの対処法は?(PDFファイル:201.2KB)
2歳のころ
「自分で!」と頑固に主張します。半面、褒められる事に喜びを感じ自信につながります。
体の成長
身長の平均 85~88センチメートル、体重の平均 11~12キログラム(1年間で2キログラム増えます)
母子健康手帳(P46~49)の成長曲線に記入してみてください。 大きい子も小さめの子もグラフに沿って増えていればよいです。
発達のみちすじ

運動の発達
- 1歳6か月前から2歳:階段をのぼる、ボールをける
- 1歳6か月過ぎ以降:その場でジャンプ
ことば
- 1歳6か月過ぎから2歳6か月:2語文を話す(異なった2つの言葉をつなげる)
生活
- 1歳6か月前から2歳前:あまりこぼさずスプーンで食べる
- 1歳6か月から2歳過ぎ:上着・ずぼん・靴などをぬぐ
- 2歳前から2歳6か月:上着・ずぼん・靴などを自分でつける
発達には個人差があり幅があります。出来なくても大丈夫!関わり方については、保健センターにご相談くださいね。
ほめ方、叱り方
自分でやりたい、上手くできない、かんしゃく、駄々をこねる...。
お家の方も困る場面が増えます。どうほめて、どう叱るか、とても難しいですね。
ほめ方
ほめてもらう事、認めてもらう事は自信につながり、次に頑張る力を育てます。
- 「いいな」「がんばったな」「次もして欲しい」と思った行動は、すぐそのタイミングで言葉や態度で表現しましょう。
- 「〇〇(マルマル)できたね」「嬉しいよ」「ありがとね」など言葉で伝えましょう。
- 目を見て抱きしめる、頭をなでなでする、などスキンシップをとりましょう。
叱り方
ほめて育てたいと思っても、"やってはいけない事"を学んでいく時期でもあります。
- 危ないことをした時、人に迷惑をかけた時、社会のルールでいけない事をした時。家族の中でも基準を同じにしておくと、お子さんが迷いません。
- お子さんの目線に合わせ、真剣に、愛情をもって。
- 短い言葉で、その場で、子どもさん自身を否定せず、行動を叱る。
感情的に怒ってしまった時は子どもさんを抱きしめ「ごめんね、〇〇(マルマル)ちゃんの事大好きだよ」の一言を。
歯の健康
個人差はありますが、16本の乳歯が生えてきます。
2歳歯科 むし歯の予防と口育て(PDFファイル:413.3KB)
多いお困りごと
2歳ことばが遅れていないかしら?(PDFファイル:77.1KB)
2歳トイレトレーニングの方法(PDFファイル:54.1KB)
2歳がまん出来る子になるためには(PDFファイル:154.3KB)
2歳かんしゃくやパニックの対処法は?(PDFファイル:201.2KB)
3歳のころ
自分の考え、判断で行動しようとする意思が強くなる時期。褒められる事で相手の要求に応じようという姿勢が出てきます。
体の成長
2歳から1年間で 体重は平均2キログラム、身長は平均8センチメートル 大きくなります。
母子健康手帳(P46~49)の成長曲線に記入してみてください。 大きい子も小さめの子もグラフに沿って増えていればよいです。
発達のみちすじ
運動の発達
- 2歳6か月から3歳過ぎ:両足で前へ飛ぶ
- 3歳から:片足とび
手先の発達
- 3歳から:真似して○(マル)を描く
ことば
- 2歳6か月から3歳:たずねると氏名を答える(苗字+名前)
- 3歳前から:赤・黄・青・緑がわかる。大きい、小さいがわかる。
生活
- 2歳6か月から:ボタンをかける、声をかけると自分で服を着る
- 3歳から:ひとりで衣服の着脱ができる
発達には個人差があり幅があります。出来なくても大丈夫!関わり方については、保健センターにご相談くださいね。
身の回りの自立
- 言葉:自分の考えを言葉で表現できる。
- 身支度:自分で洋服を着替え、顔を洗うことができる。
- 食事:自分で箸やスプーンを使って食べる事ができる。
- 排泄:4歳に向けておしっこもウンチもトイレでできるようになる。
- 遊び:お母さんから離れお友達と遊べるようになります。
「自分でやる!」、 体験(上手くいった、失敗した)、 自分の判断を確認 、「自立」="人間らしく生きる脳が育つ" 子どもさんの得意や苦手があり上手くいかない事も多いですね。3歳児の特徴を踏まえたお家での取り組みのポイントを参考にしてみてください。
生活リズムを整え集団の場へ
生活リズムを調整する脳(視床下部)は4歳までに出来上がります。リズムを整え体の準備をし、気持ちよく集団生活に送り出せるように準備していきましょう。
多いお困りごと
3歳がまん出来る子になるためには(PDFファイル:154.3KB)
3歳かんしゃくやパニックの対処法は?(PDFファイル:201.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
医療福祉部健康課
電話番号:0573-66-1111
内線:予防保健係623・健康支援係(母子)626・健康支援係(成人)627
メールによるお問い合わせ





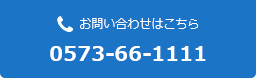
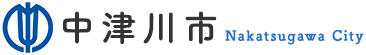
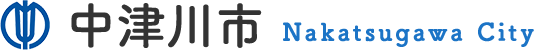
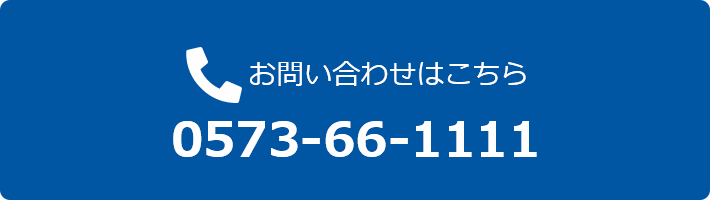

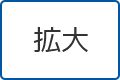





更新日:2025年07月15日